みどりII

名称:環境観測技術衛星「みどりII」/AdvancedEarthObservingSatellite-II(ADEOS-II)
小分類:地球観測衛星
開発機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))/環境庁(EA)/アメリカ航空宇宙局(NASA)/フランス国立宇宙研究センター(CNES)
運用機関・会社:宇宙航空研究開発機構(JAXA)
打ち上げ年月日:2002年12月14日
運用停止年月日:2003年10月31日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:H-IIA
打ち上げ場所:種子島宇宙センター(TNSC)
みどりIIは、5つのセンサーを搭載した地球観測衛星です。
高性能マイクロ波放射計(AMSR=Advanced Microwave Scanning Radiometer)は、地表や大気から自然に放射されるごく弱いマイクロ波を受信することで、水に関するさまざまな量(水蒸気量、降水量、海面水温、海上風、海氷など)を昼、夜の区別なく、また雲の有無に関わらず観測します。これによって、全地球規模の水循環、エネルギー循環を把握するためのデータを得ます。
グローバル・イメージャ(GLI=Global Imager)は、地球表面や雲などからの太陽反射光や、赤外放射光を多くの波長で観測することで、生物に関するさまざまな量(クロロフィル色素、有機物、植生など)や、温度、雪氷、雲の分布、分類などを測定します。そして、全地球規模の炭素循環や気候変動を把握するためのデータを得ます。
改良型大気周縁赤外分光計II型(ILAS-II=Improved Limb Atmospheric Spectrometer-II)は、南北両半球の高緯度地方の大気の微量成分(オゾン、エアロゾルなど)の高度による分布を観測します。
海上風観測装置(Sea Winds)は、海上風の方向、風速を測定します。
地表反射光観測装置(POLDER=Polarization and Directionality of the Earth'sReflectances)は、地球表面、エアロゾル、雲、海で反射される太陽光の偏光、方向性、分光特性を測定します。そして温室効果ガス増加による地球輻射の潜在的な影響、対流圏におけるエアロゾルの循環、全球的な炭素循環の解明を行ないます。
1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?
翼をひとつ広げたような一翼式(太陽電池パドル)の形をしています。本体は約6m×4m×4m、太陽電池パドルは約3m×24mの大きさです。
重量は約3.7t(打ち上げ時)/約1.3t(ミッション重量)で、姿勢制御方式は、3軸姿勢制御方式を採用しています。
みどりIIは宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))が開発した2つのセンサーのほかに、NASA、CNESなどにより開発された5つのセンサーを搭載しています。
2.どんな目的に使用されるの?
みどりIIは、みどりの観測ミッション(目的)を引き継ぐとともに、地球温暖化など、地球規模の環境変動の研究のためのデータを取ることが目的です。さらにそうしたデータを気象・漁業などへの実利用を図ること、観測技術の開発・高度化などを目的とします。
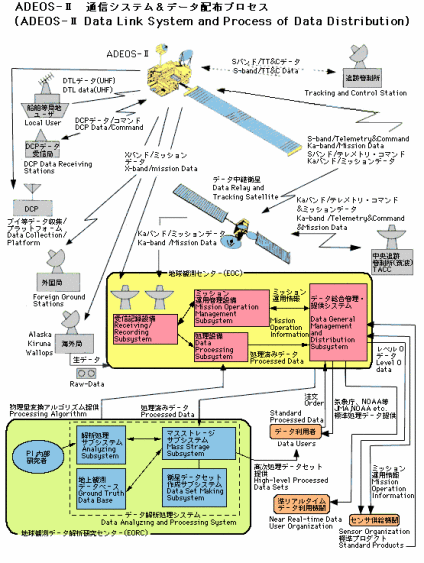
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
打ち上げ後、予定どおり軌道に乗り、高性能マイクロ波放射計や、グローバル・イメージャ、改良型大気周縁分光計II型、海上風観測装置、 地表反射光観測装置などによる地球環境の観測を行ないました。またこだまやアルテミスとの衛星間通信実験にも成功しましたが、太陽電池パドルからの発生電力が低下する異常が発生したため、現在は運用停止になり、異常発生の原因が調べられています。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
みどりがあります。
5.どのように地球を回るの?
高度802.9km。公転周期101分(地球を101分で1周します)、軌道傾斜約98.62度の太陽同期準回帰軌道です。太陽同期準回帰軌道とは、いつもほぼ同じ時刻に同一地点の上空を通過するため、観測衛星に向いている軌道です。また、地球の自転によって経路がすこしずつずれていきますが、4日後には再び同じ時刻に同じ位置にもどっています(回帰周期)。
- AdvancedEarthObservingSatellite-IIのページへのリンク
