ディー‐オー‐エッチ‐シー【DOHC】
読み方:でぃーおーえっちしー
DOHC(ディーオーエイチシー)
【スペル】DOHC
ダブルオーバーヘッドカムシャフトという方式でバルブを開け閉めするエンジン形式のこと。OHC(SOHCとも呼ぶ)では一本だったカムシャフトが2本あるので“ダブル”。また一般的に、OHCではカムシャフトがロッカーアームというシーソーのようなパーツを押すことによってバルブを遠隔操作していたが、多くのDOHCは直接バルブを押すため高回転向きで、その分だけパワーを出すことが可能といわれている。OHCエンジンをハイパワー化(高回転化)するために考案された機構で、現在、高性能とうたわれるモデルのほとんどはDOHCが採用されている。 カムシャフトが2本あることから、ツインカムとも呼ばれている。
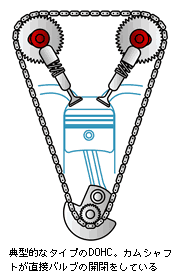
【関連用語】アメリカン カムシャフト シングル
DOHC
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/11/06 16:22 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2015年9月)
|
DOHC (ディーオーエィチシー) とは、Double OverHead Camshaft(ダブル・オーバーヘッド・カムシャフト)の略で、レシプロエンジンにおける吸排気弁機構の形式の一つ。

(ジャガー製XKエンジン ジャガー・XK150搭載。カムシャフトカバーが並列配置となり、ヘッド中央に点火プラグが配置される)
特徴

(トヨタ製・1NZ-FE型(直動式バルブ仕様) 今日のDOHCエンジンはシリンダーヘッドカバーがアルミダイカスト、または耐熱樹脂で出来ており、一部の車種を除きシリンダーヘッドカバーは耐熱樹脂製の化粧カバーで覆われるようになった)



排気バルブと吸気バルブが別々のカムによって開閉される。
シリンダーヘッドにおけるバルブの駆動について、吸気側と排気側で別々のカムシャフトを備えるものを指す。これにより
- カム軸配置の自由度
- ポート形状・バルブ配置設計の自由度
- 燃焼室形状設計の自由度
- 動弁系慣性質量およびフリクションロスの軽減
といった面でSVやOHV、SOHCに対し優れる。これらにより
- 高回転高出力、低公害低燃費といった要求にあわせた設計
- 各種可変バルブ機構の取り込み
も比較的容易となる。欠点としては
- 部品点数が増えて機構が複雑になりコストがかかる
- カムシャフトが1ヘッドにつき2本になるためシリンダーヘッドが大型化しエンジン重心が高くなる
といったものがある[1]。
歴史
1912年に、エルネスト・アンリがフランスのプジョーのレーシングカーのために開発したのが最初であるとされるが、スペインのイスパノ・スイザの設計者マルク・ビルキヒトによる着想を剽窃したという説もある。
部品点数が多く機構が複雑であることから、1950年代以前はレーシングカーや高級スポーツカーに限定された技術であった。
第二次世界大戦後、戦前からDOHCエンジンを積極的に手掛けてきたアルファロメオが量産に転じたほか、ヨーロッパや日本の大手自動車メーカーは、従来の量産エンジンを元にヘッド部分をDOHC形に改造した高性能エンジンを開発、スポーツモデルに搭載して市場に送り出した。
日本で初めてDOHCエンジンを搭載した市販4輪自動車は、1963年に発表された軽トラックのホンダ・T360である。このDOHCエンジンは高速走行性能を確保するために搭載されたものであり、T360より遅れて開発が始まったスポーツ360には同エンジンに更にチューンを加えたものが搭載されていた[注釈 1]。その後、2ストローク機関のものが数多く存在するオートバイにおいてもDOHCは広く採用されるようになった。日本のオートバイでは1965年にホンダ・CB450、1972年にはカワサキの輸出専用車種Z1[注釈 2]などがDOHCエンジンを搭載した。
本来スポーツモデル向けの機構と見なされてきたDOHCであるが、トヨタ自動車は吸排気効率を高めつつ理想的な燃焼室形状を確保できる自由度の高さに着目し、省燃費化・低公害化の手段として実用車向けの普及型DOHCエンジン(ハイメカツインカム)を開発した。1986年8月以降、同社のガソリンエンジン乗用車のほとんどに採用された[注釈 3][注釈 4]。
以来、量産型DOHCエンジンは世界の多くのメーカーに普及している。軽自動車においても1990年代頃からDOHC化が進み、2021年のホンダ・アクティトラックの生産終了・販売終了によって全車DOHCとなった。さらに排ガス規制強化により、ディーゼルエンジンも燃料噴射弁をピストン直上に置くことのできるメリットのあるDOHCを広く採用するようになった[2]。
名称について
「ツインカム(TWIN CAM)」と呼ばれることもある[1]。四輪ではトヨタ[注釈 5]と日産[注釈 6]、スズキ、ダイハツが、二輪ではカワサキがこの呼称を採用している。“Twin”は明らかに「2組」となってしまうため、トヨタではV型エンジンなどについては“FOUR CAM”と呼称を分けていた。
例外的にハーレーダビッドソンは自社のカムシャフトが2本のV型2気筒OHVエンジンをTWINCAMと称している。これは自社の従来のエンジンのカムシャフトが1本だったことから、それらと区別するためである。
表記はトヨタが「TWINCAM24(4バルブ6気筒)」「TWINCAM16(4バルブ4気筒)」「TWINCAM20(5バルブ4気筒)」、日産は「TWINCAM 24VALVE(4バルブ6気筒)」「TWINCAM 16VALVE(4バルブ4気筒)」、ダイハツが「TWINCAM-16V(4バルブ4気筒)」「TWINCAM-12V(4バルブ3気筒)」となる。
また別名では、主に直列型エンジンがTWIN CAM、V型および水平対向型エンジンがそれぞれFOUR CAMなどと呼ばれる。
マルチバルブ
4ストロークエンジンにおいて、1つのシリンダーに3つ以上のバルブを持つことをいい、そのエンジンのことをマルチバルブエンジンという。一部にSOHCやOHV(OHVの場合は一部のオートバイあるいは産業用、農業機械用を含むディーゼルエンジン)のマルチバルブエンジンが存在するものの、DOHCの方が普通であり[3]、前述のプジョーの最初のDOHCエンジンも同時に最初のマルチバルブエンジンでもあった。両者は密接な関係にある。
その他の動弁機構--歴史順
脚注
注釈
- ^ スポーツ360は諸般の事情により市販には至らなかったものの、後に排気量を531 ccに拡大した同DOHCエンジンを搭載するS500が発売された。
- ^ 翌年には排気量を750ccに変更した日本向けモデル750RS(Z2)が登場している。
- ^ 点火プラグをシリンダー直上に配置できることも重要な利点である。
- ^ カムリ/ビスタを皮切りに、カローラ・スプリンター・コロナ ・カリーナ・マークII・クラウン・スターレットなど。1994年1月以降はカローラバン/スプリンターバンなどの一部のガソリンエンジン商用車に搭載するようになった。
- ^ 2T-G系などが主力の時代はDOHCと称している。
- ^ FJ20系しかDOHCエンジンがなかった時代にはDOHCと称している。
出典
- ^ a b GP企画センター 1999, p. 55.
- ^ 森慶太 (2001年3月29日). “「なぜディーゼルにDOHCが必要なのでしょうか?」”. webCG. 2023年7月20日閲覧。
- ^ GP企画センター 1999, p. 59.
参考文献
- GP企画センター(編)、1999、『エンジンの基礎知識と最新メカ』、グランプリ出版 ISBN 4-87687-207-4
- GP企画センター(編)、2000、『新版 クルマのメカ入門』、グランプリ出版 ISBN 4-87687-215-5
関連項目
DOHC
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/07/26 07:01 UTC 版)
「ホンダ・ZC型エンジン」の記事における「DOHC」の解説
ホンダ・S800の生産終了から14年ぶりに復活したDOHCエンジンで、動弁系以外の基本構造はEV型及びEW型のものが踏襲された。ボアストローク比はDOHCエンジンとしては異例のロングストローク型で、軽量コンパクトながら中・低速域のトルクも高く、同機種を搭載したシビックなどがモータースポーツ(JTC、N1耐久など)で活躍した。 軽量のアルミ製シリンダーブロックが採用された本体は、吸・排気バルブがそれぞれ2個ずつ設けられ、タイミングベルトで駆動されるカムシャフトにより内側支点のスイングアームを介し開閉される。点火プラグが燃焼室の天井中央部に取付けられている。 PGM-FI仕様が基本的なモデルであるが、一部車種にシングルキャブレター仕様も存在する。PGM-FI仕様はインテークマニホールドの各気筒のポートにインジェクターが取付けられたマルチポイント式で、インテークマニホールドに可変吸気装置が装備されているものもある。ES型と同様CVCCが採用されておらず、三元触媒が採用されたほか、キャブレター仕様では排気2次エアー供給システムも装備されている。
※この「DOHC」の解説は、「ホンダ・ZC型エンジン」の解説の一部です。
「DOHC」を含む「ホンダ・ZC型エンジン」の記事については、「ホンダ・ZC型エンジン」の概要を参照ください。
DOHCと同じ種類の言葉
- DOHCのページへのリンク
