てんま

名称:第8号科学衛星「てんま」/Astronomy Satellite-B(ASTRO-B)
小分類:科学衛星
開発機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
運用機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げ年月日:1983年2月20日
運用停止年月日:1988年12月17日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:M-3S
打ち上げ場所:鹿児島宇宙空間観測所(KSC)
国際標識番号:1983011A
てんまは、X線星、X線銀河、ガンマ線バースト、軟X線星雲の観測を行なうX線天文観測衛星です。はくちょうに続く、日本で2番目のX線天文観測衛星です。はくちょうは中性子星を主体とするX線パルサーや、X線バースト源など多くのX線天体を観測し、成果をあげてきました。てんまは、はくちょうよりも格段にすぐれた分解能力のある観測装置により、中性子星や活動銀河の観測を行ない、はくちょうによって明らかになった問題の解明につとめました。とくに中性子星の構造の解明に、大きな役割を果たしました。
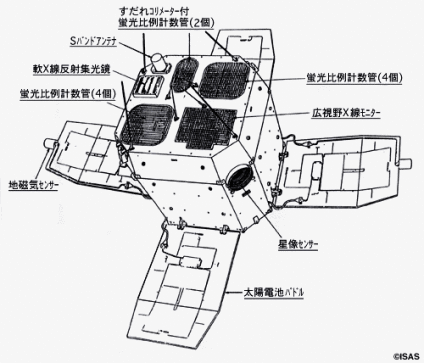
「てんま」外観図
ほぼ8角柱の本体に、四方に羽根のような太陽電池パドルがついています。大きさは対面寸法最大94cm、高さ89.5cmで、重量は216キログラムです。てんまには、3種類のX線観測装置がのせられています。主観測装置は蛍光比例計数管で、これはエネルギー分解能に優れた、新しい型のX線検出器です。蛍光比例計数管を本格的に宇宙観測に用いるのは、これが初めてのことでした。この他に、軟X線を観測する軟X線反射集光鏡装置、広い視野をもち、多くのX線天体の変化や、出現・消滅を監視する広視野X線モニター、放射線帯の検知とガンマ線バーストの記録を行なう検出器を搭載しています。
2.どんな目的に使用されるの?
X線天文観測衛星とは、超新星や白色わい星や中性子星のまわりの高温のガスが放射するX 線を観測することによって、宇宙の爆発現象を明らかにする衛星です。X線は大気に吸収されてしまうので、大気圏外に出ないと観測できません。そのためにてんまのような、X線天文観測衛星が打ち上げられ、X線星、X線銀河、ガンマ線バースト、軟X線星雲の観測を行なっています。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
ほ座のX線パルサーVelaX-1の観測、ケンタウルス座のCenX-3の観測、かみのけ座の銀河集団のX線スペクトルの観測、じょうぎ座のバースト源MXB1636-53などの観測を行ないました。軌道上の宇宙天文台として全国の科学者や、外国の天文台との共同観測などに活躍しました。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
ひのとり、ぎんが、あすか、ASTRO-Eがあります。
- 第8号科学衛星「てんま」のページへのリンク
