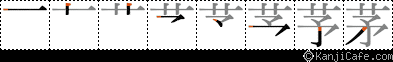かや【×茅/×萱】
ち【×茅】
ち‐がや【×茅/×茅×萱/白=茅】
読み方:ちがや
イネ科の多年草。原野に群生し、高さ約60センチ。晩春、葉より先に「つばな」とよぶ円柱状の花穂をつける。根茎を漢方で茅根(ぼうこん)といい、利尿・止血薬とする。しげちがや。《季 秋》「すごすごと日の入る山の—かな/紅緑」

ぼう【×茅】
ちがや (茅)









●わが国の各地をはじめ、アジアやアフリカに広く分布しています。山野にふつうに生え、高さは30~50センチになります。根茎で広がり、葉は広線形でまとまってつき、冬には先端が赤みを帯びます。茎の節にだけ、白色の長毛があります。5月から6月ごろ、茎頂に尾状花序をつけます。小穂の基部には長い絹毛が密生し、銀白色がよく目立ちます。若い花穂は茅花(つばな)と呼ばれ、甘みがあるのでむかしは子どものおやつにされたそうです。漢方では根茎を茅根(ぼうこん)と呼び、利尿や消炎、止血などに用います。別名で「ふしげちがや(節毛茅)」とも呼ばれます。
●イネ科チガヤ属の多年草で、学名は Imperata cylindrica var. koenigii。英名は Japanese blood grass。
| チカラシバ: | ペンニセツム・バーガンディジャイアント ペンニセツム・パープルマジェスティ 力芝 |
| チガヤ: | 茅 |
| チゴザサ: | 稚児笹 |
| チヂミザサ: | 縮み笹 |
| チャスマンティウム: | ワイルドオーツ |
茅
茅
茅
茅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/17 14:30 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2013年6月)
|

茅(かや)は、古くから[いつ?]屋根材や飼肥料などに利用されてきた、イネ科[1][2]あるいはイネ科およびカヤツリグサ科[3]の草本の総称である。
カヤと呼ばれるのは、細長い葉と茎を地上から立てる一部の有用草本植物で、代表種にチガヤ、スゲ、ススキがある[3][4]。
ススキを特定的に意味することもある。総称が本義でススキの意が派生[3]だが、逆に、ススキが本義で意味が広がった[2]とも。
名称
語源
語源には諸説あり、屋根を葺くことから刈屋あるいは上屋[3][1]、あるいは朝鮮語起源[1]とも。
漢字
「茅」は元来はカヤの1種のチガヤの意味で、カヤ全体の意味に広がった[3]。
「萱」とも書くが、この字の本来の意味は「ワスレグサ」であり、「かや」と訓ずるのは国訓である[5]。元来は『和名抄』や『名義抄』で「萓」(下が亘でなく且)と書かれていたのだが、誤って「萱」となった[3]。
特徴
イネやムギなどの茎(藁)は水を吸ってしまうのに対し、茅の茎は油分があるので水をはじき、耐水性が高い。
利用
材料
耐水性の高さから、茅の茎は屋根を葺くのに好適な材料となり、明治期以前の日本では重要な屋根材として用いられた。
屋根を葺くために刈り取った茅をとくに刈茅(かるかや)と呼び[6]、これを用いて葺いた屋根を茅葺(かやぶき)屋根と呼んだ。
現在でも、菅笠をはじめとする各種民芸品や、茅の輪(ちのわ)などが茅を編んで作られている。
その他
かつて[いつ?]の農村では牛など家畜の飼料、田畑の肥料、燃料などさまざまな利用があった。
収穫
このように重要であった茅を確保するために、往時[いつ?]の農村では、集落周辺の一定地域を茅場とし、毎年火を入れて森林化の進行を防ぎ、そこから茅を収穫することが普通であった。
言葉
主な種類
カヤが和名に付く種は多く、ほとんどがイネ科である。
カヤが和名に付く代表的な種と、それ以外でもカヤの例とされる種を挙げる。
イネ科
- ヨシ Phragmites australis
- ススキ Miscanthus sinensis
- スゲ[3][4] Carex spp.
- オギ[1] Miscanthus sacchariflorus
- イタチガヤ Pogonatherum crinitum
- オカルガヤ Cymbopogon tartilis var. goeringii
- カモガヤ Dactylis glomerata - 帰化植物
- キツネガヤ Bromus pauciflorus
- チガヤ Imperata cylindrica
- ネズミガヤ Muhlenbergia japonica
- メカルガヤ Themeda japonica
- メリケンカルガヤ Andropogon virginicus - 帰化植物
カヤツリグサ科
無関係なもの
裸子植物のカヤ(榧、イチイ科の木本)およびイヌカヤ、カヤツリグサ(蚊帳吊草)の「カヤ」は「茅」とは無関係である。
関連項目
脚注
茅(かや)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/30 22:29 UTC 版)
維新前、小此木家に仕えていた中間・茂作の娘。算術の心得があった父が、会計役として宮仕えの身となり経済的余裕ができたため、静より先に山手女学院に入学していた。
※この「茅(かや)」の解説は、「夜明け後の静」の解説の一部です。
「茅(かや)」を含む「夜明け後の静」の記事については、「夜明け後の静」の概要を参照ください。
茅
茅
「茅」の例文・使い方・用例・文例
茅と同じ種類の言葉
- >> 「茅」を含む用語の索引
- 茅のページへのリンク