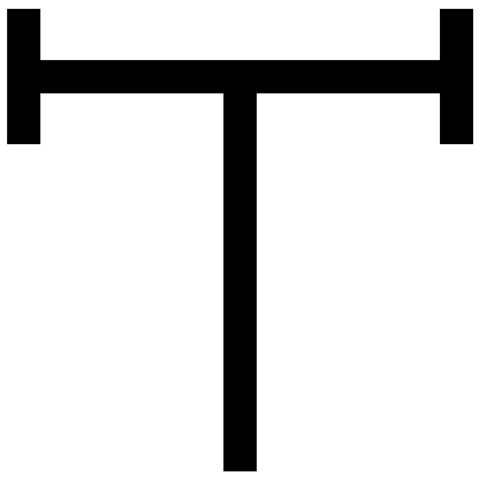きしょう‐だい〔キシヤウ‐〕【気象台】
気象台
気象台
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/02 00:13 UTC 版)
気象台(きしょうだい、英: Meteorological Observatory)とは、日本における気象庁の機関のひとつであり、国土交通省設置法で規定されている。地上気象観測(天気)だけではなく、地震・火山・海洋などの観測も行なう。また、過去観測した気象を公的に証明する気象証明を発行する業務もある。
なお、気象庁では特定の気象台および気象観測所、測候所、さらに海洋気象観測船、南極の昭和基地において、上空(高層域)の気象状況を観測している。高層気象観測では、測定器を上空に飛ばして計測するラジオゾンデと、上空に電波を発射し、反射した電波を観測するウィンドプロファイラを実施している[1][2]。
語源
明治初期の日本の近代気象観測が始まったころ、気象観測を行う施設は気候測量場や測候所と呼ばれていた。鯉沼寛一によると、1880年(明治13年)長崎測候所の月報の発行元として「東京測候所」が「地理局気象台」に変わったことが確認でき、この頃から日本で「気象台」の語が使われ始めた。増えつつあった測候所に対して、東京の拠点がその中枢であることを示すための表現と考えられる。なお、当時は内務省地理局下の各測候所とは別に、海軍省水路寮の観象台も天文と気象の観測を行っていたことからその影響も考えられる。1887年には東京気象台が中央気象台に改称し、後の気象庁に至る。気象庁編の『気象百年史』や同庁ホームページでは1875年(明治8年)6月1日東京における気象観測開始を東京気象台の設置としているが、鯉沼によれば当時のジョイネルによる観測記録にある"Imperial Meteorological Observatory, Tokio, Japan"を後年邦訳したものと考えられる[3][4][5]。
気象台・測候所等の種類
施設等機関
- 高層気象台
- 高層気象の観測や研究、高層気象観測用測器の点検校正等の業務を行う。
地方支分部局

- 地方気象台(一般) - 50気象台
- 測候所(一般) - 2測候所
- 分担気象官署として、気象庁予報警報規程第 10 条及び第 12 条に基づき、府県予報区担当官署以外に波浪予報、気象の注意報・警報の発表を行うことができる。
- 帯広(北海道)・名瀬(鹿児島県)
航空気象に特化した組織
各空港に所在する。それぞれ地域分掌組織と同等であり、本来ならば分ける必要はないが、業務が大きく異なるため別記した。
組織再編
測候所の縮小
かつては気象台と併せて100か所を超える測候所での有人観測観測を行っていたが、観測技術の高度化や経費節減の要請により基本的に無人化された。地方気象台の管轄が広い北海道十勝地方の帯広と鹿児島県奄美大島の名瀬の2か所が有人の測候所として存続している。
空港出張所等の廃止
航空地方気象台や航空測候所の下に所属し各地の空港に設置されていた空港出張所や空港分室は、観測の機械化や観測業務の民間委託が進められ、航空気象観測所に移行した。
海洋気象台の廃止
1920年から2013年9月まで、海洋や海上気象を主な担当とする組織として存在したが、組織改組によって消滅した。
観測の自動化
特別地域気象観測所、ほとんどの地方気象台などでは、地上気象観測装置の観測と気象衛星やレーダーのデータを組み合わせ、目視で行われていた天気の記録(晴れ・曇りの判別、雨雪判別)や雷の記録を代替している[6]。
航空気象観測でも、自動観測の導入が進められている[7]。
気象官署ではない有人観測所
測候所や気象台(気象官署)ではないものの有人拠点となっている観測所としては、小笠原諸島・父島(東京都小笠原村)の父島気象観測所、南鳥島の南鳥島気象観測所、館野(茨城県つくば市)の高層気象台が挙げられ、いずれも高層気象観測(ラジオゾンデ放出)などが行われている[8]が、予報・警報は行わないため、施設等機関に位置付けられている[6]。
関連項目
脚注
出典
- ^ ラジオゾンデによる高層気象観測について
- ^ ウィンドプロファイラの概要について
- ^ 鯉沼寛一「内務省における気象観測の開始の経緯と気象台の名称」、日本気象学会、『天気』、16巻、3号、1969年
- ^ 「グロッサリー > 中央気象台」、国立公文書館アジア歴史資料センター、2022年9月25日閲覧
- ^ 鯉沼寛一「日本における初期の気象組織の形成」、『城西大学教養関係紀要』1巻、pp.77–88、1977年 doi:10.20566/09125299_1_77
- ^ a b 「地上気象観測」、気象庁、2023年2月17日閲覧
- ^ 「航空気象観測の完全自動化」、気象庁、2023年2月17日閲覧
- ^ 「ラジオゾンデによる高層気象観測」、気象庁、2023年2月17日閲覧
外部リンク
- 各地の気象台の一覧 - 気象庁ホームページ内にある全国の気象台一覧
気象台
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/04 20:52 UTC 版)
気象台は7か所あり、その地域を管轄する地方気象庁に属している。気象観測所より多くの気象公務員が勤めており、気象観測所で観測する気象要素の気圧、気温、風向、風速、湿度、降水量、降雨の有無、日射量、日照時間、地面の温度、初霜温度などは縦貫気象観測装備(ASOS)で自動観測し、天気、視程、雲量、雲形、蒸発量、地中温度などは1時間ごとに手動観測する。積雪量は自動積雪観測装備または積雪板(または雪尺)で観測する。気象台では管轄地域の局地予報をする。
※この「気象台」の解説は、「大韓民国気象庁」の解説の一部です。
「気象台」を含む「大韓民国気象庁」の記事については、「大韓民国気象庁」の概要を参照ください。
「気象台」の例文・使い方・用例・文例
気象台と同じ種類の言葉
- 気象台のページへのリンク