お‐ちゅうげん【▽御中元】
読み方:おちゅうげん
「中元2」に同じ。
お中元
お中元・暑中見舞(残暑見舞)
贈答習慣
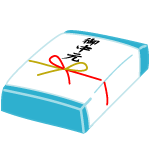
- お中元
- 中国古来のまつりごとである上元・中元・下元の三元の内、7月15日の中元と日本古来のまつりごとの一つである7月の御霊祭における贈答習慣に加えて、伝来した佛教の7月15日に行われる盂蘭盆会とが重なったことから、お中元の贈答が盛んに行なわれるようになったようです。
- 暑中見舞い
- 暑中見舞いのご挨拶は、土用(7月19、20日〜8月6、7日)の18日間に行なうのが礼儀です。御中元の贈答時期が忌中に掛かって外す場合は、この期間に暑中見舞いとして贈ります。
贈答時期
- お中元
- 関東地方では新暦で行うことから7月初めより中頃までに、関西地方では旧暦で行うことから1ヶ月遅れの8月初めより中頃までに贈るのが一般的です。
- 暑中見舞い
- 土用の内に贈ります。尚、立秋(8月7、8日)が過ぎたら「残暑見舞い」になりますので注意が必要です。暑中見舞いの「はがき」などの挨拶文も同様です。
お返しの次期
- お中元
- お互いに贈りあうことがお返しになり、また習慣ともなっています。 お中元返しをしない場合は、届いたその日の内に電話や礼状で感謝の気持ちを伝えるようにします。
- 暑中見舞い
- お見舞いを受けたら、その日の内に先ず一言お礼の電話か礼状を送ります。気になる方にはお見舞い返しとして御礼を、訪問を受けた場合も御礼の手土産を差し上げるのが礼儀です。
ひとくちMEMO
- 東日本では7月初めより中頃までの間に中元を贈る。それ以降は暑中見舞いにて贈る。西日本では1ヶ月遅れの8月初めより中頃までの間に贈る。特にお返しの必要はないが電話か手紙でお礼の心を伝える。気がすまない場合はお中元を贈るのもよい。当方又は先方が喪中の場合でも、お中元を贈ることに差し支えはないが、忌中(忌明け祭前)の場合や気になる場合は、時期をずらして暑中見舞い(立秋まで)や残暑見舞い(立秋以降)の形で贈るのもよい。
- 古く中国から伝わった三元と称して、贖罪(代償物によって過去に犯した罪業をあがなうこと)の日とした上元(1月15日)・中元(7月15日)・下元(12月15日)の内の中元が、日本古来の御魂祭り(1年を2回に分けて先祖の霊を迎えてお供え物や贈り物をした習し)と、伝来した佛教の盂蘭盆会(7月15日)とが重なって、現在の中元贈答習慣が根付いた。
ご贈答のマナー
| 贈答様式 | 贈り元 | 献辞(表書き) | 慶弔用品 |
|---|---|---|---|
| お中元を贈る | 当方 | 御中元 | 【のし紙】花結び祝 |
| 暑中見舞を贈る | 当方 | 暑中御見舞 残暑御見舞 |
使用例(のし紙/金封/のし袋の様式)
| のし紙/金封/のし袋の様式 | 使い方 |
|---|---|
 |
中元
(お中元 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/07/08 08:11 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2012年7月)
|
| 中元節 | |
|---|---|

|
|
| 正式名称 | 仏教:盂蘭盆経 (簡体字: 盂兰盆; 繁体字: 盂蘭盆; 拼音: Yúlánpén) 道教と中国民俗:中元 (中元节; 中元節) |
| 別名 | 中元月 |
| 挙行者 | 仏教, 道教, 中国民俗信仰 主に中国、ベトナム、台湾、韓国、日本、シンガポール、マレーシア、インドネシア。関連する祭りがカンボジア、ラオス、スリランカ、タイにある。 |
| 趣旨 | あの世の門が開かれ、すべての霊が食べ物や飲み物を受け取ることができるようになる. |
| 日付 | 旧暦7月15日の夜 |
| 2024年 | 8月18日 |
| 2025年 | 9月6日 |
| 行事 | 祖先崇拝、(僧侶と故人に)食べ物を提供し、冥銭を燃やし、聖典を唱える。 |
| 関連祝日 | お盆 (日本) Tết Trung Nguyên (ベトナム) 百中(百種)[1] (韓国) 亡人節 (カンボジア) Boun khao padap din (ラオス) 施餓鬼 (スリランカ) Sat Thai (タイ) |
| 中元 | |||||||||||||||||||

中元節での供物
|
|||||||||||||||||||
| 繁体字 | 盂蘭盆節 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 簡体字 | 盂兰盆节 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 別名 | |||||||||||||||||||
| 中国語 | 鬼節 | ||||||||||||||||||
| 文字通りの意味 | Ghost Festival | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
中元(ちゅうげん)は、道教に由来する年中行事で三元の1つ。仏教では盂蘭盆節(うらぼんせつ)と呼ぶ。もともと旧暦の7月15日に行われていたが、現代の日本では新暦の7月15日または8月15日に行われる。この時期に、世話になった人々に贈り物をする習慣を特に「お中元」とも呼ぶ。
中国では、旧暦7月15日を鬼節と呼び、旧暦7月を鬼月として、祖先の霊が下界に出てくると考えいる。 清明節(春)や重陽節(秋)のように、現世の子孫が亡くなった祖先に敬意を表するのとは異なり、亡くなった祖先が生きている人に会いに来るとされる[2]。
その15日目には、天界・地獄・現世の世界がつながり、道教および仏教においては、故人の苦しみを浄化するための儀式を行う。鬼月の本質は死者への崇拝であり、伝統的に子孫の親孝行は死後も祖先に及ぶとされている。清明節と鬼節の違いは、清明節では同世代と若い世代を含めたすべての故人に敬意を払うのに対し、鬼節では古い世代にしか敬意を払わない点である。中元においては、紙製の船や灯篭を川に流すことがあるが、これは祖先の失われた霊に道しるべを与えるという意味がある[3]。
歴史
中元は三元の一つで、地官大帝(もしくは赦罪大帝。舜と同一視される)の誕生日であり、様々な罪が赦される贖罪の行事が催される。また、地官大帝は地獄の帝でもあるため、死者の罪が赦されるよう願う行事も催される。
中国仏教では、この日に祖霊を供養する盂蘭盆会を催すようになった。仏弟子の目連が毎年、亡母を供養した日とされるが、原始仏教には祖霊供養の習慣はなく、中国で生まれた創作話であり、日付も中元に付会させた後付けとされる。なおインド仏教には盂蘭盆(ウランバナ、倒懸)という用語はあるが、これは年中行事とは関係ない哲学的概念であり、行事としての盂蘭盆会は中国起源である。盂蘭盆会は中元と習合し、一体化した。
日本では、盂蘭盆会は道教を通じて習合し、お盆の行事となった。江戸時代には、盆供(先祖への供物)と共に、商い先や世話になった人に贈り物をするようになり、この習慣を特に中元と呼ぶようになった。
時期
日本以外では旧暦7月15日である。日本では明治の改暦により、お盆のように、地域により7月15日または8月15日となった。
大まかに言えば、東日本(特に関東)では7月15日、西日本(特に関西)では8月15日だが、全国的には7月15日が標準とされ、8月15日のお中元を「月遅れ」と呼ぶ。ほとんどの地域でお盆と同じ日付だが、異なる地域もあり、関東地方の一部ではお中元は7月15日だがお盆は8月15日である。
ただし、贈答はこの日付ちょうどでなくとも、この日付までに送ればいい(特に配送の場合)。少々の遅れも格段問題とはされず、「月初めから15日ごろまで」等とされる。
習俗
 |
この節の加筆が望まれています。
|
日本


世話になった人々や、仕事で付き合いがある人々に、贈り物をする。江戸時代に風習として定着した。現代では形式的な贈答を互いにやめる人・企業も多い。お中元の市場規模は約7821億円(2018年時点の矢野経済研究所による推計)で、年々減少傾向にある[4]。
表書きの文面や、季節の品揃えを別にすれば、歳暮とおおよそ同じである。
中元の時期が過ぎた8月下旬から9月上旬にかけて、売れ残った中元用ギフトの商品をバラ売りする「解体セール」が百貨店やスーパーマーケットなどにて行われている[5]。
中国

盂蘭盆会と習合しており明確には区別できない。ただし、盂蘭盆会は仏教行事であるため祖霊供養だが、中元では祖霊に限らず供養する。中元を称するイベントとしては、閩南(福建省南部)で中元祭が催される。
台湾
スリランカ
関連項目
脚注・出典
- ^ 参考:en:Miryang Baekjung Festival(密陽百中ノリ、慶尚南道密陽市、韓国の国家無形文化財第068号、ノリは韓国語で遊びのこと)
- ^ “Culture insider - China's ghost festival”. China Daily. (2014年8月8日). オリジナルの2017年11月7日時点におけるアーカイブ。 2017年11月1日閲覧。
- ^ “Chinese Ghost Festival - "the Chinese Halloween"”. Peoples Daily (English). (2009年10月30日). オリジナルの2017年11月7日時点におけるアーカイブ。 2017年11月1日閲覧。
- ^ お中元、生活スタイル映す「一人用・調理簡単」ニーズ増『朝日新聞』朝刊2018年6月26日(生活面)2018年7月12日閲覧
- ^ 札幌テレビ (2024年8月21日). “最大50%オフ 円安で高騰の商品を格安販売 訳ありのミカンを使ったジュースも 札幌の百貨店”. 日テレNEWS NNN. 2025年1月10日閲覧。
「お中元」の例文・使い方・用例・文例
- お中元のページへのリンク



