ステージア
この車名は、stage(ステージ)にadvanceのaを組み合わせた造語。一歩進んだ、新しいライフステージを提案するというところからきている。スカイラインのワゴン版といえるクルマ。96年9月デビュー。全長4800mm、全幅1755mmという大型のFRワゴンで、2列シートをもち、定員5名。エンジンはすべてガソリンの直6で、2L、2.5L、2.5Lターボの3種、駆動方式は2WD(後輪)と4WDをラインアップ。リヤシートは6:4の分割可倒式で、8段階のリクライニングのほか、荷物を積む際、ワンタッチレバーで後席を前へ倒せるのが特徴。
98年8月にマイナーチェンジし、ヘッドランプ、フロントグリル、バンパーなどのデザインを改めた。室内ではシート、トリム生地などを変更。2.5Lターボはネオストレート6、RB25DETに換装。続いて2000年6月にスポーティなRSシリーズにRB20DEエンジン搭載車を追加。また、カスタマイズグレードのタイプBを新設定した。
2001年10月、V35スカイライン・ベースの2代目が登場、FMパッケージの踏襲で、エンジンもV6オンリー(2.5/3L)となり、直6タイプは姿を消した。グレードはRXとRSの2シリーズのほかに、別格としてワゴンとSUVのクロスオーバービーグルAR-X four(All road X・Cross over Vehicleの略)を設定する。通常グレードの駆動方式は2WDと4WD、ミッションは4速、5速のマニュアルモード付きフルレンジ電子制御ATが付く。AR-X fourはVQ25DETを積み、専用パーツで内外を固め、最低地上高も基準車に対して40mm高い。アテーサE-TS、ビスカスLSD、電動スーパーハイキャスというハイメカを搭載する。
2002年10月、オーテックジャパンがモディファイしたエアロセレクションを設定。2003年6月にも同社モデファイのアクシスを追加した。
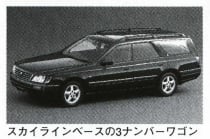
ステージア
(stage a から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/10/13 12:06 UTC 版)
ステージア (STAGEA)
 |
このページは曖昧さ回避のためのページです。一つの語句が複数の意味・職能を有する場合の水先案内のために、異なる用法を一覧にしてあります。お探しの用語に一番近い記事を選んで下さい。このページへリンクしているページを見つけたら、リンクを適切な項目に張り替えて下さい。 |
STAGEA
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 00:56 UTC 版)
エレクトーン ステージア (Electone STAGEA) は、2004年3月以降に展開された現行シリーズの商標である。「STAGEA」の名前の由来は、演奏する場としての「ステージ(stage)」と、勇気を与えてくれる女神「ガイア(gaea)」との造語になっており、いろいろな場で活躍し演奏者に勇気を与える楽器になるように名前をつけられている。メインシリーズは型番が「ELS」で始まることから、先代のELシリーズと同様に「ELSシリーズ」と呼ばれることもある。ELSシリーズは、現行モデルの「ELS-02シリーズ」と、旧モデルの「ELS-01シリーズ」に分けられる。 メインの外部記憶装置に関しては、ELS-01シリーズ発売当初はスマートメディアであり、曲集対応のプロテクトデータはスマートメディアに保存するようになっていた。しかし、2005年3月7日、スマートメディアの主な製造メーカーであった東芝がスマートメディアの生産・供給から撤退することを発表したことなどから、外部記憶装置はスマートメディアからUSBメモリへと移行した。また、2009年より発売された「typeU」シリーズではスマートメディアドライブが廃止され、代わりにUSBメモリの着脱を容易にするための専用アダプターが取り付けられた。 また、HS/ELシリーズの頃から「レジストデータに依存」してしまう演奏スタイルが増えてきた事への解決策として「ベーシックレジスト(初期化後にメモリーボタン1〜16にセットされたレジスト)」「レジストレーションメニュー」(通称レジメ)が充実した。これによって多様な音楽ジャンルに合わせた音色の組み合わせが予め準備され、レジストデータを準備していなくともその場で音色をセットして演奏できる機能が強化された。 なお、近年のヤマハエレクトーンフェスティバルのセミファイナルでは、小学校高学年以上の部において自由曲演奏の他にモチーフ即興演奏が規定されている。このモチーフ即興演奏ではレジストデータをUSBメモリでは準備せず、その場で音色をセットして演奏する規定になっている。 2014年よりSTAGEAの新ラインナップ「ELS-02シリーズ」が発売。音色数の増加、スーパーアーティキュレーションボイスの採用など、新技術も多数導入されている。ELS-01シリーズからもELS-02シリーズとほぼ同等の性能にできる「バイタライズユニット」も5月から併売された。 ELS-01シリーズでは六角レンチを用いてユーザ自身での分解と組み立てが可能な「ユニット構造」を採用し、乗用車での可搬が可能であったが、上述の通り分解しても各パーツがまだまだ重い事もあり、ELS-02シリーズでは分解・組立は不可となった。 また、インターネットダイレクトコネクションによりYAMAHAのサイトからレジストレーションを直接ダウンロード購入する機能があったが、2016年7月のバージョンアップ(ELS-02シリーズ)に伴い「ダイレクトコネクション」機能は廃止され、それに代わって「オーディオ」機能が搭載された。 2016年5月には「ELB-02」、2016年12月には「ELC-02」が発売された。ELB-02は対象を大人初心者にまで広げたベーシックモデルとして、ELC-02はELS-02と同等の演奏機能を備えながら、持ち運びができるカジュアルモデルとして発売された。同時にSTAGEA D-DECK PACKAGEをELC-02とほぼ同等の性能にできる「ELCU-M02」も発売された。
※この「STAGEA」の解説は、「エレクトーン」の解説の一部です。
「STAGEA」を含む「エレクトーン」の記事については、「エレクトーン」の概要を参照ください。
- stage aのページへのリンク
