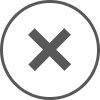にほんご‐がく【日本語学】
日本語学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/18 13:13 UTC 版)
日本語学(にほんごがく)とは、日本語を研究の対象とする学問である。日本語学を専攻する学者を日本語学者という。
注釈
- ^ この他に「日本語研究史[7]」(または「国語研究史[8]」)や「日本語学説史[9]」といった呼称もある。ここでは一般的な名称として使われる「日本語学史」を用いた。
- ^ 限定を加えずに広く日本語研究の歴史として捉えると、その対象範囲は日本思想にも及ぶことになり、研究史と思想史との境界が希薄なものとなりかねないため、「言語学的観点から一定の評価や判断が可能なもの」を対象として扱うなどの限定を設ける必要性が生じる[10]。こうした点については、飯田晴巳 (1998)や山東功 (2015)が詳しい。
- ^ 分野によっては訓点資料や抄物のように、若い世代への継承が急務な場合があるほか、中世の辞書や近世語資料のように研究対象が膨大であるために、その全体像の把握のためにさらなる研究者の養成が必要な場合もある[13]。
- ^ 一般に「ヲコト点」と呼ばれるが、これは江戸時代以後の呼称であり、院政時代には「テニハ点」といわれ、それ以前は単に「点」とだけ呼ばれていた[17]。
- ^ いつ頃から手本として使用され始めたのかについては不明な点が多いが、斎宮跡に11世紀末から12世紀初頭と考えられる「いろは」の書かれた土器が出土しているほか、12世紀半ば以降の同様の土器も全国各地で出土していることから、「いろは」が出来て間もない頃とされる[19]。なお、2020年時点で全文が確認できる土器としては、堀河院跡に出土した12世紀末から13世紀初頭の土器が最古である[20]。
- ^ 『日本書紀』巻第29(天武天皇11年3月13日条)に「肇めて新字一部四十四巻を造らしむ」とある[21]。この記事が仮に史実でないとしても、天武朝において辞書編纂が行われた可能性はある[22]。
- ^ 鎌倉初期に増補して十巻本としたものは『伊呂波字類抄』と呼ばれる[31]。
- ^ 『天仁遠波十三ヶ条口伝』『姉小路家手似葉伝』『出葉抄』『秘伝天爾波抄』など様々な名称で伝わっている[45]。
- ^ アクセントの高低による「を」と「お」の使い分けは、すでに『類聚名義抄』や『色葉字類抄』などにも見られる[50]。
- ^ ほとんどが思い付き程度の恣意的なものとされるが[63]、近世初期の言語生活などを知り得る資料とされる[64]。
- ^ 村田春海・清水浜臣『古言梯再考増補標註』にある「古言梯のいて来しをり竟宴の哥」に「古言のかけはしとふふみあつめをへたる日よめる」という魚彦の詞書があることから、実際の書名は「ふることのかけはし」の可能性がある[77]。
- ^ 藤重匹龍『掌中古言梯』、村田春海・清水浜臣『古言梯再考増補標註』、山田常典『増補古言梯標註』などがある[78]。これらのほかにも、市岡猛彦『雅言仮字格』、鶴峯戊申『増補正誤仮名遣』、村田春海『仮字拾要』などがある[79][80]。
- ^ 例えば主格などに「は・も」などが付いた場合に文末が終止形になるのは当然のようであるが、主格を示す「が・の」が来た場合は、「君が思ほせりける[86]」「にほひの袖にとまれる[87]」のように文末が連体形で結ばれるのであるから、あえて「は・も・徒」の下が終止形で結ばれることを示した[85]。
- ^ 成章は兄の皆川淇園と共に漢学を修め、国学に転じた後も兄の漢学に対しては深い理解を示したという[90]。
- ^ 御杖の言説は、近代において土田杏村が高く評価して以降、改めて注目されるようになっていった[93][94]。
- ^ 前編は1777年、中編は1862年に刊行されたが、後編は明治になって刊行された[104]。
- ^ 写本で伝えられて版本の形にならなかった上に、容易に目にすることが可能になるのは、明治に『増補俚言集覧』(1899年~1900年)として刊行されてからである[105]。
- ^ 版本の形になったのは「い」~「な」の語彙で、全体像を確認することが可能になるのは、1887年に『増補雅言集覧』(1903年版もある)が刊行されてからである[106]。
- ^ 以上が「近世期の三大辞書」といわれる[107]。これらに『鸚鵡抄』を加えて「四大辞書」といわれることもあるが、『鸚鵡抄』は未刊行であったことを理由に、流布や影響といった側面から除外される[108]。
- ^ 今日でいう「未然形」のことで、義門と同時期に富樫広蔭は「未然段」と呼んでいた[117]。
- ^ 今日でいう「終止形」のことで、当時は他にも富樫広蔭の「断止段」や鈴木重胤の「絶定言」などがあった[118]。なお、「終止」を活用形の名称として初めて用いたのは、黒川真頼の可能性が高いとされる[118][119]。
- ^ 今日でいう「命令形」のことで、『活語雑話』に宣長の『漢字三音考』を参考にした旨が記されていることから、その記述を加味した結果と推察される[120]。
- ^ これは中世の「体」「用」「てにをは」以来の伝統を継承するものである[122]。
- ^ 『古事記』や『日本書紀』などのほか、『和名類聚抄』や『倭訓栞』などの辞書類、さらには『先代旧事本紀』が利用されている[129]。
- ^ 今日におけるヘボン式は、羅馬字会が提案した綴りを下敷きに修正を施したもので[133]、『和英語林集成』第3版(1886年)において確定させた[134]。
- ^ 例えば「国語学史の最初の刊行書」として注目される保科孝一 (1899)は、「科学的研究が微々として振るわなかったこと」「研究材料の範囲が極端に狭かったこと」「学者の自尊心が強いゆえに比較研究をしなかったこと」を理由にしている[139]。こうした考え方に対しては、時枝誠記のほかに[140]、山田孝雄などが批判している[141]。
- ^ 大槻は黒川真頼の『詞の栞』の講義にたびたび列席していた[142]。真頼の文法学説には、義門が春庭の説を展開して著した『詞の道しるべ』(1810年)の受容が指摘されている[143]。
- ^ 中途で打ち切られたのは、編集母胎である大学が廃止されたことに加え、文部省内で「見出し語の配列が徹底していない上に品詞表示がない」「位相の指示や語種の区別が不十分」「漢語が偏っている上に洋語が少なすぎる」「語源記述がほとんどない」「俗語に対する意識が低い」「使用の手引きが見られない」といった体裁が問題視されたことが、原因として挙げられる[147]。
- ^ 『言海』が刊行されるまでには、近藤真琴の『ことばのその』(1885年)、物集高見の『ことばのはやし』(1888年)、高橋五郎の『漢英対照いろは辞典』(1888年)と『和漢雅俗いろは辞典』(1888年〜1889年)が刊行されているが、いずれも雅語に徹している[148][149]。また、『言海』刊行後、山田美妙が『日本大辞書』(1892年〜1893年)を著したが、アクセントを付した口語体の辞書として歴史的意義がある一方で、全体的に尻窄まりとなってしまっている[150]。こうした点からも『言海』は評価されている。
- ^ 監修者として重野安繹、三島毅、服部宇之吉の名前があるが、実質的な編集は三省堂編修所の齋藤精輔が中心となり、読売新聞社にいた同郷の足助直次郎を招き入れ、深井鑑一郎や福田重政と一緒にあたらせたという[153]。
- ^ 例えば『口語法調査報告書』は、東条操が「方言区画論」を提唱する契機となった[164]。また『口語法別記』は、口語に関する歴史的変遷を記述した成果として、後の口語研究の可能性を開拓した[165]。
- ^ 当初は「歐米ニ於ル言語研究者ノ言語觀念ノ發達ニ就テ、言語研究ノ方法及其目的、歐米言語学ノ國語學ニ及ボシタル影響」など、幾つか構想を練っていたが、橋本進吉から「到底この1年間にできるようなものではない」という指摘を受けて決定したという[167]。なお、この卒論は後に時枝誠記 (1976)として原本が写真版で複製されている。
- ^ 時枝自身は「人間を取り戻すこと」としている[174]。
- ^ 詳細については時枝誠記 (1941)や時枝誠記 (1955)などで説明されているが、早くに時枝誠記 (1933)で随想的に示されており、時枝誠記 (1937a)で成立の基本的意見が断片的に示された後に、時枝誠記 (1937b)および時枝誠記 (1937c)で真正面に打ち出されている[175]。
- ^ ただし、時枝が指摘するソシュールの言語観に対する理解の在り方については、時枝が『一般言語学講義』を文献学的検証もなしに批判していることもあって、数多くの議論を呼んでいる[176]。
- ^ 時枝の文法論については、時枝誠記 (1941)のほか、時枝誠記 (1950)や時枝誠記 (1954)などに詳しいが、いずれも「山田文法」を多く引用して説明していることから、山田孝雄の言語論を根幹としているとされる[177]。
- ^ 例えば時枝誠記 (1949)などにおいて、「言語の実践に関する議論であるならば、それは他の言語現象と共に、それ自体が国語学の対象とならなければならない」「国語における音声や文字や文法が国語学の対象となるのと同じように、国語の主体的意識の問題として考察の対象となる」と述べている[179]。
- ^ 原因としては、標準語の普及に伴って「方言を顧みる必要はなくなった」と考える識者が続出したことや[184]、国語調査委員会による膨大な調査結果の資料が関東大震災によって焼失したことなどが挙げられる[185]。
- ^ 藤原定家の作と伝えられている歌学書『愚秘抄』(平安末期頃に成立か)が最初とされる[189]。この思想は近世期で一層有力になり、例えば本居宣長の『玉勝間』や荻生徂徠の『南留別志』などにおいて、そのような旨の言及が見られる[190]。
- ^ 柳田自身も1905年頃から関心を持っていた地名の研究を通じて体験していた[191]。
- ^ 『言海』の増補改訂版。当初は大槻自身が改訂作業を進めていたが、事半ばにして1928年に没した後に実兄の大槻如電らが引き継ぎ、関根正直や新村出らの指導を得て完成させた[198]。
- ^ 説明を読んだ人が、その語を自然に思い浮かべることができるよう、日常語で具体的に記述することを指す[201][202]。例えば「水」について、「水素と酸素からなる化合物」といったような化学的説明ではなく、「生活するのに欠かせない、透き通った冷たい液体」といった一般的認識を説明するようにした[201][202]。
- ^ 英称は The Mathematical Linguistic Society of Japan(直訳すると「日本数理言語学会」)である。和名と食い違っているのは、「将来必ずや統計学に留まらず数学の諸分野の手法を使うようになるだろうことを見越した」のが、主な理由であるという[206]。
出典
- ^ a b "国語学". 精選版 日本国語大辞典(小学館). コトバンクより2023年12月12日閲覧。
- ^ “大阪大学日本語学研究室”. 2024年1月10日閲覧。
- ^ “大阪大学国語学研究室沿革”. 2024年1月10日閲覧。
- ^ 小林隆 (2002), p. 97.
- ^ 山本真吾 (2013), p. 261.
- ^ 山東功 (2019), p. 284.
- ^ 杉本つとむ (2008)、中尾比早子 (2009)など。
- ^ 中田祝夫 (1961)など。
- ^ 釘貫亨 (2007)、釘貫亨 (2013)など。
- ^ 山東功 (2019), pp. 284–285.
- ^ a b 今野真二 (2014), p. ⅸ(「はじめに」)
- ^ a b 山東功 (2019), p. 285.
- ^ a b 「編集後記」『國語と國文學』第96巻第5号、明治書院、2019年5月、160頁。
- ^ 山本真吾 (2013), p. 284.
- ^ a b 遠藤佳那子 (2019), p. 6(「はじめに」)
- ^ 遠藤嘉基 (1976), pp. 181–182.
- ^ 遠藤嘉基 (1976), p. 192.
- ^ 馬渕和夫 (1977b), p. 415.
- ^ 岡田一祐 (2022), p. 12.
- ^ 岡田一祐 (2022), p. 13.
- ^ 沖森卓也 (2015), pp. 29–30.
- ^ 犬飼隆 (2000), p. 16.
- ^ 沖森卓也 (2023), p. 12(原著:沖森卓也 2008)
- ^ 倉島節尚 (2015), p. 16.
- ^ 小林芳規 (2000), pp. 31–32.
- ^ 月本雅幸 (2016), p. 6.
- ^ 小林芳規 (2000), pp. 34–35.
- ^ 小林芳規 (2000), pp. 35–36.
- ^ 藤本灯 (2016), p. 13.
- ^ 金子彰 (2015), pp. 59–60.
- ^ 沖森卓也 (2000), p. 40.
- ^ 山本真吾 (2015a), pp. 69–70.
- ^ 望月郁子 (1998), p. 12.
- ^ 飯田晴巳 (2015), p. 53.
- ^ 金子彰 (2015), p. 60.
- ^ 山本真吾 (2015a), pp. 74–75.
- ^ 肥爪周二 (1998), p. 4.
- ^ 月本雅幸 (2016), p. 5.
- ^ 林史典 (2016), pp. 9–11.
- ^ 山田孝雄 (1938), pp. 81–85.
- ^ 山田孝雄 (1938), pp. 85–87.
- ^ 山東功 (2019), p. 287.
- ^ 乾善彦 (2016), p. 23.
- ^ 田中康二 (2015b), p. 363(初出:田中康二 2015a)
- ^ 遠藤嘉基 (1976), p. 212.
- ^ 国語学会 (1979), p. 84.
- ^ 今野真二 (2016b), p. 16.
- ^ 今野真二 (2016b), p. 17.
- ^ 築島裕 (1986), pp. 12–17.
- ^ 築島裕 (1986), p. 35.
- ^ 今野真二 (2016b), p. 19.
- ^ 築島裕 (1986), pp. 41–42.
- ^ 尾崎知光 (1983), p. 16(初出:尾崎知光 1976)
- ^ 川平ひとし (1998), pp. 26–28.
- ^ a b 中山綠朗 (2015), p. 80.
- ^ a b 木村一 (2015), p. 90.
- ^ 木村一 (2015), pp. 92–97.
- ^ 小林賢次 (2000), p. 45.
- ^ 山田潔 (2015), p. 40.
- ^ 山本真吾 (2015b), pp. 28–29.
- ^ 丸山徹 (2016), pp. 29–30.
- ^ 山本真吾 (2013), pp. 284–285.
- ^ 国語学会 (1979), p. 147.
- ^ 土居文人 (2015), p. 298.
- ^ 土居文人 (2015), pp. 294–296.
- ^ 国語学会 (1979), p. 149.
- ^ 岡田袈裟男 (2016), p. 39.
- ^ 国語学会 (1979), p. 152.
- ^ a b 長谷川千秋 (2016), p. 34.
- ^ 長谷川千秋 (2016), p. 35.
- ^ 山内育男 (1961), p. 135.
- ^ 内田宗一 (2016), p. 42.
- ^ 内田宗一 (2016), p. 41.
- ^ 竹内美智子 (1961), pp. 179–180.
- ^ 竹内美智子 (1961), p. 180.
- ^ 内田宗一 (2016), p. 43.
- ^ 今野真二 (2016a), p. 198.
- ^ 岩澤和夫 (2001), p. 275.
- ^ 木枝増一 (1933), pp. 181–182.
- ^ 今野真二 (2016a), pp. 215–216.
- ^ 築島裕 (1986), pp. 133–134.
- ^ 矢田勉 (2016), p. 52.
- ^ a b 矢田勉 (2016), p. 53.
- ^ 竹田純太郎 (1998), p. 50.
- ^ a b 田中康二 (2015b), pp. 366–372(初出:田中康二 2015a)
- ^ 『万葉集』巻2・206番歌
- ^ 『古今集』巻第1・春歌上・47番歌
- ^ 田中康二 (2015b), pp. 193–197(初出:田中康二 2014)
- ^ a b 遠藤佳那子 (2016b), p. 57.
- ^ 遠藤佳那子 (2016b), p. 56.
- ^ 遠藤佳那子 (2016b), p. 58.
- ^ 遠藤佳那子 (2016b), pp. 57–58.
- ^ 今野真二 (2020), p. 160.
- ^ 今野真二 (2023), pp. 278–280.
- ^ 安田尚道 (2023), p. 277(初出:安田尚道 2016)
- ^ 肥爪周二 (2016), p. 120.
- ^ 遠藤嘉基 (1976), pp. 209–210.
- ^ 西宮一民 (1977), p. 400.
- ^ 徳川宗賢 (1977), pp. 331–332.
- ^ 宮治弘明 (1991), p. 243.
- ^ 田籠博 (2016), p. 51.
- ^ 日野資純 (1961), p. 442.
- ^ 平井吾門 (2016), p. 44.
- ^ 木村義之 (2015), p. 104.
- ^ 木村義之 (2015), p. 111.
- ^ 木村義之 (2015), p. 108.
- ^ 湯浅茂雄 (2000), p. 64.
- ^ 木村義之 (2015), p. 103.
- ^ 木村義之 (2015), pp. 116–118.
- ^ 平井吾門 (2016), pp. 46–47.
- ^ 中村朱美 (2016), p. 62.
- ^ 内田宗一 (2016), pp. 41–43.
- ^ 平井吾門 (2016), p. 46.
- ^ 坪井美樹 (2016), pp. 69–70.
- ^ 森野宗明 (1961), p. 312.
- ^ 中村朱美 (2016), pp. 62–63.
- ^ 遠藤佳那子 (2022), p. 2.
- ^ a b 遠藤佳那子 (2023), p. 3.
- ^ 遠藤佳那子 (2019), pp. 169–170(初出:遠藤佳那子 2016a)
- ^ 遠藤佳那子 (2019), p. 110(初出:遠藤佳那子 2013)
- ^ 仁田義雄 (2021), p. 134.
- ^ a b c 仁田義雄 (2021), p. 135.
- ^ 坪井美樹 (2016), p. 69.
- ^ 小林芳規 (1961b), pp. 340–341.
- ^ 坪井美樹 (2016), p. 71.
- ^ 坪井美樹 (2016), p. 70.
- ^ a b c 坪井美樹 (2016), pp. 70–71.
- ^ 木村一 (2016), p. 76.
- ^ 山東功 (2013), pp. 97–98.
- ^ 山東功 (2013), p. 98.
- ^ 金子弘 (2016), p. 74.
- ^ 大野晋 (1976), p. 245.
- ^ 木村一 (2016), p. 79.
- ^ 山東功 (2013), p. 175.
- ^ 木村一 (2016), p. 78.
- ^ 猿田知之 (1993), pp. 9–13.
- ^ 山東功 (2002), pp. 4–10.
- ^ a b 湯浅茂雄 (2016), pp. 90–91.
- ^ 猿田知之 (1993), pp. 14–32.
- ^ 猿田知之 (1993), pp. 58–59.
- ^ 猿田知之 (1993), pp. 83–84.
- ^ 遠藤佳那子 (2019), p. 163(初出:遠藤佳那子 2016a)
- ^ 遠藤佳那子 (2019), p. 189(初出:遠藤佳那子 2017)
- ^ 湯浅茂雄 (2016), p. 91.
- ^ 斎藤倫明 (2016), p. 114.
- ^ 犬飼守薫 (2000), p. 75.
- ^ 犬飼守薫 (2000), p. 74.
- ^ 山田忠雄 (1981), pp. 517–525.
- ^ 山田忠雄 (1981), pp. 532–543.
- ^ 山田忠雄 (1981), pp. 622–624.
- ^ 築島裕 (1986), pp. 140–141.
- ^ 沖森卓也 (2023), p. 180(原著:沖森卓也 2017)
- ^ 齋藤精輔 (1991), pp. 93–94.
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 196–197(原著:沖森卓也 2017)
- ^ 清水康行 (2016), p. 108.
- ^ a b 清水康行 (2016), p. 109.
- ^ a b 加藤彰彦 (1961), p. 569.
- ^ 茅島篤 (2016), pp. 86–87.
- ^ 藤田保幸 (2016), p. 99.
- ^ 野村剛史 (2016), pp. 102–103.
- ^ 田島優 (2016), pp. 105–106.
- ^ 山東功 (2016), pp. 93–94.
- ^ 清水康行 (2016), p. 111.
- ^ 宮治弘明 (1991), p. 244.
- ^ 湯浅茂雄 (2016), pp. 89–90.
- ^ 加藤彰彦 (1961), p. 570.
- ^ 時枝誠記 (1957), pp. 28–31.
- ^ 山東功 (2001), pp. 9–11.
- ^ 山東功 (2002), pp. 27–34.
- ^ 山東功 (2007), pp. 84–85.
- ^ 山東功 (2011), pp. 76–77.
- ^ a b c 山東功 (2020), p. 35.
- ^ 山東功 (2020), pp. 35–36.
- ^ 時枝誠記「近代科学としての国語学」『毎日新聞』、1964年12月4日、夕刊、3面。
- ^ 鈴木一彦 (1968), p. 138.
- ^ a b 山東功 (2020), p. 36.
- ^ 神島達郎 (2021), pp. 81–108.
- ^ 加藤彰彦 (1961), p. 561.
- ^ 加藤彰彦 (1961), p. 562.
- ^ 辻村敏樹 (1961), p. 425.
- ^ 大石初太郎 (1977), pp. 218–219.
- ^ 加藤彰彦 (1961), p. 585.
- ^ a b c 小林隆 (2016), p. 117.
- ^ 徳川宗賢 (1977), p. 333.
- ^ a b c 宮治弘明 (1991), p. 245.
- ^ 日野資純 (1961), p. 444.
- ^ 徳川宗賢 (1977), p. 343.
- ^ a b c 宮治弘明 (1991), p. 246.
- ^ 日野資純 (1961), pp. 440–441.
- ^ 徳川宗賢 (1977), pp. 330–331.
- ^ 徳川宗賢 (1977), p. 363.
- ^ 徳川宗賢 (1977), p. 364.
- ^ 徳川宗賢 (1977), pp. 351–353.
- ^ 徳川宗賢 (1977), pp. 354–356.
- ^ 上野和昭 (2020), p. 81.
- ^ 久野眞 (2020), p. 57.
- ^ a b 飯間浩明 (2020), p. 83.
- ^ 湯浅茂雄 (2016), p. 89.
- ^ 沖森卓也 (2023), pp. 232–233(原著:沖森卓也 2017)
- ^ 飯間浩明 (2020), p. 84.
- ^ a b 山崎誠 (2013), pp. 88–89.
- ^ a b c 飯間浩明 (2020), p. 85.
- ^ 山田潔 (2020), p. 89.
- ^ 「「国語学会」の名称、来年から「日本語学会」に」『読売新聞』、2003年2月25日、朝刊、38面。
- ^ 「「日本語学会」に改称へ 「国語」か「日本語」か」『朝日新聞』、2003年2月25日、朝刊、33面。
- ^ a b 計量国語学会 (2009)「計量国語学会設立のころ」
- ^ 工藤真由美 (2013), p. 73.
- ^ 金岡孝 (1977), pp. 378–395.
- ^ 国立国語研究所 (2023), p. 36.
日本語学
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/24 17:16 UTC 版)
日本語学においては、奥田靖雄らの言語学研究会が1960年代に語結合の概念を導入し、これを「連語」と翻訳した。ロシア言語学と同じく主語と述語の結びつきを語結合と見なしていない。
※この「日本語学」の解説は、「語結合」の解説の一部です。
「日本語学」を含む「語結合」の記事については、「語結合」の概要を参照ください。
「日本語学」の例文・使い方・用例・文例
固有名詞の分類
- 日本語学のページへのリンク