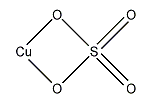硫酸銅(II)
硫酸銅(II)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/30 08:41 UTC 版)
| 硫酸銅(II) | |
|---|---|

CuSO 4 · 5H2Oの結晶 |
|
 |
|
 |
|
|
Copper(II) sulfate |
|
|
別称
|
|
| 識別情報 | |
|
|
|
3D model (JSmol)
|
|
| ChEBI | |
| ChEMBL | |
| ChemSpider | |
| ECHA InfoCard | 100.028.952 |
| EC番号 |
|
| Gmelin参照 | 8294 |
| KEGG | |
|
PubChem CID
|
|
| RTECS number |
|
| UNII |
|
|
CompTox Dashboard (EPA)
|
|
|
|
|
|
| 特性 | |
| 化学式 | CuSO 4 (無水物) CuSO 4 · 5H2O (五水和物) |
| モル質量 | 159.60 g/mol (無水物)[2] 249.685 g/mol (五水和物)[2] |
| 外観 | 灰白色(無水物) 青色(五水和物) |
| 密度 | 3.60 g/cm3 (無水物)[2] 2.286 g/cm3 (五水和物)[2] |
| 融点 | 110℃ で分解 |
| 沸点 | 650 °Cで酸化銅に分解 |
| 水への溶解度 | 五水和物 316 g/L (0 °C) 2033 g/L (100 °C) 無水物 168 g/L (10 °C) 201 g/L (20 °C) 404 g/L (60 °C) 770 g/L (100 °C)[3] |
| 溶解度 | 無水物 エタノールに溶けない[2] 五水和物 メタノールに溶ける[2] 10.4 g/L (18 °C) エタノールとアセトンに溶けない |
| 磁化率 | 1330·10−6 cm3/mol |
| 屈折率 (nD) | 1.724–1.739 (無水物)[4] 1.514–1.544 (五水和物)[5] |
| 構造 | |
| 直方晶系 (無水物, カルコシアナイト), 空間群 Pnma, oP24, a = 0.839 nm, b = 0.669 nm, c = 0.483 nm.[6] 三斜晶系 (五水和物), 空間群 P1, aP22, a = 0.5986 nm, b = 0.6141 nm, c = 1.0736 nm, α = 77.333°, β = 82.267°, γ = 72.567°[7] |
|
| 熱化学 | |
| 標準生成熱 ΔfH |
−769.98 kJ/mol |
| 標準モルエントロピー S |
5 J/(K·mol) |
| 危険性 | |
| GHS表示: | |
   |
|
| Danger | |
| H302, H315, H318, H319, H410 | |
| P264, P264+P265, P270, P273, P280, P301+P317, P302+P352, P305+P351+P338, P305+P354+P338, P317, P321, P330, P332+P317, P337+P317, P362+P364, P391, P501 | |
| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド) | |
| 引火点 | 不燃性 |
| 致死量または濃度 (LD, LC) | |
|
半数致死量 LD50
|
300 mg/kg (経口, ラット)[9] 87 mg/kg (経口, マウス) |
| NIOSH(米国の健康曝露限度): | |
|
PEL
|
TWA 1 mg/m3 (as Cu)[8] |
|
REL
|
TWA 1 mg/m3 (as Cu)[8] |
|
IDLH
|
TWA 100 mg/m3 (as Cu)[8] |
| 安全データシート (SDS) | anhydrous pentahydrate |
| 関連する物質 | |
| その他の 陽イオン |
|
| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |
硫酸銅(II)(りゅうさんどう に、英: copper(II) sulfate,sulphate、化学式 CuSO4)は、銅(II)イオンと硫酸イオンのイオン化合物である。
性質
無水物は白色の粉末である。水和物として、有名な青色の三斜晶系結晶(五水和物)の他に、一水和物、三水和物、七水和物があり、水に易溶で水溶液は青色を示す。中学校および高校の理科の実験に用いられることから馴染み深い化合物である。しかし、重金属である銅による毒性があるために取り扱いには注意を要し、毒物及び劇物取締法により医薬用外劇物に指定されている[10]。
五水和物で、特に鉱物として自然産出するものは、胆礬(たんばん)とも呼ばれている。これは銅山の古い坑道の内壁などで、地下水から析出して結晶となっているものを得ることができる。主に霜柱状、若しくは鍾乳石状の形で産出することが多い。銅の錆である緑青にも含まれる。三水和物はボナッティ石 (Bonattite)[11]、七水和物はブース石[12]として産出するが希少である。
無水物の製法
硫酸銅(II)水和物の加熱脱水で得られる、白色粉末状の物質である無水物は、脱水時に加熱しすぎると更に反応が進み、黒色の酸化銅(II)と三酸化硫黄に分解する。無水物をつくる際は火加減に十分注意しなければならない。
- 脱水 :

外部リンク
- 硫酸銅(II)のページへのリンク