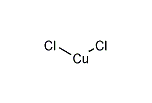ジクロロ銅(II)
塩化銅(II)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/03 15:29 UTC 版)

|
|||
|
|||
|
|||
| 物質名 | |||
|---|---|---|---|
|
塩化銅(II) |
|||
|
別名
塩化第二銅 |
|||
| 識別情報 | |||
|
|||
|
3D model (JSmol)
|
|
||
| バイルシュタイン | 8128168 | ||
| ChEBI | |||
| ChEMBL | |||
| ChemSpider | |||
| DrugBank | |||
| ECHA InfoCard | 100.028.373 | ||
| EC番号 |
|
||
| Gmelin参照 | 9300 | ||
|
PubChem CID
|
|||
| RTECS number |
|
||
| UNII |
|
||
| 国連/北米番号 | 2802 | ||
|
CompTox Dashboard (EPA)
|
|||
|
|||
|
|||
| 性質 | |||
| CuCl 2 |
|||
| モル質量 | 134.45 g/mol (無水物) 170.48 g/mol (二水和物) |
||
| 外観 | 暗褐色の固体(無水物) 水色の固体(二水和物) |
||
| 匂い | 無臭 | ||
| 密度 | 3.386 g/cm3 (無水物) 2.51 g/cm3 (二水和物) |
||
| 融点 | 630 °C (1,166 °F; 903 K) (推定) 100 °C (二水和物の脱水) |
||
| 沸点 | 993 °C (1,819 °F; 1,266 K) (無水物、分解) | ||
| 70.6 g/(100 mL) (0 °C) 75.7 g/(100 mL) (25 °C) 107.9 g/(100 mL) (100 °C) |
|||
| 溶解度 | アセトンに溶ける | ||
| メタノールへの溶解度 | 68 g/(100 mL) (15 °C) | ||
| エタノールへの溶解度 | 53 g/(100 mL) (15 °C) | ||
| 磁化率 | +1080·10−6 cm3/mol | ||
| 構造[1][2] | |||
| 単斜晶系 (β = 121°) (無水物) 直方晶系 (二水和物) |
|||
| C2/m (無水物) Pbmn (二水和物) |
|||
|
a = 6.85 Å (無水物)
7.41 Å (二水和物), b = 3.30 Å (無水物) 8.09 Å (二水和物), c = 6.70 Å (無水物) 3.75 Å (二水和物) |
|||
| 八面体 | |||
| 危険性 | |||
| GHS表示: | |||
    |
|||
| Danger | |||
| H301, H302, H312, H315, H318, H319, H335, H410, H411 | |||
| P261, P264, P270, P271, P273, P280, P301+P310, P301+P312, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P310, P312, P321, P322, P330, P332+P313, P337+P313, P362, P363, P391, P403+P233, P405, P501 | |||
| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド) | |||
| 引火点 | 不燃性 | ||
| NIOSH(米国の健康曝露限度): | |||
|
PEL
|
TWA 1 mg/m3 (as Cu)[3] | ||
|
REL
|
TWA 1 mg/m3 (as Cu)[3] | ||
|
IDLH
|
TWA 100 mg/m3 (as Cu)[3] | ||
| 安全データシート (SDS) | Fisher Scientific | ||
| 関連する物質 | |||
| その他の 陰イオン |
フッ化銅(II) 臭化銅(II) |
||
| その他の 陽イオン |
塩化銅(I) 塩化銀 塩化金(III) |
||
|
特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。
|
|||
塩化銅(II)(えんかどう に、英: copper(II) chloride)は、組成式が CuCl2 と表される銅の塩化物である。無水物と二水和物がある。無水物は褐色がかった黄色であり、二水和物は青緑色の結晶である。潮解性があり、無水物は吸湿性もある。水和物は110℃で無水物になる。993℃まで熱すると、塩化銅(I)と塩素に分解する[4]。水に溶けやすく、メタノール、エタノール、アセトン、酢酸エチルなどに可溶[5]。CAS登録番号は[7447-39-4]。有毒で、毒物及び劇物取締法により、劇物に指定されている。また、電気分解によって、塩素と銅に分解できることから中学校の理科で電気分解の学習にも用いられる。花火の緑色の発色剤としても用いられる。
構造
塩化銅(II)無水物はヨウ化カドミウム構造を歪めた構造をしている。これは、ほとんどの銅(II)化合物にみられるヤーン・テラー効果によるものである。
塩化銅(II)二水和物は非常に歪んだ八面体構造をしており、銅イオンを取り囲む2つの水配位子と4つの塩素配位子は隣の別の銅イオンと非対称的に橋架け構造をとっている[6]。
合成
赤熱した銅線を塩素の中に入れると褐色の煙として発生する。

外部リンク
「塩化銅 (II)」の例文・使い方・用例・文例
- 塩化銅(II)のページへのリンク