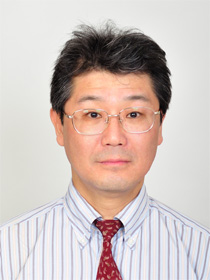伊藤 能(いとう のう)
伊藤能
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/08/05 09:50 UTC 版)
| 伊藤能 七段 | |
|---|---|
| 名前 | 伊藤能 |
| 生年月日 | 1962年1月16日 |
| 没年月日 | 2016年12月25日(54歳没) |
| プロ入り年月日 | 1992年10月1日(30歳) |
| 棋士番号 | 205 |
| 出身地 | 東京都杉並区 |
| 所属 | 日本将棋連盟(関東) |
| 師匠 | 米長邦雄永世棋聖 |
| 段位 | 七段 |
| 棋士DB | 伊藤能 |
| 戦績 | |
| 竜王戦最高クラス | 6組(24期) |
| 順位戦最高クラス | C級2組(13期) |
| 2017年2月5日現在 | |
伊藤 能(いとう のう、1962年1月16日 - 2016年12月25日 )は、将棋棋士。棋士番号205。東京都杉並区出身。米長邦雄永世棋聖門下。
棋歴
1984年に22歳で奨励会三段となったが、その後、なかなか四段昇段(プロ入り)ができなかった。
1987年に三段リーグ制度が復活し四段昇段は狭き門となるが、その第1回の四段昇段の2名は、いずれも米長門の弟弟子の中川大輔、先崎学であった。
その5年後、伊藤は、当時の規定である年齢制限(31歳までに四段昇段)の1期前の第11回三段リーグで2位に入り、四段昇段(プロデビュー)を果たした。その最終日は、リーグ順位22位、成績4番手で迎えたが、2戦2勝し、さらにライバルが敗れての大逆転で、伊藤自身は「神風」「奇跡」と表現した。
プロ入り後は主に早指し棋戦でその才能を発揮し、第44回(1994年度)NHK杯の予選を勝ち抜き本戦に進出。1回戦で森雞二に、2回戦では東和男にそれぞれ勝利した。いずれも、後手番から相手の得意戦法[注 1]からの激しい攻めに動じることなく受けて立つ、伊藤ならではの勝局であった。
その他にも、要所要所で見せ場を作っている。第19回全日本プロ将棋トーナメント1回戦(2000年6月16日)では、後に初代永世竜王となる渡辺明に棋士人生初の黒星を喫させ、第61期順位戦・C級2組3回戦(2002年8月20日)では、第30回将棋大賞・連勝賞を受賞した山崎隆之[注 2]の連勝を16で止めた。
その一方で、持ち時間が長い順位戦は不得手としており、C級2組で13年指したあいだ、指し分け(5勝5敗)を超える成績を収められず、第54期(1995年度)及び第64期(2005年度)で降級点を喫し、2006年にフリークラス宣言をした。
順位戦と同様に持ち時間が長い竜王戦も不得手としており、第6期(1992-1993年度)から第29期(2015-2016年度)まで、最下級クラスの6組から昇級できずにいた。
2016年12月25日、現役のまま死去[1]。54歳没[1]。日本将棋連盟は七段を追贈した(2016年12月25日付)[2]。
棋風
人物
- 30歳8ヶ月での四段昇段は1987年度に現行の三段リーグが開始して以降の最年長記録、奨励会在籍17年は四段昇段者では最長記録である。四段昇段当時の奨励会幹事は、伊藤と奨励会同期入会の神谷広志及び大野八一雄であった。
- 自身が奨励会で苦労した経験もあってか、奨励会員には非常に優しく接する。自身の対局で記録係を担当した奨励会員が不慣れな様子を示した際も、当人が動揺しないよう配慮をする姿勢が窺える[4]。近年は、タイトル戦の記録係を務めた渡辺正和五段など若手棋士に対しても、隣で様々な気配りを見せていた。
- 中学生のときに、通っていた将棋道場の席主から「プロになる気があるなら師匠を紹介するけど、棋士は誰が好きか」と問われ、「うーん、米長かなあ」と答えた。まさか、それがそのまま実現するとは思わず、伊藤の父は驚きの表情を飛び越えてオロオロしたという[5]。
- 奨励会時代は、米長宅の側のアパートに住み、「半内弟子」生活だった。電話がないため、食事は内弟子の先崎学が伊藤を呼んで、米長宅で摂ったという[6]。
- 観戦記の執筆でも知られ、『将棋ジャーナル』や『近代将棋』に連載していた団鬼六と親交があった。行方尚史がA級昇級したときは、団とともに貸切船の観桜遊覧で行方を祝った。
- また、真部一男や土佐浩司らに、囲碁の藤沢秀行名誉棋聖の自宅にも連れられていき、酒の相手をした。米長に「藤沢秀行と初めて会った印象」を訊かれたときは、「名誉棋聖があまりにもインパクトが強すぎ、言葉が出なかった」と伊藤は答えている。
- 米長の死後、当時奨励会三段だった弟弟子の杉本和陽を弟子として自身が死去するまで引き取っていた。杉本は伊藤の死後は中川大輔門下に、プロ入り後は再び米長門下となっている。
昇段履歴
- 1975年11月1日: 6級 = 奨励会入会
- 1976年6月1日: 5級
- 1978年5月1日: 4級
- 1978年8月1日: 3級
- 1978年10月1日: 2級
- 1980年5月1日: 1級
- 1980年8月1日: 初段
- 1982年5月1日: 二段
- 1984年5月1日: 三段
- 1992年9月1日: 四段 = プロ入り
- 1999年7月27日: 五段(勝数規定 /公式戦100勝)[7]
- 2012年4月1日: 六段(フリークラス昇段規定)[8]
- 2016年12月25日: 七段(追贈)[1]
主な成績
在籍クラス
| 開始 年度 |
順位戦 | 竜王戦 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | 名人 | A級 | B級 | C級 | 期 | 竜王 | 1組 | 2組 | 3組 | 4組 | 5組 | 6組 | 決勝 T |
|||||
| 1組 | 2組 | 1組 | 2組 | |||||||||||||||
| 1992 | 51 | 昇段前 | 6 | 6組 | -- | 2-2 | ||||||||||||
| 1993 | 52 | C252 | 4-6 | 7 | 6組 | -- | 3-2 | |||||||||||
| 1994 | 53 | C236 | 4-6 | 8 | 6組 | -- | 2-2 | |||||||||||
| 1995 | 54 | C233x | 3-7 | 9 | 6組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 1996 | 55 | C241* | 4-6 | 10 | 6組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 1997 | 56 | C235* | 4-6 | 11 | 6組 | -- | 3-2 | |||||||||||
| 1998 | 57 | C231* | 5-5 | 12 | 6組 | -- | 0-2 | |||||||||||
| 1999 | 58 | C224* | 5-5 | 13 | 6組 | -- | 3-2 | |||||||||||
| 2000 | 59 | C225* | 4-6 | 14 | 6組 | -- | 4-2 | |||||||||||
| 2001 | 60 | C228* | 5-5 | 15 | 6組 | -- | 2-2 | |||||||||||
| 2002 | 61 | C221* | 5-5 | 16 | 6組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 2003 | 62 | C219* | 4-6 | 17 | 6組 | -- | 2-2 | |||||||||||
| 2004 | 63 | C226* | 4-6 | 18 | 6組 | -- | 1-2 | |||||||||||
| 2005 | 64 | C233*x | 3-7 | 19 | 6組 | -- | 3-2 | |||||||||||
| 2006 | 65 | F宣 | 20 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
| 2007 | 66 | F宣 | 21 | 6組 | -- | 3-2 | ||||||||||||
| 2008 | 67 | F宣 | 22 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
| 2009 | 68 | F宣 | 23 | 6組 | -- | 4-2 | ||||||||||||
| 2010 | 69 | F宣 | 24 | 6組 | -- | 2-2 | ||||||||||||
| 2011 | 70 | F宣 | 25 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
| 2012 | 71 | F宣 | 26 | 6組 | -- | 0-2 | ||||||||||||
| 2013 | 72 | F宣 | 27 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
| 2014 | 73 | F宣 | 28 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
| 2015 | 74 | F宣 | 29 | 6組 | -- | 1-2 | ||||||||||||
| 2016 | 75 | F宣 | 30 | 6組 | -- | 0-1 | ||||||||||||
| 2016年12月25日死去 | ||||||||||||||||||
| 順位戦、竜王戦の 枠表記 は挑戦者。右欄の数字は勝-敗(番勝負/PO含まず)。 順位戦の右数字はクラス内順位 ( x当期降級点 / *累積降級点 / +降級点消去 ) 順位戦の「F編」はフリークラス編入 /「F宣」は宣言によるフリークラス転出。 竜王戦の 太字 はランキング戦優勝、竜王戦の 組(添字) は棋士以外の枠での出場。 |
||||||||||||||||||
年度別成績
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 10 | 4 | 6 | 0.4000 | [9] |
| 1993 | 39 | 25 | 14 | 0.6410 | [10] |
| 1994 | 37 | 17 | 20 | 0.4595 | [11] |
| 1995 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | [12] |
| 1996 | 25 | 10 | 15 | 0.4000 | [13] |
| 1997 | 32 | 15 | 17 | 0.4688 | [14] |
| 1998 | 30 | 15 | 15 | 0.5000 | [15] |
| 1999 | 26 | 10 | 16 | 0.3846 | [16] |
| 2000 | 31 | 15 | 16 | 0.4839 | [17] |
| 1992-2000 (小計) |
256 | 120 | 136 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
| 2001 | 28 | 12 | 16 | 0.4286 | [18] |
| 2002 | 27 | 12 | 15 | 0.4444 | [19] |
| 2003 | 26 | 9 | 17 | 0.3462 | [20] |
| 2004 | 22 | 6 | 16 | 0.2727 | [21] |
| 2005 | 22 | 5 | 17 | 0.2273 | [22] |
| 2006 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | [23] |
| 2007 | 18 | 10 | 8 | 0.5556 | [24] |
| 2008 | 15 | 4 | 11 | 0.2667 | [25] |
| 2009 | 14 | 4 | 10 | 0.2857 | [26] |
| 2010 | 18 | 8 | 18 | 0.4444 | [27] |
| 2001-2010 (小計) |
205 | 74 | 131 | ||
| 年度 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | (出典) |
| 2011 | 16 | 6 | 10 | 0.3750 | [28] |
| 2012 | 12 | 2 | 10 | 0.1667 | [29] |
| 2013 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | [30] |
| 2014 | 15 | 5 | 10 | 0.3333 | [31] |
| 2015 | 11 | 0 | 11 | 0.0000 | [32] |
| 2016 | 10 | 2 | 8 | 0.2000 | [33] |
| 2011-2016 (小計) |
79 | 20 | 59 | ||
| 通算 | 548 | 214 | 326 | 0.3963 | |
| 2016年12月25日死去 | |||||
主な著書
- 「棋士米長邦雄名言集 人生に勝つために」 (2014年、日本将棋連盟)
脚注
注釈
出典
- ^ a b c “訃報 伊藤能六段”. 日本将棋連盟. 2016年12月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年7月3日閲覧。
- ^ “棋士データベース 七段 伊藤能”. 日本将棋連盟公式サイト. 2017年7月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年7月3日閲覧。
- ^ 「将棋観戦が身近になる プロ棋士名鑑 2015」(宝島社)ほか
- ^ 第4回朝日杯将棋オープン戦一次予選・伊藤能五段 対 清水市代女流王将(2010年7月26日)
- ^ 『NHK将棋講座』2013年12月号
- ^ 将棋世界2017年3月号 「追悼・伊藤能六段」
- ^ 『近代将棋(1999年10月号)』近代将棋社/国立国会図書館デジタルコレクション、171頁。
- ^ 『2012年4月1日付昇級・昇段者|将棋ニュース|日本将棋連盟』2012年4月4日。
- ^ [1][名無しリンク]
- ^ [2][名無しリンク]
- ^ [3][名無しリンク]
- ^ [4][名無しリンク]
- ^ [5][名無しリンク]
- ^ [6][名無しリンク]
- ^ [7][名無しリンク]
- ^ [8][名無しリンク]
- ^ [9][名無しリンク]
- ^ [10][名無しリンク]
- ^ [11][名無しリンク]
- ^ [12][名無しリンク]
- ^ [13][名無しリンク]
- ^ [14][名無しリンク]
- ^ [15][名無しリンク]
- ^ [16][名無しリンク]
- ^ [17][名無しリンク]
- ^ [18][名無しリンク]
- ^ [19][名無しリンク]
- ^ [20][名無しリンク]
- ^ [21][名無しリンク]
- ^ [22][名無しリンク]
- ^ [23][名無しリンク]
- ^ [24][名無しリンク]
- ^ [25][名無しリンク]
関連項目
外部リンク
固有名詞の分類
- 伊藤能のページへのリンク