あすか
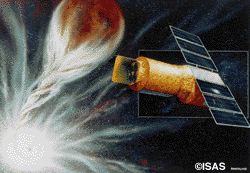
名称:第15号科学衛星「あすか」/Astronomy Satellite-D(ASTRO-D)
小分類:科学衛星
開発機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
運用機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げ年月日:1993年2月20日
運用停止年月日:2001年3月2日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:M-3SII
打ち上げ場所:鹿児島宇宙空間観測所(KSC)
国際標識番号:1993011A
あすかは、近くの星から遠方の銀河に至るすべての種類の天体を、X線で観察することを目的に開発された、日本で4番目のX線天文衛星です。
軽量ですが、最新のX線観測技術を取り入れた高性能のX線天文台です。4台のX線反射望遠鏡をのせ、各焦点にX線撮像・分光装置(焦点面検出器)が置かれており、焦点面検出器には蛍光比例計数管2台と、X線CCDカメラ2台を用いています。これらによって、1980年代後半に活躍したぎんがの検出限界より数百倍の微弱なX線天体をとらえることができます。
また、X線天文学計画ではぎんが、あすかで共同研究を行ないました。あすかではX線反射望遠鏡とX線CCDカメラなど、さまざまな部分で日米共同開発・協力が行なわれ、さらにX線天文衛星計画においても種々の日米協力が行なわれていましたが、2001年3月2日に大気圏に突入し、約8年にわたる運用を終了しました。
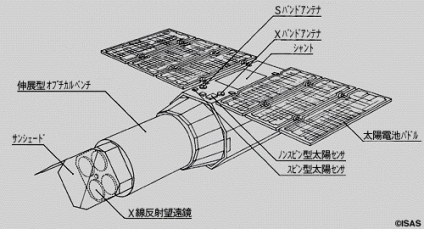
あすか外観図
円筒形の本体に、翼のような太陽電池パドルが広がった形をしています。重量は417kgです。
あすかはX線により天文観測を行ないますが、とらえることができる波長範囲は1~20オングストロームで、これはぎんがに比べ、蛍光比例計数管で2倍以上で、X線CCDカメラは約10倍の波長分解能を持っています。
2.どんな目的に使用されるの?
あすかは宇宙空間の星・銀河のX線観測、銀河団などの宇宙最深部のX線による観察を目的としています。超新星の残骸や銀河団の超高温プラズマをはじめ、中性子星、ブラックホール等のX線星、クエーサー等活動銀河の分光学的研究、感度を活かした微弱天体の探索、宇宙最深部の観測に使用されます。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
1993年3月17日、蛍光比例計数管によりX線天体の初めての撮像観測に成功しました。1993年4月5日には発見されたばかりの銀河M81の超新星SN1993JからのX線をとらえることに成功しました。開発だけではなく、観測運用にも外国人研究者が加わり、国際的なX線天文台として活躍していましたが、2001年3月2日に大気圏突入し、約8年にわたる運用を終えました。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
ひのとり、てんま、ぎんが、ASTRO-Eがあります。
- 第15号科学衛星「あすか」のページへのリンク
