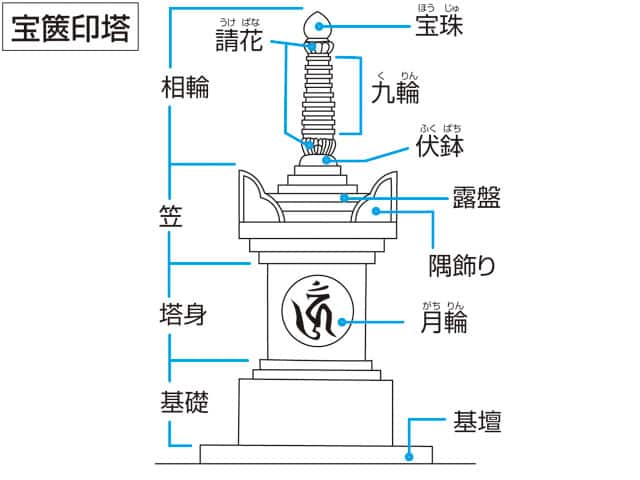ほう‐じゅ【宝珠】
ほうじゅ 【宝珠】
宝珠(ほうじゅ)
宝珠
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 07:28 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動
宝珠(ほうじゅ、ほうしゅ,ラテン語: globus cruciger、英語: orb、ドイツ語: Reichsapfel)とは、十字架が上に付いた球体のことである。
名称
他の和訳については、十字聖球・帝国宝玉などがある。
使い場
中世を通して、そして今日でも、キリスト教の権威として、硬貨・図像学・レガリア・王権の象徴などで使われる。また、世界を象徴する球体に対し、キリストの印である十字架の支配権を象徴する。地上の統治者や天使のような天界的な存在は、文字通り手で持つことで自らの支配権を表す。キリスト自身が宝珠を持つ場合は、西洋美術の図像学では「世界の救世主」(en:Salvator Mundi)として知られている。王笏と組み合わせて描写されることが多い。
歴史

知られている最古の宝珠は、最も確かなものは423年の東ローマ帝国のテオドシウス2世の硬貨の裏側であるが、395年と408年の間のアルカディウスの硬貨の裏側の可能性もある。
世界を人の手で持つ、あるいは世界を人の足の下に置く、あるいは世界に座ることの視覚的象徴性は、古代から非キリスト教徒の間でも使われたイメージだった。ローマ市民は、世界または宇宙、そして皇帝のそれに対する支配と保護の表現としての球体に親しんでいた。例えば、4世紀の皇帝コンスタンティヌス1世の時代のコインは、手に球体を持っている。また、2世紀の皇帝ハドリアヌスの時代のコインは、ローマの神サルースが球体に足を乗せている。
5世紀のキリスト教の発展に伴い、世界に対するキリスト教の神の支配権の象徴として、球体の上に十字架が付けられた。キリスト教徒にとっては、皇帝が神に代わって世界を手で持つことが象徴的であった。中世の図像では、物の大きさが、周囲の他の物と比べたその物の重要性を示した。そのため、世界は小さく、統治者または天使は大きくされた。球体は全世界の象徴だったが、その使用(王権を示すレガリアや紋章)は、世界の小部分の統治者たちの間に増殖した。
宝珠は、強力な統治者と天界の存在によって使われた。宝珠は、大天使と同様に、皇帝と王の肖像を飾った。王冠の宝珠は、デンマーク、スウェーデン、ベルギー、オランダ、イタリア、スペイン、ポルトガル、ハンガリー、ルーマニア、ユーゴスラビア、ドイツ帝国など、ヨーロッパ中で、実際の王冠や紋章の王冠の頂部装飾として使われた。宝珠はまだ、今も残るヨーロッパの君主国の国章で、見られる。現代のイングランドでも、君主の宝珠(en:Sovereign's Orb)は、王冠の庇護と支配の下にある国家と英国国教会の両方を象徴する。
-
カール4世 (神聖ローマ皇帝)の1356年の金印勅書
-
ボヘミア王ヴァーツラフ3世
-
ジギスムント (神聖ローマ皇帝)(アルブレヒト・デューラー画)
-
宝珠を持つフリードリヒ5世 (プファルツ選帝侯)
-
ロシア皇帝の王冠・王笏・宝珠
参考文献
- Leslie Brubaker, Dictionary of the Middle Ages, vol 5, pg. 564, ISBN 0684181614
関連項目
宝珠(ほうじゅ)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/04 09:22 UTC 版)
「麒麟町ぼうえいぐみ」の記事における「宝珠(ほうじゅ)」の解説
ぼうえいぐみが変身する為に使用するツール。青龍、白虎、朱雀、玄武の4つがあり、資格者に渡される前に調整が行われる。強化服のダメージが一定量を超えると壊れる。修復は可能。ともみが密かにバージョンアップ版(玄武を除く)を作っていた。
※この「宝珠(ほうじゅ)」の解説は、「麒麟町ぼうえいぐみ」の解説の一部です。
「宝珠(ほうじゅ)」を含む「麒麟町ぼうえいぐみ」の記事については、「麒麟町ぼうえいぐみ」の概要を参照ください。
「宝珠」の例文・使い方・用例・文例
宝珠と同じ種類の言葉
- >> 「宝珠」を含む用語の索引
- 宝珠のページへのリンク