おおぞら
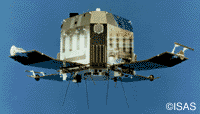
名称:第9号科学衛星「おおぞら」/Exospheric Satellite-C(EXOS-C)
小分類:科学衛星
開発機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
運用機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げ年月日:1984年2月14日
運用停止年月日:1989年7月19日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:M-3S
打ち上げ場所:鹿児島宇宙空間観測所(KSC)
おおぞらは、地球周辺の科学観測を目的に開発されたもので、たいよう、きょっこう、じきけんにつづく我が国第4番目の地球周辺観測衛星です。中層大気の構造と組成の解明、太陽風(太陽から吹き出す高速プラズマ流)と地球大気の影響でいろいろな物理現象を起こす磁気圏(地球の周囲半径約6万から7万kmの範囲)の観測、なかでもオーロラの観測を主目的としています。
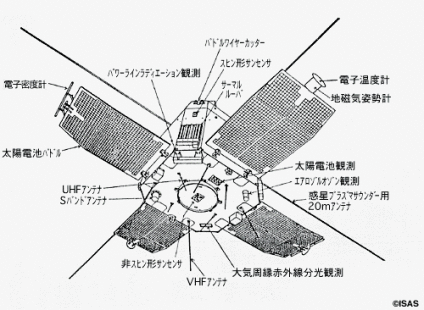
おおぞら外観図
8角柱の箱の四方に羽根のような太陽電池パドルがついたような形をしています。大きさは、最大対面寸法109cm、高さ88cmで、重量は207kgです。
「おおぞら」には、11種類の観測器がのせられていますが、そのなかには地上15kmから100kmほどの高さの中層大気の組成を観測する大気周縁赤外線分光観測装置があります。これは、水蒸気、炭酸ガス、メタン、オゾンの密度分布を観測するために新たに開発された赤外線吸収スペクトル測定装置で、非常に短時間で赤外線吸収スペクトルを測定することができます。
また、地球の電磁気環境を観測する装置としては、惑星プラズマサウンダーという装置があります。これは衛星から20mの長さのアンテナを4本伸ばし、このアンテナから高周波の電波を電離層中に放射して、電離層中に生じるさまざまなプラズマ波動現象を観測するというものです。
2.どんな目的に使用されるの?
「おおぞら」にのせられた11種類の観測器のうち、5つの観測器は大気環境の研究、他の6つの観測器は地球の電磁気環境の研究のために使用されています。
大気の観測では、地上15kmから100kmほどの高さの中層大気中の水蒸気、炭酸ガス、メタン、オゾンの密度分布を観測します。
電磁気環境の観測では、太陽風(太陽から吹き出す高速プラズマ流)と地球大気の影響でいろいろな物理現象を起こす磁気圏(地球の周囲半径約6万から7万kmの範囲)の観測、なかでもオーロラの観測を主目的としています。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
おおぞらの観測内容は、1982年から1985年の間に世界的に実施された、中層大気国際観測計画の中心課題であり、日本のMAP計画の中の重要プロジェクトでした。また、おおぞらは、極域電離層に降下しているオーロラの粒子と、それによるプラズマの波動を観測しましたが、この観測でプラズマの波動は超低周波から高周波にわたって、はげしい電波放射が発生することがわかりました。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
同じオーロラ観測衛星として、きょっこう、じきけん、あけぼのがあります。
- 第9号科学衛星「おおぞら」のページへのリンク
