ぎんが

名称:第11号科学衛星「ぎんが」/Astronomy Satellite-C(ASTRO-C)
小分類:科学衛星
開発機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
運用機関・会社:宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げ年月日:1987年2月5日
運用停止年月日:1991年11月1日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙科学研究所(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:M-3SII
打ち上げ場所:鹿児島宇宙空間観測所(KSC)
国際標識番号:1987012A
ぎんがは、はくちょう、てんまに続く日本で3番目のX線天文衛星です。
X線は宇宙の中の高温のガスが放射したものです。こうした高温のガスは超新星のまわりや、白色矮星、中性子星のまわりなどで発生します。また、X線には周期的なもの、疑似同期的なもの、あるいは雑音のようなものなど、さまざまなものがあります。これらを観測することによって、X線天体の構造に関する重要な情報を得ることができます。こうした観測を行なうのがX線天文で、大気圏外で行なわれます。
ぎんがは、X線天体から放射されるX線の強さの変化を高精度で測定することを主目的に開発されたものです。大面積比例計数管(LAC)と、全天X線監視装置(ASM)、ガンマ線バースト検出器(GBD)の3つの観測器がのせられています。大面積比例計数管は日英、ガンマ線バースト検出器は日米の国際協力によって開発されたものです。星空を撮影するテレビカメラ・星像センサー(STT)などが搭載されています。
また、X線天文学計画ではぎんが、あすかで共同研究を行なうとともに、さらにX線天文衛星計画において種々の日米協力が行なわれています。
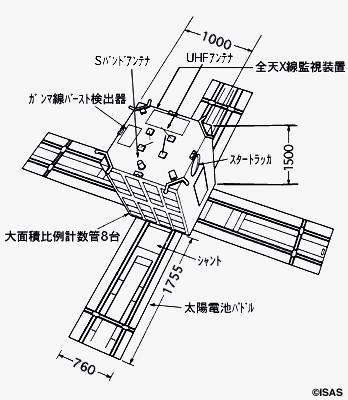
「ぎんが」外観図
1m×1m×1.5mの直方体に、幅0.76m、長さ1.7mの太陽電池パドルが四方に取り付けられています。重量は420kgです。大面積比例計数管(LAC)は、衛星の一側面の全面(有効面積4500立方cm)で、この種の観測器としては当時、世界最大のものです。これは、日本と英国のレスター大学によって、共同開発されたものです(ガンマ線カウンターは、日本と米国のロスアラモス研究所の共同開発)。
2.どんな目的に使用されるの?
「ぎんが」は、銀河系内の中性子星やブラックホールのほかに、もっと遠くの活動銀河(クェーサーなど)の観測を目的としています。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
打ち上げられた1987年の2月23日に、4世紀ぶりに大マゼラン星雲に超新星が出現し、この超新星が出す宇宙X線を8月に観測に成功しました。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
ひのとり、てんま、あすか、ASTRO-Eがあります。
- 第11号科学衛星「ぎんが」のページへのリンク
