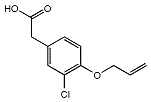アルクロフェナク
| 分子式: | C11H11ClO3 |
| その他の名称: | メルバン、アルクロフェナック、Mervan、W 7320、Alclofenac、4-(Allyloxy)-3-chlorobenzeneacetic acid、アロピジン、エピナール、アルグン、メジフェナック、Zumaril、ネオステン、プリナールギン、ネオストン、Alclophenac、ロイフェナック、ズマリル、Neosten、Prinalgin、Neoston、Reufenac、Allopydin、Medifenac、Epinal、Argun、(4-Allyloxy-3-chlorophenyl)acetic acid、アルクロフェナク、3-Chloro-4-(allyloxy)benzeneacetic acid |
| 体系名: | 3-クロロ-4-(2-プロペニルオキシ)ベンゼン酢酸、4-(アリルオキシ)-3-クロロベンゼン酢酸、(4-アリルオキシ-3-クロロフェニル)酢酸、3-クロロ-4-(アリルオキシ)ベンゼン酢酸 |
アルグン
アルグン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/14 16:10 UTC 版)
| アルグン ارغون خان |
|
|---|---|
| イルハン朝第4代イル・カン | |

|
|
| 在位 | 1284年8月11日 - 1291年3月10日 |
| 戴冠式 | 1284年8月11日 |
|
|
|
| 出生 | 1258年? |
| 死去 | 1291年3月10日 |
| 埋葬 | スィジャース山(ソルターニーイェ) |
| 子女 | ガザン、オルジェイトゥ他 |
| 王朝 | イルハン朝 |
| 父親 | アバカ |
| 母親 | カイミシュ・ハトゥン |
| 宗教 | 仏教 |
アルグン(ارغون خان Arγun, Arghun, 1258年? - 1291年3月10日[1])は、イルハン朝の第4代君主(イル・カン、ハン、在位:1284年8月11日 - 1291年3月10日)。
第2代君主・アバカの長男。アバカの側室の一人カイミシュ・ハトゥン(エゲチ)の息子。第5代君主・ガイハトゥの異母兄で、第7代君主・ガザン・ハン、第8代君主・オルジェイトゥの父。『元史』の漢字表記では阿魯渾大王、『集史』などのペルシア語表記では ارغون خان Arghāūn khān と書かれる。
生涯
継承争い
父・アバカ没後のクリルタイで、後継を巡って叔父であるテグデル(フレグの7男)、モンケ・テムル(フレグの11男。フレグとアバカの正妃オルジェイ・ハトゥンの息子)らを推すグループと対立した。モンケ・テムルがアバカの死から25日後の1282年4月26日にモースルで急死すると[2]、テグデルの母クトイ・ハトゥンとモンケ・テムルの母オルジェイ・ハトゥンの両名は、アバカ一統が推すアルグンを後援した。しかし、他のフレグ家の王族たちや部将たちの多くがテグデルを推し、また、「ヤサ」の規定に従い君主位の継承は宗族の年長者によるべきであるという意見もはなはだ根強かった[3]。このため、モンケ・テムルの死の10日後にあたる1282年5月6日にクリルタイの全会一致をもってテグデルが即位することとなった。
しかし、テグデル推戴後もアルグンは弟のガイハトゥや従兄弟のバイドゥらとともにたびたび叛乱を起こし、一度ならずテグデル側に捕縛されたが、ついには逆にテグデルを捕らえた。この争乱の最中にアルグンを擁護していた叔父のコンクルタイ(フレグの9男)をテグデルが処刑し、これを恨んだ生母アジャジュ・エゲチらコンクルタイ家の人々が復讐としてテグデルを処刑するよう迫り、結局テグデルは1284年8月10日に処刑された。
アルグンは一時離反した叔父のフラチュ(フレグの12男)と和解すると、ガイハトゥらの推戴を受けて、マラーガ近傍のハシュトルード川とクルバーン・シラとの間にあったカムシウンという夏営地においてクリルタイを開催し、1284年8月11日に即位した[4]。
1286年2月24日(諸説あり)、モンゴル皇帝(カアン)クビライから勅書を奉じた使者が来訪し、アルグンにハンの称号を与え、アルグンの君主位継承が追認された[5]。
晩年
晩年は病を得て、1291年3月10日にアッラーン地方で冬営中に34歳で病没した。
その後、彼の遺骸はイラン中部ザンジャーンとアブハルの中間にあったモンゴル語で「クンクル・ウラン」と呼ばれたシャルーヤーズ草原の南部、スィジャース山に埋葬された。このクンクル・ウランに後年オルジェイトゥは自らの廟墓(オルジェイトゥ廟)を含むソルターニーイェを建設している。
ヨーロッパへの使節派遣


アルグンの治世にはマムルーク朝対策のため、ヨーロッパの勢力に使者を交していたことが知られている。主にローマ教皇庁とフランス王国へのものが有名である。1288年、ネストリウス派の「カタイとオング諸都市の首都大主教」バール・サウマらがローマへ派遣され、教皇ニコラウス4世に謁見して国書を手渡した。ニコラウス4世はこれを大いに歓迎してキリスト教徒の君主であるアルグンを称讃し、返書では「聖地エルサレムをキリスト教徒側に奪還してエルサレム王国の解放は遠からず容易に達成するであろう」とアルグンのエルサレム入城を進言している。またエラダク、トクダンのふたりのモンゴル王妃がカトリックに改宗したと聞き、両妃にも別途に書簡を送って言祝いだと伝えられる(前者はエラダクはアルグンと妃ウルク・ハトゥンとの娘オルジェイ・ハトゥンあたりかと考えられ、後者のトクダンは弟ガイハトゥの母后トクダン・ハトゥンと考えられる)。
また1289年にはアルグンの側近でジェノヴァ人ブスカレッロ・ド・ジスルフがローマにたどり着き、先に教皇からの返書に同意して聖地エルサレムの攻略案を了承する旨アルグンからの声明を伝え、さらにイングランド国王エドワード1世とフランス国王フィリップ4世にも同様にシリア・パレスティナ遠征の提案を了承する書簡をラテン語による注釈付きで届けたと言う。1291年1月にはこれらの書簡がフランス、イングランドに届き、8月には教皇ニコラウスはエドワード1世宛の親書でアルグンが自らの愛子にニコラウスという洗礼名を与えたことを引いて、アルグンからの書簡の紹介と十字軍への参加を要請している。しかし、この周到に錬られたシリア遠征計画も、フランスに達した2ヶ月後には、当のアルグンが病没してしまい事実上頓挫した。アルグンがこれらヨーロッパの教皇と君主たちへ発した勅書の内、ニコラウス4世とフィリップ4世宛の、朱印入りのウイグル文字モンゴル語国書がそれぞれバチカン図書館とフランス国立図書館に現在でも伝存している。
宗室
『集史』「アルグン・ハン紀」によると、アルグンには男子は4人、女子も4人いたという。
父母
- 父 アバカ
- 母 カイミシュ・エゲチ
兄弟・姉妹
后妃
- クトルク・ハトゥン [注 1] - 大ハトゥン。四男ヒタイ・オグルの母
- オルジェイ・ハトゥン[注 2]
- ウルク・ハトゥン[注 3] - 次男イェス・テムル、三男オルジェイトゥ、長女オルジェタイ、次女オルジェ・テムル、三女クトルグ・テムルの母
- セルジューク・ハトゥン[注 4]
- (大)ブルガン・ハトゥン[注 5] - 父アバカの妃。四女ダランチの母
- ブルガン・ハトゥン[注 6]
- トデイ・ハトゥン[注 7] - 父アバカの側室。前君主テグデルの妃。
側室
- コルタク・エゲチ - 長男ガザンの母
- クトイ
- エルケ・エゲチ
子女
男子
女子
- 長女 オルジェタイ - 母ウルク・ハトゥン。アミール・アリナクに降嫁。タージュ・ウッディーン・ハサン・ブズルグの母。
- 次女 オルジェ・テムル - 母ウルク・ハトゥン。大アミール・イリンジンに降嫁。
- 三女 クトルグ・テムル - 母ウルク・ハトゥン。ディヤール・バクルのアミール・ブラジュに降嫁。
- 四女 ダランチ - 母ブルガン・ハトゥン。ギレイ・バウルチの息子ジャンダンに降嫁。
脚注
注釈
- ^ オイラト部族出身。オイラト首長家のクドカ・ベキの親族で、アバカの臨終に立ち会ったテンギズ・キュレゲンの娘。テンギズはグユクの皇女を娶りクトルグを儲けたため、彼女はグユクの外孫にあたる。
- ^ ベスト部族出身のイラン駐留軍司令バイジュ・ノヤンの孫スラミシュの娘。クトルク・ハトゥンの死後、その地位を受け継ぐ。
- ^ ケレイト部族出身。祖父フレグの大ハトゥンドクズ・ハトゥンの兄弟サリジャの娘で、オン・ハンの曾孫にあたる。
- ^ ルーム・セルジューク朝の第14代君主スルターン・クルチ・アルスラーン4世の娘。
- ^ バヤウト部族の有力部将ノカイ・ヤルグチの姪。父アバカに最も寵愛されたの正妃。大ブルガン・ハトゥンとも。
- ^ コンギラト首長家当主デイ・セチェンの遠縁アバタイ・ノヤン(ヒンドゥスターン・カシュミール鎮守府軍中軍千戸長)の息子ウトマンの娘。父アバカの正妃ブルガン・ハトゥンと同名異人。彼女の死後その地位を受け継ぐ。アルグンの死後は弟ガイハトゥが受継ぎ、ガイハトゥの三男チン・プーラードを産む。
- ^ コンギラト部族出身。父アバカの側室のひとりで王女ユル・クトルグ、ノカイを産む。アバカの正妃ミリタイ・ハトゥン亡き後その地位を継承する。後にテグデルに受け継がれ、テグデルの大ハトゥン位を最後に継いで、その死後はアルグンの妃となった。
出典
- ^ ドーソン『モンゴル帝国史 5』、239頁
- ^ ドーソン『モンゴル帝国史 5』、119頁
- ^ ドーソン『モンゴル帝国史 5』、131頁
- ^ ドーソン『モンゴル帝国史 5』、189-190頁
- ^ ドーソン『モンゴル帝国史 5』、199-200頁
参考文献
関連項目
外部リンク
|
|
アルグン (1284–1291)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/27 07:07 UTC 版)
「フランクとモンゴルの同盟」の記事における「アルグン (1284–1291)」の解説
詳細は「アルグン」を参照 アバカは1282年に逝去し、ハーンの地位はイスラム教に改宗していた彼の弟テグデルに速やかに引き継がれた。テグデルは西欧との同盟を模索していたアバカの方針を翻し、その代わりに、マムルーク朝のスルタン、カラーウーンに同盟を求めた。カラーウーンはこの頃シリアへの進撃を続け、1285年に聖ヨハネ騎士団のマルガット城、1287年にラタキア、1289年にトリポリ伯国を占領していた。しかし、テグデルのイスラム傾倒主義は支持が得られず、1284年に仏教徒でアバカの長男のアルグンが大ハーンのクビライの支持を取り付けて反乱を起こし、テグデルを処刑した。それから、Arghunは西欧との同盟の意向を復活させて、複数の使節を欧州各国へ派遣した。 アルグンの最初の使節は、クビライ・ハンの西洋天文学部の長でネストリウス派の科学者イーサ・ケルメルチ(英語版)が送られた。ケルメルチは1285年に教皇ホノリウス4世に謁見し、サラセン人 (イスラム教徒) を 「追い出して」、 「偽りの地 (すなわち、エジプト)」を西欧人と分かち合おうと申し出た。第2の (且つ、恐らく最も有名な) 使節は、高齢の聖職者ラッバーン・バール・サウマであり、彼は当時としては珍しい中国からエルサレムまでという巡礼の最中で、イルハン朝に滞在していた。 バール・サウマと後のブスカレッロ・デ・ギゾルフィ(英語版)のような他の使節を通して、アルグンは、もしエルサレムが占領できた際には彼自身が洗礼を受け、キリスト教徒にエルサレムを返還するだろうと欧州の君主らに約束した。バール・サウマは欧州の各国君主によって暖かく歓迎されたが、西欧諸国の十字軍や聖地奪還に対する関心は失われつつあり、同盟関係を構築する任務はついに実を結ぶことは無かった。イングランドは外交代表として20年前のエドワード1世の十字軍の一員として従軍したジェフリー・オブ・ラングリー(英語版)を送ることによって応え、1291年、イングランド大使としてモンゴルの宮廷に送られた。
※この「アルグン (1284–1291)」の解説は、「フランクとモンゴルの同盟」の解説の一部です。
「アルグン (1284–1291)」を含む「フランクとモンゴルの同盟」の記事については、「フランクとモンゴルの同盟」の概要を参照ください。
固有名詞の分類
- アルグンのページへのリンク