【神式】式年祭・例年祭 (忌明け祭後の行事)
式年祭(仏教でいう回忌法要)
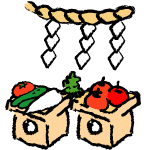 百日祭・一年祭・三年祭・五年祭・十年祭・二十年祭・三十年祭・四十年祭・五十年祭・百年祭がありますが、三十年祭で切り上げるのが一般的のようです。
百日祭・一年祭・三年祭・五年祭・十年祭・二十年祭・三十年祭・四十年祭・五十年祭・百年祭がありますが、三十年祭で切り上げるのが一般的のようです。
盆祭(例年祭)
仏教の盆供養と同じ日に行われ、神道では盆祭又は中元祭といって、お墓参りをしたり自宅に氏神の神官を招いて執り行いますが、故人が逝去後初めて迎える盆祭を新盆祭と言います。
ひとくちMEMO
- 宗教・宗派にかかわらず通夜・葬儀の儀式においては、町内会役員・近隣者・会社や職場や業界関係者・寺院や教会などの方々には、世話役・進行係・会計係・受付係・会場案内係・台所係・駐車及び交通整理係・霊柩車やハイヤー及びタクシーやマイクロバスの運転手・火葬場係員などの他、寺院のお手伝いさん・教会の聖歌隊やオルガニストなどとしてお世話になりますが、そうした方々への謝礼の献辞(表書き)は「御礼」とします。
(注:係員が公的職員の場合は謝礼受取りを禁じています。) - お祝い返しや香奠返しは通常1/2〜1/3返しとされていますが、基本的には「上に薄く下に厚く」返すのが一般的とされています。また、商品で返す場合は1/3返し、商品券で返す場合は1/2返し、両方の場合は各々1/3返しが最近の傾向です。
- 蓮の絵が入ったものは佛式用に付き、藍銀水引ののし紙は蓮の絵が入っていないものを用いる。
- 十年祭以降、二十年祭・三十年祭・四十年祭・五十年祭とあるが、十年祭以降は極内輪で、三十年祭で切り上げるのが一般的。
ご贈答のマナー
| 贈答様式 | 贈り元 | 献辞(表書き) | 慶弔用品 |
|---|---|---|---|
| 百日祭(百日目)時の神社・神官への謝礼 | 当家 | 御祭祀料 御祈祷料 御神饌料 御礼 |
【金封】 双銀結切り/双銀あわび結び 黄白結切り/黄白あわび結び 水引熨斗なし 【のし袋】 白無地/黄白結切り 黄白あわび結び |
| 新盆祭(例年祭)時の神社・神官への謝礼 | 当家 | ||
| 式年祭時の神社・神官への謝礼 一年祭(満一年目) 二年祭(満二年目) 五年祭(満五年目) 十年祭(満十年目) |
当家 | ||
| 式年祭時の神官への謝礼に付ける | 御膳料 | 【のし袋】白無地 | |
| 御車料 | |||
| 式年祭時にお供え金を贈る | 身内 身内以外 |
御霊前 玉串料 御榊料 |
【金封】 双銀結切り/双銀あわび結び 黄白結切り/黄白あわび結び 水引熨斗なし 【のし袋】 白無地/黄白(銀)結切り 黄白(銀)あわび結び |
| 式年祭時にお供え品を贈る | 身内 身内以外 |
御供物 御供 |
【のし紙】 藍銀結切り(蓮なし) 藍銀あわび結び(蓮なし) 黄白結切り/黄白あわび結び |
| 式年祭時の香奠返し※ | 当家 | 偲び草 志 茶の子 |
※忌明け法要の日と香奠返し(忌明け法要の引き出物)の表書きと贈る時点の違い
使用例(のし紙/金封/のし袋の様式)
| のし紙/金封/のし袋の様式 | 使い方 |
|---|---|

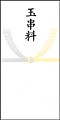

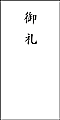 
 |
式年祭
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 16:22 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2017年8月)
|
式年祭(しきねんさい)は、決められた期間ごとに行われる祭祀のことであり、神社の祭礼や祖先祭祀において見られる祭祀形態である。
由緒ある神社の一部では、定まった年ごとに行われる祭祀がある。例えば、鹿島神宮、香取神宮では12年ごとの午の年に、盛大な神幸祭を行うこととなっている。また、諏訪大社でも7年ごと(開催年を1年と数えるため実際の周期は6年)の寅もしくは申の年に御柱祭が行われることは有名である。これらの祭りは毎年行われる祭り(例祭)よりも大規模であることが多く、重視されている祭りといえる。
神社には、一定の年ごとに社殿の建て直し(式年遷宮)をするところがみられるが、社殿の建て直し自体が祭祀の一環だという見方をしたとき、これも式年祭の一種と言える。最も有名なのは伊勢神宮式年遷宮で、20年ごとに全ての社殿を建て直し、大規模な祭礼を行うことになっている。あまり注目されないが、諏訪大社の御柱祭もその儀礼の中には社殿の建て直しが含まれており、御柱祭も式年遷宮に含めることができる。なお、式年祭は大社に限らず、氏神レベルでの神社においても、その神社独自の由緒に基づいて、式年祭を行っているところがある。
一方、祖先祭祀においても、決められた年ごとに祭祀を行うことが多い。一般に仏教行事として行われる年忌では、一周忌・三回忌・七回忌・十三回忌・十七回忌・二十三回忌などと特定の年(等間隔ではない)に、通常の祭祀とは違った特別な祭祀が行われる。
宮中祭祀における式年は、3年・5年・10年・20年・30年・40年・50年・以後100年ごとと規定され、祖先祭祀に関するものにおいて式年の大祭と小祭が神式で行われている。
人物を祀る日光東照宮や北野天満宮では50年ごとに大祭が行われており、これは両者の結合ともいうことができるかもしれない。
主な式年祭
宮中祭祀の式年祭
- 大祭
- 先帝以前3代の式年祭
- 先后の式年祭
- 皇妣たる皇后の式年祭
- 小祭
- 綏靖天皇以下先帝以前4代に至る歴代天皇の式年祭
式年祭
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:24 UTC 版)
式年祭として、20年に1度本殿一棟を造り替える大遷宮祭と、その間2回の修理を行う小遷宮祭が行われる。祭は、穂高神社に伝わる『三宮穂高社御造宮定日記』(安曇野市指定文化財)に従い、文明15年(1483年)以前からの古い形式で、安曇野市指定無形民俗文化財に指定されている。 神事は遷座の100日前の四至榊立神事から始まる。役目を終えた本殿は各社に払い下げられるか取り壊すかされ、移築されて現存のものは十数棟ある。
※この「式年祭」の解説は、「穂高神社」の解説の一部です。
「式年祭」を含む「穂高神社」の記事については、「穂高神社」の概要を参照ください。
「式年祭」の例文・使い方・用例・文例
式年祭と同じ種類の言葉
- 式年祭のページへのリンク


