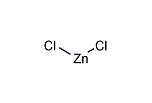えんか‐あえん〔エンクワ‐〕【塩化亜鉛】
ジクロロ亜鉛
塩化亜鉛
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/04 15:48 UTC 版)

|
|

|
|
| 物質名 | |
|---|---|
|
塩化亜鉛 |
|
|
別名
塩化亜鉛(II) |
|
| 識別情報 | |
| ECHA InfoCard | 100.028.720 |
| EC番号 |
|
| RTECS number |
|
| 国連/北米番号 | 2331 |
|
CompTox Dashboard (EPA)
|
|
| 性質 | |
| ZnCl2 | |
| モル質量 | 136.315 g/mol |
| 外観 | 白色固体 |
| 密度 | 2.907 g/cm3 |
| 融点 | 275 °C (527 °F; 548 K) |
| 沸点 | 756 °C (1,393 °F; 1,029 K) |
| 432 g/100 mL (25 ℃) | |
| 構造 | |
| 4つの結晶系があり、無水物では β 相が最も安定。 | |
| 四面体形, 気相では直線形 | |
| 関連する物質 | |
| その他の 陰イオン |
フッ化亜鉛 臭化亜鉛 ヨウ化亜鉛 |
| その他の 陽イオン |
塩化カドミウム 塩化水銀(II) |
|
特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。
|
|
塩化亜鉛(えんかあえん、Zinc chloride)とは、亜鉛の塩化物である。
概要
無水物の斜方晶は塩素が六方最密構造、亜鉛が4面体空孔に配置した構造。過剰な塩素の存在や濃厚溶液では亜鉛に四面体型に塩素が配位した[ZnCl4]2-構造が見られる。28 ℃以上では無水塩が[2]、28 ℃以下で水和物を形成し、28 ℃で1.5水和物、11.5 ℃で2.5水和物、6 ℃で3水和物、−30 ℃で4水和物を形成することが知られている[3] 。
歴史
1648年にドイツの J. R. グラウバーによって最初に合成された[3]。
性質
潮解性を示し水溶液は一部が加水分解により中程度の酸性(pHは4前後)を示す 。濃厚溶液は粘度が高く蛍光を発する。水の他にエタノール、アセトン、グリセリン、エーテルにも溶ける。加熱すると分解し、有毒なヒューム(煙、粉塵: 塩化水素、酸化亜鉛)を生じる。
人体への影響
塩化亜鉛の微粉末(ヒューム)は刺激性であり、眼、呼吸器あるいは皮膚を刺激する。ヒュームを大量に吸引するとチアノーゼを起こす[3] 。水生生物に対して毒性が強い[1]。
製法
製造法は金属亜鉛または酸化亜鉛に塩酸を加えると得られる。あるいは工業的には無水塩化亜鉛は亜鉛と塩化水素から以下の反応で生成する[3] 。
塩化亜鉛
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 04:07 UTC 版)
塩化亜鉛による煙を生成するための最も一般的な組成物は、六塩化エタン、粒状アルミニウム、酸化亜鉛の混合物で、塩化亜鉛スモークミクスチャー(zinc chloride smoke mixtur、通称HC)と呼ばれる。 ここで生成される煙は灰白色をしており、塩化亜鉛、亜鉛酸塩化物、塩化水素から成り、空気中の湿気を吸収する。また、有機塩素、ホスゲン、一酸化炭素、塩素を含む。 その毒性は主に強酸性の塩化水素酸によるものだが、水と塩化亜鉛の反応によって産生した熱によっても生じる。高濃度の煙を吸入するのは非常に危険である。
※この「塩化亜鉛」の解説は、「煙幕」の解説の一部です。
「塩化亜鉛」を含む「煙幕」の記事については、「煙幕」の概要を参照ください。
「塩化亜鉛」の例文・使い方・用例・文例
- 塩化亜鉛という化合物
塩化亜鉛と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
- 塩化亜鉛のページへのリンク