HV‐1
| 分子式: | C32H22O12 |
| その他の名称: | Antibiotic SC-2051、SC-2051、抗生物質SC-2051、1,1'-[4,4'-Dioxo-5,5',6,6',8,8'-hexahydroxy-9,9'-bi[4H-naphtho[2,3-b]pyran]-2,2'-diyl]bis(2-propanone)、2,2'-Diacetonyl-5,5',6,6',8,8'-hexahydroxy-9,9'-bi[4H-naphtho[2,3-b]pyran]-4,4'-dione、HV-1 |
| 体系名: | 1,1'-[4,4'-ジオキソ-5,5',6,6',8,8'-ヘキサヒドロキシ-9,9'-ビ[4H-ナフト[2,3-b]ピラン]-2,2'-ジイル]ビス(2-プロパノン)、2,2'-ジアセトニル-5,5',6,6',8,8'-ヘキサヒドロキシ-9,9'-ビ[4H-ナフト[2,3-b]ピラン]-4,4'-ジオン |
電位依存性プロトンチャネル
(HV‐1 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/01 04:55 UTC 版)
電位依存性プロトンチャネル[1](でんいいぞんせいプロトンチャネル、英語: voltage-gated proton channel、略称:Hv)は電位依存性イオンチャネルの一つであり、プロトン(H+)を膜電位が脱分極したときに通過させることができるイオンチャネルである[2]。従来の電位依存性イオンチャネルは6回膜貫通構造が4つ組み合わさることで1つのイオン通過経路を作るのに対し、電位依存性プロトンチャネルは4回膜貫通構造のみでH+を通すことができ、基本的にはこれが2つ組み合わさったダイマーとして存在している点でユニークなチャネルである[2]。哺乳類ではHv1という一種類の電位依存性プロトンチャネルしか存在していない[3]ため、本記事ではHv1を主として扱う。
名称
Hv1という名称は初めて発見された電位依存性プロトンチャネルであるためである。HはもちろんH+を意味し、vは電位依存性(voltage-gated)であるためである[2]。他のチャネルにおいてもこれに似た命名法は使用されており、例えばCav1.1やKv1.1などがある。
Hv1以外にVSOPとして言及されることがある。これは後述する電位センサーのみから成るタンパク質(voltage-sensor-only protein)であるためである[2]。
正式な遺伝子名としてはHVCN1となっているが、タンパク質の特徴をよく表しているHv1として言及されることが多い[注 1]。HVCN1は12番染色体長腕にある12q24.11という位置にコードされている[3]。
分子系統学
多くの電位依存性イオンチャネルには同じイオンを通すものであっても種類がある。例えば、電位依存性カリウムチャネルであればKv7.1やhERGなど40種類も知られている。しかし、電位依存性プロトンチャネルにおいては哺乳類ではHv1ただ1つしか存在しない[3]。
進化上最も早く見られるHv1は原生生物におけるHv1である。電位依存性ナトリウムチャネルや電位依存性カルシウムチャネルの電位センサードメインが分離してできたものだと考えられている[3]。なお、原核生物にはいかなる電位依存性プロトンチャネルの発現も確認されていない[3]。
原生生物からHv1の発現が確認されているとはいえ、それ以降のすべての生物においてHv1が確認されているわけではない。例えば、モデル生物で著名な例を挙げるとキイロショウジョウバエ、出芽酵母 Saccharomyces cerevisiae、線虫 Caenorhabditis elegans、キイロタマホコリカビなどがある。これらの生物ではその生理学的な機能上、必要性がないために発現していないと思われる[3]。
電位依存性プロトンチャネルを持たない生物が居る一方で、複数種の電位依存性プロトンチャネルを持つ生物も存在する。例えばジャンボアメフラシAplysia californicaはHv2やHv3を持っており、マガキCrassostrea gigasはHv4を持つ[3]。
歴史
Hv1を流れるプロトン電流は1982年、ヒメリンゴマイマイの神経細胞に塩化水素を注入してプラスに膜電位を固定した実験で初めて測定された。プラスに膜電位を固定するとH+の流出により細胞内pHが上昇し、それに伴ってプロトン電流が減衰する現象も確認された。1993年にはヒトの好中球でもプロトン電流が観測され、食細胞におけるNADPHオキシダーゼの活性化に重要であることもこのとき示唆された[2]。
数々の研究を経て2006年にHv1をコードする遺伝子が発見された。この発見は当時のイオンチャネルの常識を覆すものであり、多くの電位依存性イオンチャネルで電位センサードメイン(VSD)として成り立っている構造が単独でプロトンを通すチャネルを形成する、という事実は予想外のものであった[2]。
Hv1は安定した結晶構造をとれず、X線結晶構造解析がそのままの状態では行えないためHv1の詳細な構造は発見から長らく分かっていなかった。しかし、2014年、大阪大学の研究者らによってHv1キメラをうまく作成することで結晶構造解析に成功した[4]。
構造

Hv1の構造はN末端細胞質領域、膜貫通領域、C末端のコイルドコイル構造部位から成る[5]。膜貫通領域はN末端側からS1~S4と呼ばれており、これにより4回膜貫通となっている。4回膜貫通の2つのサブユニットが集まってホモダイマーを形成する[2]。
かねてより発見されていた電位依存性カリウムチャネルなどの電位依存性イオンチャネルはS1~S4に加えてS5~S6も存在し、S1~S4は電位センサードメイン(VSD)、S5~S6はポアドメイン(PD)と呼ばれる。この6回膜貫通のモノマーが4つ集まったテトラマーとして存在し、4つのPDが一つのポアを形成する。しかし、Hv1にはS1~S4しかないため従来のチャネルのVSDに相当する構造しか存在せず、PDが存在しない。そこでHv1は各モノマーのVSDに個別のH+通過経路を持っているという電位依存性イオンチャネルの中では異質なチャネルである。同様の構造を持つ物質として電位依存性ホスファターゼがあるが、こちらはイオン通過能は持たない[2]。
Hv1は電位センサードメイン(VSD)のみでH+を通過させることができるが、従来の電位依存性イオンチャネルのVSDはH+を通過させることはできない。しかし、Shaker型K+チャネルにおいて、S4に存在するアルギニンの一部をヒスチジンに単変異させるとH+を通すようになったという結果が報告されており、Hv1は構造的に従来の電位依存性イオンチャネルのVSDに類似していることが分かる[6]。
電位依存性の構造
電位依存性の機構には従来の電位依存性イオンチャネルとの類似性がある。電位依存性K+・Na+チャネルではチャネル開口にしたがいS4ドメインが外側に移動するが、これはHv1においても起こる。これにはS4に含まれる正電荷を帯びたアミノ酸残基が重要である[2]。Hv1においてはこの電位センサーモチーフがRxWRxxR(Rはアルギニン、Wはトリプトファン、xはその他)という順序で並んでおり、3つのアルギニンが重要な役割を果たす[3]。しかし、Hv1では3つあるアルギニンのうち、C末端側の2つが無くてもH+チャネルとしての機能は保持されることが分かっている[2]。
S4の正電荷Rの間にあるxにはロイシン、バリン、イソロイシンのような疎水性のアミノ酸が含まれている[6]。一つ目と二つ目のRの間にあるトリプトファン(W)はHv1の電位センサーモチーフとして高度に保存されている。トリプトファンを別のアミノ酸に変えると活性化が100倍も速くなったことから、H+の輸送を遅くするのに重要と考えられている[7]。
S4が外側に動いた後、S1が内側に移動する可能性が考えられている。S1の内側への移動は負電荷のアスパラギン酸やグルタミン酸による。蛍光変化の実験では二相性の変化が確認されており、S4の移動のみでない可能性を強める。順序としてはS4の外側への移動、S1の内側への移動、これら2つの協調による開口の順であると考えられている[6]。
H+の通過に重要な構造
Hv1をH+が通過するための機構にはグロッタス機構が関わっている。プロトンは水和によりH3O+の形で存在し、水分子から水分子へとH+を受け渡すことで、Hv1におけるH+通過も行われていると考えられている[2]。水分子のみならず、Hv1の通路を構成する極性アミノ酸残基もグロッタス機構に貢献していると考えられている[2]。
通路のうち、S1がゲートを構成し、Hv1のH+選択性を高めていると考えられている。特にヒトでは112番目のアスパラギン酸(D112)がH+選択性に関与しており、アラニンやセリン、ヒスチジンなどの中性のアミノ酸に変異させた場合、Cl-を通過させてしまう。アスパラギン酸と同様に酸性アミノ酸のグルタミン酸への変異ではH+選択性を失わなかったことから、この部位のカルボキシ基が重要と考えられている[7]。
Hv1にはイオンや水の漏れを防ぐためにガスケットと呼ばれる疎水性の構造が膜貫通領域の中ほどに存在する[1]。ガスケットはD112のようなH+選択性には関わらないためガスケットを構成するアミノ酸変異体でもH+選択性は保たれる。しかし、ガスケットが無いとチャネルが開いていない状態でもイオンや水を通すため、非活性化時にもH+を少し通してしまう。それゆえに、ガスケット部分を極性アミノ酸に変異させた変異体では通常H+電流の見られない負の電位でもリーク電流が流れるという特徴がある。ガスケットを構成する疎性アミノ酸はV109、F150、V177、V178が考えられている[注 2][8]。
C末端とダイマー形成
C末端領域はダイマー形成に重要である。Hv1がダイマーを形成するとチャネルの各モノマーが協調してチャネルの開閉を行うため、開閉をゆっくりとさせる効果がある[9]。実際にC末端を欠失させた変異体ではWTのHv1よりも5~6倍活性化速度が速いことが実験で明らかになっている[2]。ダイマーを形成するためには膜貫通領域同士での相互作用も必要であると考えられているが、S4-S4同士が相互作用するとする説や、S1とS4の両方において相互作用するという説がある[9]。ダイマーの形成は生理学的な機能上重要であると考えられてはいるものの、モノマーのみでもH+の選択性や電位・pH依存性といった基本的な特徴は保持しており、モノマーとして発現している可能性がある種さえ居る[3]。
ダイマーは2つのモノマーが自然に形成するものであるが、これを人為的に一方のC末端ともう一方のN末端をつなげたものをタンデムと呼ぶ。タンデムの場合はモノマーとしてよりもダイマーとして機能することが分かっている[2]。人為的に作成されたチャネルとしてはモノマー・ダイマー以外にトリマーやテトラマーがある。これらは活性化速度がダイマーよりも速かったことから、協調はしていないと考えられる[10]。
N末端
N末端は活性化速度の制御に関わっている。例えばHv1のN末端の29番目のトレオニン残基(T29)のリン酸化がコンダクタンスと電位の関係を負の方向にシフトさせる(=より低い電位で活性化しやすくなる)ことが分かっている[11]。しかし、N末端は立体構造が分かっていないこともあり、未解明な点が多く残されている[7]。
構造解析

Hv1はキメラ蛋白でのみ結晶構造解析が実現できている[6]。初めてキメラチャネルを実現した竹下らのmHv1ccはマウス由来Hv1(mHv1)のC末端にあるコイルドコイル構造部位をSaccharomyces cerevisiaeのGCN4[注 3]に置換し、S2中盤~S3中盤をカタユウレイボヤの電位依存性ホスファターゼ(Ci-VSP)の対応する部分で置換し、N末端を74塩基削った人工的なHv1である。キメラ化により熱安定性を高めることができ、結晶化に至った。キメラ化したmHv1ccにおいても電位依存性やpH依存性が確認されている[4]。
機能
分子的機能
Hv1は膜電位が正のときに開口し、細胞内から細胞外へH+を流出させる外向き整流性のチャネルである。ネルンストの式を用いれば細胞内外のpHが同じとき電流の向きが変わる電位である反転電位は0mVであることが分かる[注 4]が、この反転電位よりもチャネルが開口する最小の電位である閾値電位が約20mVと大きいため外向き整流性となる[注 5]。ただし、渦鞭毛藻の一種であるKarlodinium veneficumでは生理的条件でも反転電位>閾値電位となるため、負の膜電位でもH+が通過でき、外向き整流性ではない[2]。外向き整流性のHv1の反転電位を実験的に求めるためには先に閾膜電位よりも大きい電流を加えた後に、脱活性化したときに流れるテール電流が正から負に変わる電位を反転電位とすれば測定できる[3]。
Hv1の活性化は細胞内・細胞外両方のpH感受性がある。細胞内pH(pHi)が低下するとコンダクタンス-電位関係が負にシフトし、細胞外pH(pHo)が低下するとコンダクタンス-電位関係は正にシフトする。つまり、pHo-pHiが低下すればコンダクタンス-電位関係は正にシフトするということであり、この差はΔpHと呼ばれる[2]。活性化がpH感受性な一方で、脱活性化ではpH感受性はあまりない[2]。
Hv1は他のイオンチャネルよりも温度感受性が高いこともよく知られている。活性化速度の温度係数Q10は他の電位依存性イオンチャネルでは3~5なのに対して、Hv1では6~9程度であるという結果が測定されている[5]。
H+には中性子が一つ多い重水素(2H+)という同位体が存在する。H+を2H+に変えても基本的な機能は同じであるが、活性化速度が3倍遅くなる。これは2H+における水素結合が強く、極性アミノ酸残基との親和性が高まるためであると考えられている[2]。
生理的機能
生体内のH+はプロトンポンプ、輸送体、イオンチャネルなどの細胞膜に発現するタンパク質によって調節されている。このH+を調節するタンパク質の一つとしてHv1が知られている[5]。Hv1の機能はH+の外向きの電流を流すことであり、つまり、細胞内から細胞外へのH+の排出である[2]。
免疫系
生理的に最も重要といわれる機能が食細胞における呼吸バーストへの関与である。好中球やマクロファージのような食細胞は活性酸素を産生するが、そのためにはNADPHオキシダーゼという酵素の作用が必要である。NADPHオキシダーゼは細胞内のNADPHから細胞外のO2へ電子を受け渡してスーパーオキシドO2-とするが、そのときにH+が生じる。このときに、Hv1が生じたH+による膜電位の上昇・pHの変動を補償する[2]。同時に、排出されたH+はO2-から過酸化水素H2O2や次亜塩素酸HOClの産生にも役立つ[2]。
リンパ球の中ではB細胞でHv1の発現が確認されている。Hv1抗体による免疫染色ではT細胞には染色が見られないが、B細胞では高レベルに発現していることが報告されている。B細胞でも信号伝達のためにROSが用いられており、ROSが一時的にプロテインチロシンホスファターゼを阻害することがB細胞の活性化に重要と考えられている[2]。
好塩基球では食細胞で見られるenhanced gating modeが見られないかわりに、活性化によりヒスタミンの放出が引き起こされることが分かっている。ヒスタミンが放出されるときにCa2+の流入が起こるため、細胞内外の電荷を調節するためにHv1が機能している可能性がある[2]。
神経系
神経系においてはマクロファージ様細胞である小膠細胞(ミクログリア)がHv1を発現している。ミクログリアは脳の髄鞘が活動に伴い変化する過程において重要な働きを持っている。炎症や神経毒性により髄鞘が損傷すると、損傷した髄鞘を取り除くためにミクログリアが働く。この際にROSが上の貪食細胞での例のように産生され、Hv1も協調して働く[12]。
生殖器系
ヒトでは精子にHv1が発現しており、pHiの上昇、つまりアルカリ化が受精能獲得に関係していると考えられている。精液中には多数のZn2+が含まれており、通常時は精子細胞内のアルカリ化が阻害されている。しかし、女性器に入るとZn2+が緩衝され、プロトンチャネルの阻害が弱まることでH+が排出される[2]。精子細胞内のアルカリ化はCatSperチャネルを活性化し、精子運動能を高める[5][13]。
呼吸器系
気道上皮細胞にもHv1は存在しており、気道におけるH+分泌の多くをHv1が占めている。このH+分泌はHv1を阻害するZn2+以外に、NADPHオキシダーゼの阻害によっても抑制されることから、オキシダーゼの作用で生まれたプロトン勾配でH+が分泌されていると考えられる[2]。
その他の機能
Hv1はH+の排出によって間接的にCa2+によるシグナル伝達を制御している可能性がある。例えば、好中球のHv1を欠失させた実験ではCa2+の流入成分の低下やそれによる運動性の低下を起こすことが示された[14]。また、CatSperチャネルにより行われる精子の運動能獲得もCa2+シグナルによる例の一つである[13]。他にも膵臓β細胞ではHv1欠失マウスが高血糖になったことが報告されており、Ca2+の流入が低下し、インスリンが分泌できなくなるという機序が想定されている[15]。
他にもHv1の生理学的機能としては軟骨細胞における低浸透圧ショック後の細胞内アルカリ化や心臓線維芽細胞における膜電位・pH調節[6]、膵β細胞、クッパー細胞、脂肪細胞におけるホルモン分泌[3]などに関わっている。
他の生物における機能
Hv1が初めて発見された渦鞭毛藻においてはルシフェリン・ルシフェラーゼによる生物発光に関わっている。渦鞭毛藻の液胞に活動電位が発生すると液胞膜からつながっているシンチロンというルシフェリンやルシフェラーゼの入った顆粒をも脱分極させ、液胞からシンチロンへのH+流出が起こる。これによりシンチロンのpHが酸性側に傾き、ルシフェリン・ルシフェラーゼの至適pHとなることで生物発光を起こすと考えられている[2]。
円石藻においては炭酸カルシウムの生成が行われるが、その際にの反応が起きてH+が蓄積するため、H+の排出にHv1が役立っていると考えられている[2]。
薬理学
Hv1はPMAによるリン酸化で特殊な活性化が行われることが分かっている。この活性化様式をenhanced gating modeといい、コンダクタンス-電位関係の負のシフト、最大コンダクタンスの上昇、活性化速度上昇などが起こる。一方で、脱活性化速度は低下する。PMAのみならず、アラキドン酸、fMLF[注 6]、IL-5、LTB4などのアゴニスト刺激によっても起こる。これらの機構にはHv1のN末端に存在するトレオニンのリン酸化が重要であると考えられており、アラニン変異では活性化が起こらなくなることが報告されている[2]。
Hv1の活性剤としてはほかに不飽和脂肪酸、内因性カンナビノイド[5]などがある。
Hv1はZn2+によって阻害されることがよく知られている。活性化(開口)状態ではZn2+は結合せず、非活性化(閉鎖)状態のときに結合する[1]。この結合にはS2やS4に存在するヒスチジン残基やS1に存在する酸性アミノ酸が関わっていると考えられている[1]。生物種によってZn2+による阻害のされやすさは異なり、カタユウレイボヤや円石藻のEmiliania huxleyiなどではZn2+による阻害が他の種よりも弱いことが明らかになっている[2]。また、モノマーの場合はZn+による阻害がダイマーの時よりも弱いことが分かっている[3]。
ほかに重金属イオンとして、Cd2+、Be2+、Al3+、Mn2+、Co2+、Ni2+、Cu2+、La3+、Gd3+、Hg2+、Pb2+などもHv1を阻害することが報告されている[2]。
グアニジン誘導体もHv1阻害剤として作用する。グアニジン誘導体は細胞内側から結合し、Hv1が開口しているときに阻害する作用を持つ開状態チャネル阻害薬である[6][5]。
他に阻害剤としてはクモ毒のハナトキシンが知られている[5]。
疾患との関与
がんにおける発現
Hv1はがん細胞において異常に発現していることが知られている。がん細胞ではワールブルグ効果が見られ、ブドウ糖代謝をほとんど解糖系に依存している。解糖系の最終代謝産物は乳酸であるためそのままではがん細胞に酸が蓄積してしまうが、Hv1が酸の細胞外排出に寄与していると考えられている[16]。
神経膠腫、乳癌、大腸癌などではHv1の活性が浸潤・転移に関連していることが知られている[6]。この機構はがん細胞の細胞外の環境を酸性にすることで免疫細胞から逃避するのに役立っているためであると考えられている[16]。Hv1のsiRNAで機能を阻害すると細胞の遊走が減少したことが報告されており、Hv1阻害によりがんの転移を抑制できる可能性がある[2]。
Hv1遺伝子(HVCN1)の体細胞変異を調べた研究によると、Hv1のN末端やS4、C末端領域の変異が多いことが明らかになっている[16]。
脳虚血後の神経障害
Hv1は脳虚血後に起こる脳への障害を増大させてしまう可能性がある[6]。ミクログリアでHv1の高発現によりROSが過剰に産生されると、さまざまなシグナル伝達を誘導し、組織損傷を引き起こし得る[12]。実際にHv1を欠失させたマウスの実験ではTNF-αやIL-6などの炎症性サイトカインを含め調べたところ、ROS産生のみ減少したという報告がある[注 7][17]。
脚注
- ^ ゆえに、当記事でもHv1と表記する。
- ^ いずれもヒトにおける位置。他の種では異なる
- ^ 同様に、コイルドコイル構造をとる。
- ^ より、pHが同じならばは変わらないので、0であることは明らかである[3]。
- ^ 閾値電位をVthreshold、反転電位をVrevとするとこれらにはの関係があり、生理的条件下ではとなる。となるためにはVrev > 110mV()より、細胞内外のpH差が1.8よりも大きく離れる必要性があり、生理的条件ではこの条件を満たさない。
- ^ N-ホルミルメチオニン、ロイシン、フェニルアラニンがこの順にN末端から並んだトリペプチド。
- ^ 他にIL-1β、IFN-γ、VEGF、NOなどを調べている。
出典
- ^ a b c d 竹下浩平; 岡村康司; 中川敦史 (2015). “電位依存性プロトンチャネル(VSOP)の結晶構造から考察するプロトン漏洩制御機構”. 生化学 87 (5): 625-628. doi:10.14952/SEIKAGAKU.2015.870625.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Decoursey, Thomas E. (2012). “Voltage-gated proton channels”. Comprehensive Physiology 2 (2): 1355-1385. doi:10.1002/cphy.c100071. PMC 3965195. PMID 23798303.
- ^ a b c d e f g h i j k l m Chaves, Gustavo; Jardin, Christophe; Derst, Christian; Musset, Boris (2023). “Voltage-Gated Proton Channels in the Tree of Life”. Biomolecules 13 (7): 1035. doi:10.3390/biom13071035. PMC 10377628. PMID 37509071.
- ^ a b Takeshita, Kohei; Sakata, Souhei; Yamashita, Eiki; Fujiwara, Yuichiro; Kawanabe, Akira; Kurokawa, Tatsuki; Okochi, Yoshifumi; Matsuda, Makoto et al. (2014). “X-ray crystal structure of voltage-gated proton channel”. Nature Structural & Molecular Biology 21 (4): 352-357. doi:10.1038/nsmb.2783. PMID 24584463.
- ^ a b c d e f g Fujiwara, Yuichiro (2024). “Temperature Dependent Activity of the Voltage-Gated Proton Channel”. Advances in Experimental Medicine and Biology 1461: 109-125. doi:10.1007/978-981-97-4584-5_8. PMID 39289277.
- ^ a b c d e f g h Castillo, Karen; Pupo, Amaury; Baez-Nieto, David; Contreras, Gustavo F.; Morera, Francisco J.; Neely, Alan; Latorre, Ramon; Gonzalez, Carlos (2015). “Voltage-gated proton (Hv1) channels, a singular voltage sensing domain”. FEBS Letters 589 (22): 3471-3478. doi:10.1016/j.febslet.2015.08.003. PMID 26296320.
- ^ a b c DeCoursey, Thomas E.; Morgan, Deri; Musset, Boris; Cherny, Vladimir V. (2016). “Insights into the structure and function of HV1 from a meta-analysis of mutation studies”. The Journal of General Physiology 148 (2): 97-118. doi:10.1085/jgp.201611619. PMC 4969798. PMID 27481712.
- ^ Banh, Richard; Cherny, Vladimir V.; Morgan, Deri; Musset, Boris; Thomas, Sarah; Kulleperuma, Kethika; Smith, Susan M. E.; Pomès, Régis et al. (2019). “Hydrophobic gasket mutation produces gating pore currents in closed human voltage-gated proton channels”. PNAS 116 (38): 18951-18961. doi:10.1073/pnas.1905462116. PMC 6754559. PMID 31462498.
- ^ a b Mony, Laetitia; Stroebel, David; Isacoff, Ehud Y. (2020). “Dimer interaction in the Hv1 proton channel”. PNAS 117 (34): 20898-20907. doi:10.1073/pnas.2010032117. PMC 7456152. PMID 32788354.
- ^ Fujiwara, Yuichiro; Kurokawa, Tatsuki; Takeshita, Kohei; Nakagawa, Atsushi; Larsson, H. Peter; Okamura, Yasushi (2013). “Gating of the designed trimeric/tetrameric voltage-gated H+ channel”. The Journal of Physiology 591 (3): 627-640. doi:10.1113/jphysiol.2012.243006. PMC 3577547. PMID 23165764.
- ^ Musset, Boris; Capasso, Melania; Cherny, Vladimir V.; Morgan, Deri; Bhamrah, Mandeep; Dyer, Martin J. S.; DeCoursey, Thomas E. (2010). “Identification of Thr29 as a critical phosphorylation site that activates the human proton channel Hvcn1 in leukocytes”. The Journal of Biological Chemistry 285 (8): 5117-5121. doi:10.1074/jbc.C109.082727. PMC 2820736. PMID 20037153.
- ^ a b Tang, Yingxin; Wu, Xuan; Li, Jiarui; Li, Yuanwei; Xu, Xiaoxiao; Li, Gaigai; Zhang, Ping; Qin, Chuan et al. (2024). “The Emerging Role of Microglial Hv1 as a Target for Immunomodulation in Myelin Repair”. Aging and Disease 15 (3): 1176-1203. doi:10.14336/AD.2023.1107. PMC 11081154. PMID 38029392.
- ^ a b Lishko, Polina V.; Kirichok, Yuriy (2010). “The role of Hv1 and CatSper channels in sperm activation”. The Journal of Physiology 588 (23): 4667-4672. doi:10.1113/jphysiol.2010.194142. PMC 3010136. PMID 20679352.
- ^ El Chemaly, Antoun; Okochi, Yoshifumi; Sasaki, Mari; Arnaudeau, Serge; Okamura, Yasushi; Demaurex, Nicolas (2010). “VSOP/Hv1 proton channels sustain calcium entry, neutrophil migration, and superoxide production by limiting cell depolarization and acidification”. The Journal of Experimental Medicine 207 (1): 129-139. doi:10.1084/jem.20091837. PMC 2812533. PMID 20026664.
- ^ Pang, Huimin; Wang, Xudong; Zhao, Shiqun; Xi, Wang; Lv, Jili; Qin, Jiwei; Zhao, Qing; Che, Yongzhe et al. (2020). “Loss of the voltage-gated proton channel Hv1 decreases insulin secretion and leads to hyperglycemia and glucose intolerance in mice”. The Journal of Biological Chemistry 295 (11): 3601-3613. doi:10.1074/jbc.RA119.010489. PMC 7076216. PMID 31949049.
- ^ a b c Jardin, Christophe; Derst, Christian; Franzen, Arne; Mahorivska, Iryna; DeCoursey, Thomas E.; Musset, Boris; Chaves, Gustavo (2025). “Biophysical Properties of Somatic Cancer Mutations in the S4 Transmembrane Segment of the Human Voltage-Gated Proton Channel hHV1”. Biomolecules 15 (2): 156. doi:10.3390/biom15020156. PMC 11853527. PMID 40001460.
- ^ Wu, Long-Jun; Wu, Gongxiong; Akhavan Sharif, M. Reza; Baker, Amanda; Jia, Yonghui; Fahey, Frederic H.; Luo, Hongbo R.; Feener, Edward P. et al. (2012). “The voltage-gated proton channel Hv1 enhances brain damage from ischemic stroke”. Nature Neuroscience 15 (4): 565-573. doi:10.1038/nn.3059. PMC 3314139. PMID 22388960.
外部リンク
- 研究紹介 - 大阪大学大学院医学系研究科/生命機能研究科 統合生理学教室
- 電位依存的プロトンチャネル分子の発見 - 生理学研究所
- HV‐1のページへのリンク
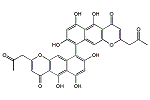
![{\displaystyle {\mathrm {HCO} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}{\vphantom {A}}^{-}{}\mathrel {\longrightarrow } {}\mathrm {CO} {\vphantom {A}}_{\smash[{t}]{3}}{\vphantom {A}}^{2-}{}+{}\mathrm {H} {\vphantom {A}}^{+}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d3eac4d5c4bc9b1f8998b172454e489922c15fa5)
![{\displaystyle V_{rev}={\frac {RT}{zF}}\ln {\frac {[H^{+}]_{o}ut}{[H^{+}]_{i}n}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/52c0ac48d1e7d5fc58c140ba7c341183f3658193)
![{\displaystyle [H^{+}]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/92a39e055b2aeeb66152908dc9af7b721759d53e)



![{\displaystyle V_{rev}={\frac {RT}{F}}\ln {\frac {[H^{+}]_{o}}{[H^{+}]_{i}}}\approx -61\Delta pH}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/cc605922db633f5f942722d353c2d9777eaa76a1)
