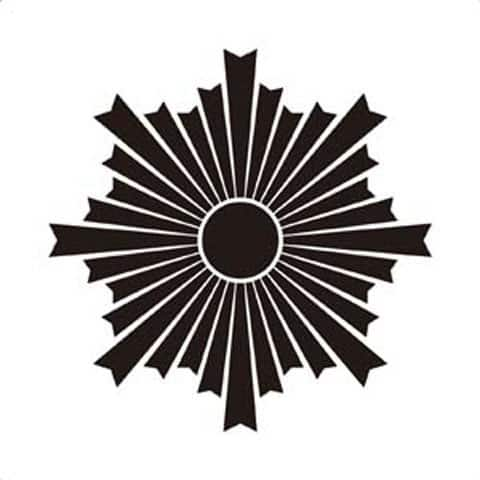【旭光】(きょっこう)
1950年代、航空自衛隊創設当時に主力戦闘機として導入されたF-86F「セイバー」の非公式愛称。
当時の防衛庁により命名されたものであるが、実際にはこの名で呼ばれることはほとんどなく、現場の隊員やファンからは「ハチロク」と呼ばれることが多かった。
なお、同じF-86でも迎撃戦闘機として導入されたD型には「月光」という別の愛称があった。
関連:栄光 月光
旭日章 (警察章)
(旭光 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/04/24 01:01 UTC 版)

旭日章(きょくじつしょう)は、昇る朝日と陽射しをかたどった紋章[1]。日本の警察のほか、多くの日本の国家機関の徽章として用いられる。日章、朝日影ともいう。家紋とする場合には旭光とも呼ばれている。
歴史
日本において、もともとは明治時代初めに陸軍の帽章として用いられた。のちに陸軍は五芒星を用い、旭日章は将校准士官の正装の帽章とされた。
警察の徽章としては、明治8年(1875年)に「円形万筋彫込(えんけいまんすじほりこみ)」と呼ばれる意匠が採用され[2]、明治15年(1882年)には「日章」(陸軍憲兵の徽章と同じく六角形)が採用され、「朝日影」は「日章」の通称として使用されていた。この六角形の「日章」は、第二次世界大戦後に廃止され、昭和23年(1948年)に現在の五角形の「日章」が正章として採用された。警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)等の法令には、「日章」と規定される[3]。「東天に昇る、かげりのない、朝日の清らかな光」を意味するという。
種類
旭日章の光条外周は、警察、国会の衛視、刑務官などは五角形、旧陸軍の憲兵は六角形、旧郵政監察官は十角形など、機関により様々な形がある。ただ、警察では五角形のものを「略章」、八角形のものを「正章」としており[4]、皇宮警察、警視庁、千葉県警察等には礼服用として八角形の帽章を付けた制帽があるほか、警察署長から授与される感謝状にも都道府県警察によっては八角形の旭日章が描かれていることも多い。また、同じ機関でも部署等により異なる意匠を用いることや[注釈 1]、日章の中に文字を入れて区別するもの(入国警備官の「IA」、労働基準監督官の「労」、麻薬取締官、麻薬取締員の「麻」、郵政監察官の「Tマーク」と「監」の組み合わせ、警務官の「警」、警備会社など民間の企業や団体が行う防犯活動の「防」など)、旭日章に他のシンボルマークを配した意匠(警察予備隊の帽章は旭日章に鳩、海上保安庁の帽章は船舶用コンパス下に旭光を配したものである[7])もある。
警察の旭日章は五角形であることから、「桜の代紋」との俗称がある。
日本国外では、同様の図案は、アメリカ合衆国・麻薬取締局[注釈 2]のバッジにもある。こちらも陽光になぞらえて「サンバースト(sunburst)」と呼ばれる。
-
八角形の旭日章(警察功労章)。
家紋

旭光(きょっこう)は、家紋の日紋の一種。同じ類の「日足(ひあし)」と同じように、中央の「日(太陽)」とする丸の部分から光条を放射線状に出したものであるが、旭光では、大きな光条との間に小さな光条が入り、また、光条の端部は谷方向へ入り込むようにデザインされている。単に旭光という場合には光条外周が8角のものをいう[8]。
脚注
注釈
- ^ また目白警察署の署紋章(正面玄関に掲げられている)のみ、警視庁管内で唯一、旭日章を桜葉が囲んだ図柄になっている。目白警察署の前身は、巣鴨警察署から1923年に分かれた高田分署であり、1925年に高田警察署に昇格。1927年に庁舎の新築が行われた。その際、高田警察署は学習院大学警備を担当していたが、同学は皇族が通うことから、近衛師団により、同師団の帽章(五芒星の周囲を桜葉で囲んだもの)を同署の紋章として使用することを特別に許可され、庁舎入口に近衛師団紋章が掲出されることとなったと言われる。そして1933年に目白署に改称したあともそのままこの紋章が使われ続けていると伝えられている[5][6]。
- ^ 厳密には日章とマルタ十字の組み合わせである。
出典
- ^ 熊本県警察本部 [@yuppi_kk] (2014年2月4日). "警察のマーク~旭日章". X(旧Twitter)より2023年3月20日閲覧。
- ^ こどもけいさつ図鑑(兵庫県警察)
- ^ 国家公安委員会 (2022年3月15日). “警察官の服制に関する規則(昭和三十一年国家公安委員会規則第四号)”. e-Gov法令検索. デジタル庁. 2023年3月20日閲覧。
- ^ 熊本県警察本部 [@yuppi_kk] (2014年4月30日). "旭日章 正章と略章". X(旧Twitter)より2023年3月20日閲覧。
- ^ 警視庁 目白警察署の概要[リンク切れ]
- ^ 東京新聞 オンリーワン 目白署、なぜ? 玄関に桜の葉つき銀色紋章 2022年1月31日閲覧.
- ^ 海上保安庁職員服制(昭和37年運輸省令第31号)
- ^ 新人物往来社編『索引で自由に探せる 家紋大図鑑』、新人物往来社 1999年
関連項目
旭光(きょっこう)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/08 07:50 UTC 版)
「国光 (リンゴ)」の記事における「旭光(きょっこう)」の解説
1931年(昭和6年)青森県りんご試験場で国光と旭を交配し、1938年(昭和13年)初結実、1948年(昭和23年)に命名した品種。果実は円錐形を呈し、大きさは平均で170グラムを測る。果梗はやや長めで太く、果皮は滑らかで蝋質を呈する。果肉は緻密で柔らかく、果汁が多くて甘みは中程度、芳香がある。収穫は9月上旬頃である。
※この「旭光(きょっこう)」の解説は、「国光 (リンゴ)」の解説の一部です。
「旭光(きょっこう)」を含む「国光 (リンゴ)」の記事については、「国光 (リンゴ)」の概要を参照ください。
旭光と同じ種類の言葉
- >> 「旭光」を含む用語の索引
- 旭光のページへのリンク