どうみゃくかんかいぞん‐しょう〔ドウミヤククワンカイゾンシヤウ〕【動脈管開存症】
読み方:どうみゃくかんかいぞんしょう
胎児期に特有の血管である動脈管が、出生後も開いたまま残ってしまう状態。動脈管は胎児の肺動脈と大動脈をつなぐ血管で、胎盤を通して母体から酸素や栄養を受け取る胎児期の血液循環に重要な役割を果たすが、出生後、肺呼吸の開始とともに自然に閉鎖して結合組織性の索となる。この動脈管が出生後も開存し続けると、通常なら左心室から大動脈を経て全身に送り出される血液が、肺静脈に流れ込み、肺の血流量が増加し、肺や心臓に大きな負担がかかる。さらに、肺の血管抵抗が上昇し、肺高血圧症を起こすと、肺動脈を流れる静脈血が大動脈に流入し、低酸素血症を生じる。乳幼児期に発症すると鬱血性心不全・発育不全、成人では感染性心内膜炎を起こしやすい。ボタロー管開存症。
動脈管開存症
| 動脈管とは,赤ちゃんがお母さんのお腹の中にいる時に,肺動脈から大動脈への抜け道になっている血管のことをいいます.赤ちゃんが生まれてから肺で呼吸をしはじめると,この抜け道は必要がなくなり,生後2〜3週までに完全に閉じてしまいます.この動脈管が自然に閉じずに残っているものを動脈管開存症といいます(図).この病気はもっとも多い先天性心疾患のひとつで,全体の5〜10%を占めています.動脈管開存症では,全身に流れるべき血液の一部が大動脈から肺動脈へ流れるために,肺や心臓(左心房・左心室)に負担がかかります.動脈管が太く開いているほど流れる血液の量が多くなり,その負担は大きくなります. |
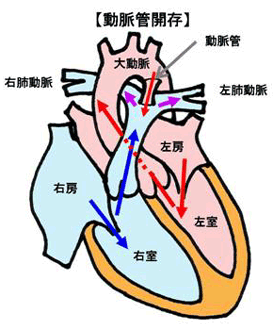
|
|
症状
非常に小さい体重で生まれた赤ちゃんにとって,大きな動脈管は肺や心臓に大きな負担となり,“呼吸が荒く回数が多い”,“ミルクの飲みがわるい”,“ミルクを飲むが体重が増えない”,“汗をたくさんかく”,“機嫌が悪く元気がない”などの心不全症状がみられる場合には,早期に治療を必要とする場合があります.ふつうの体重で生まれた赤ちゃんでも,動脈管が太く,肺や心臓に大きな負担をかけて心不全症状がみられる場合にも早期の治療が必要となります.しかし何の症状もなく過ごし,たまたま健診などで心雑音に気付かれ,検査によって見つかる場合もあります.
診断
治療
|
動脈管開存症
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/07 02:13 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動| 動脈管開存症 | |
|---|---|

動脈管開存症のシェーマ。
|
|
| 分類および外部参照情報 | |
| 診療科・ 学術分野 |
循環器学, 小児科学 |
| ICD-10 | Q25.0 |
| Patient UK | 動脈管開存症 |
| MeSH | D004374 |
動脈管開存症(どうみゃくかんかいぞんしょう、英: patent ductus arteriosus; PDA)とは、胎生の哺乳類で、出生後動脈管が閉鎖しなかった結果として生じる先天性心疾患。初期には大動脈から肺動脈への血液の流入(左→右短絡)により肺の血液量が増加し、左心系鬱血性心不全を示すが、病気の進行により肺動脈圧が大動脈圧を超えると肺動脈から大動脈への血液の流入(右→左短絡)が生じ、静脈血が全身に循環することにより低酸素血症を示す(アイゼンメンガー症候群)。動脈管開存症では通常の血流量より多くの血液が流れるため、肺動脈や肺静脈の血管径は拡張する。
原因
動脈管が出生後も開存し続けて、大動脈→肺動脈への短絡(シャント)経路として機能することにより症状を示す。
症状
通常、左心系鬱血性心不全の発症が見られるまで現れない。肺と左心系への容量負荷が高まると運動不耐性や頻呼吸、咳が認められる。特有の連続性雑音が聴取される。また、大腿動脈ではバウンディングパルスが触知される。
こうした血液のシャントによる症例は動脈管が細いとほとんど無症状の場合もあるが、感染性動脈内膜炎を起こしやすい危険性は細くても変わらない[1]。
診断
超音波診断では短絡血流が認められることで診断される。 心電図ではⅡ誘導とaVF誘導においてR波の増高が認められる。 胸部X線撮影では左心房の拡大、肺血管の拡張、左心室の拡大が認められる。
予防
早産児に対するインドメタシンやイブプロフェンの予防投与が検討されている[2][3]。
治療
インドメタシンやイブプロフェンなどのNSAIDsを投与して動脈管を閉鎖させることができる。 薬物治療に反応しない場合も、動脈管の切断あるいは結紮などの外科手術(結紮、コイル塞栓術)が可能である。 動脈管は心臓外の血管であり、手術の際に心臓を止めて人工心肺装置を稼働する必要はない。
他の先天性心疾患を合併し、左室から大動脈への血流が少なく動脈管が代理を果たしている場合[注釈 1]や、肺への血流不足で動脈管によって肺循環が支えられている場合[注釈 2]などでは、そのままの血行動態で動脈管が閉鎖すると致死的になりうるため、逆にふさがらないようにプロスタグランジンE1を持続点滴静注させるなどして動脈管を開存させる。またアイゼンメンゲル症候群を起こし右→左短絡が起きている場合も手術は厳禁[4][5]。
歴史
1938年、ロバート・エドワード・グロスは動脈管開存症に対する動脈管結紮術を初めて成功させた[6]。
関連項目
脚注
注釈
出典
- ^ 『STAP内科5 循環器(第3版)』梅村敏・木村一雄 監修、初版1999年・第3版2015年、ISBN 978-4907921026、P.153-154。
- ^ Fowlie, PW; Davis PG; McGuire W (19 May 2010). “Prophylactic intravenous indomethacin for preventing mortality and morbidity in preterm infants (Review)”. The Cochrane Database of Systematic Reviews (7): CD000174. doi:10.1002/14651858.CD000174.pub2. PMC 7045285. PMID 20614421.
- ^ Ohlsson, A; Shah, SS (27 January 2020). “Ibuprofen for the prevention of patent ductus arteriosus in preterm and/or low birth weight infants.”. The Cochrane Database of Systematic Reviews 1: CD004213. doi:10.1002/14651858.CD004213.pub5. PMC 6984616. PMID 31985838.
- ^ a b 『看護のための最新医学講座 3循環器疾患 第2版』中山書店、2005年、243頁。 ISBN 4-521-62401-4。
- ^ a b 『STAP内科5 循環器(第3版)』海馬書房、2015年。 ISBN 978-4907921026。
- ^ “Robert Edward Gross (PDF)”. Harvard University. 2021年9月2日閲覧。
参考文献
- 獣医学大辞典編集委員会編集『明解獣医学辞典』チクサン出版 1991年 ISBN 4885006104
- 日本獣医内科学アカデミー編『獣医内科学(小動物編)』文永堂出版 2005年 ISBN 4830032006
- 永井良三 編『看護のための最新医学講座 3循環器疾患 第2版』株式会社中山書店、2005年、ISBN 4-521-62401-4
- 梅村敏・木村一雄 監『STAP内科5 循環器(第3版)』、初版1999年・第3版2015年、ISBN 978-4907921026
外部リンク
- 動脈管開存症 - 日本小児外科学会
「動脈管開存症」の例文・使い方・用例・文例
- 動脈管開存症
固有名詞の分類
- 動脈管開存症のページへのリンク










