空冷
エンジンの熱を空気中に放出する冷却方式。冷却方式とはいうものの、基本的にはエンジンを冷やす特別な装置は何もついていない。走行風を利用するだけというシンプルな構造だ。 エンジンにはフィンと呼ばれる薄い板状のヒダがついていて、少しでも多くの熱を放出するように表面積をふやす工夫がなされている。シンプルな構造で軽くしやすい反面、水冷や油冷に比べ冷却効果は低い。そのため、ハイパワーなかわりに発熱量も多い大排気量モデルにはオイルクーラーなどの補助的な冷却装置が取り付けられることが多い。昔は空冷しかなかった。 現行の国産最大排気量空冷モデルはヤマハのXJR1300。1300ccともなるとフィンだけでは冷やしきれないので、やはりオイルクーラーが付いている。空冷はフィンの美しさが最大の魅力である。
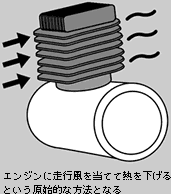
【関連用語】オイルクーラー ラジエター
空冷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/20 15:51 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2019年7月)
|

空冷(くうれい、英語:air cooling)とは、機械装置などにおける冷却法の一つであり、空気との熱交換により放熱する方法である。
概要
空冷においては、周囲の空気を冷媒とするため、冷媒を別途準備する必要がなく、液冷と比較すると構造が簡単であるというメリットがある反面、単位面積あたりの熱の移動量が液体に比べ少ないことから、多数枚のフィンなどを備え、表面積を大きくするための構造を採用するものが多く見られる。空冷は、気温の上昇によって効率が低下する。液冷システムも、その多くは、温まった冷却液を、熱源から離れた場所まで移動させて空冷で冷やすという形で空冷を併用している。
空冷には、熱せられた空気が上昇気流となることを利用するなどして空気の入れ替えを行う「自然空冷方式」と、ファン等により積極的に(強制的に)通風させる「強制空冷式」、などといった分類がある。
応用例
家庭用機器では、オートバイやラジコン、汎用機械などの発動機(四輪自動車用としてはポルシェ、フォルクスワーゲン、スバル360、マツダ・R360クーペ、トヨタ・パブリカなど一部車種に採用されたのみ)、パソコンのCPUの冷却装置、エアコンの室外機などが空冷である。業務用では一部航空機用のレシプロエンジンや、更に大規模なものでは内陸部に建設された原子力発電所の原子炉や冷却塔などといった施設が空冷を採用しているケースもある。
関連項目
空冷
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 08:28 UTC 版)
「オートバイ用エンジン」の記事における「空冷」の解説
詳細は「空冷エンジン」を参照 空冷エンジンは最も初期のオートバイから採用され続けている。シリンダー外部には表面積を大きくして外気への熱の放出を多くするために冷却フィンが設けられていて、独特の外観を持っている。より効率の良い冷却のために設計者は様々な形状の冷却フィンを考案し新型エンジンに採用した。エンジンが露出しているオートバイでは車体デザインの一部として扱われることも多く、水冷エンジンにも空冷の冷却フィンを模した外観のシリンダーブロックがデザインされる例も少なくない。スクーターの場合は走行風を受けにくい車体後方にエンジンが搭載されていることから、クランクの回転を動力とする強制空冷用のファンが設けられているものが多い。 空冷エンジンは水冷エンジンに比べ、部品の温度変化が大きくなりやすいため部品同士の間クリアランスは総じて広めに取られる場合が多く、加えて、ウォータジャケットのようにシリンダー周囲に音を抑えられる構造を持たないことから、エンジンの動作音が大きくなりがちになる。 一方、構造の単純さと製造コストの安さから途上国向けのオートバイでは未だに幅広い製品に用いられ続けている。あるいは、冷却フィンの造形や、エンジンを停止した後に金属部材が冷めていく際に響く音など、空冷エンジン特有の嗜好性には根強い愛好者も多く、空冷エンジンを搭載した新型車種もしばしばみられる。
※この「空冷」の解説は、「オートバイ用エンジン」の解説の一部です。
「空冷」を含む「オートバイ用エンジン」の記事については、「オートバイ用エンジン」の概要を参照ください。
「空冷」の例文・使い方・用例・文例
空冷と同じ種類の言葉
- >> 「空冷」を含む用語の索引
- 空冷のページへのリンク




