熱伝導性
熱伝導性
| thermal conductivity | ||
ふく(輻)射や対流によらないで、熱が物質内を伝わる性質。
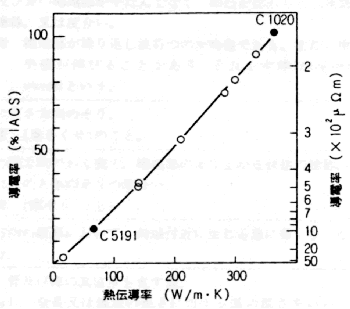
|
熱伝導
(熱伝導性 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/19 03:20 UTC 版)
熱伝導(ねつでんどう、英語: thermal conduction)は、固体または静止している流体の内部において高温側から低温側へ熱が伝わる伝熱現象[1]。
熱力学第二法則により熱は必ず高温側から低温側に向かう[1]。
概要
金属においては、
の2つの機構があるものと考えられており、電気の良導体は熱の良導体でもある(ヴィーデマン=フランツ則)。
通常の物質では伝導電子による寄与の方が大きいので、金属は半導体や絶縁体(フォノンが主要な熱伝導の担い手)よりも熱伝導性が良い。しかし、非常に硬いダイヤモンドではフォノンを介した熱伝導性の寄与の方が非常に大きくなる。
固体金属以外では、熱伝導性はその他の固体、液体、気体の順に悪くなる[2]。非鉄素材のゴムや樹脂の熱伝導性は悪いが、酸化アルミニウムなどを熱伝導性の良い金属素材を添加することで向上させることもできる[3]。
なお、固体と運動している流体の間の伝熱現象は熱伝達(convective heat transfer)という[4]。
熱の移動と物質移動(拡散)や電気伝導にはアナロジーが成り立つために化学工学では、伝熱や物質移動を扱う分野を移動現象論と呼んで、類似の取り扱いをする。
フーリエの法則
単位時間に単位面積を流れる熱流(熱流束密度)を J [W/m2] とし、温度を T とすると、分子論的熱緩和時間より十分長い時間(定常状態と見なせる時間)領域での現象に対して、熱流束密度 J は温度勾配 grad T に比例する。すなわち
熱伝導性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/24 07:14 UTC 版)
「ダイヤモンドの物質特性」の記事における「熱伝導性」の解説
大抵の電気絶縁体と異なり、ダイヤモンドは結晶内の共有結合が強固なため、優れた熱伝導体となる。天然の青色ダイヤモンドのほとんどは、炭素原子から置換されたホウ素を含み、それが高い熱伝導性を有する原因となる。天然ダイヤモンドの熱伝導率は約22 W/(cm・K) である。質量数12の炭素原子(12C) 99.9%で構成された単結晶合成ダイヤモンドは、室温における熱伝導率は33.2 W/(cm・K) と全ての固体物質中最も大きく、銅のそれの5倍である。そのため高い熱伝導率をもつダイヤモンドは、半導体製造中に起こるオーバーヒートからシリコンやその他半導体に不可欠な材料を保護する目的で利用されている。フェルミ電子がデバイ温度付近で通常のフォノン性移動モードを振る舞う際に、低温時の熱伝導性はさらに良くなるとされ、12C原子で多く占めるダイヤモンドの熱伝導率は104Kで410 W/(cm・K) までに達する。 宝石職人や宝石学者はダイヤモンドの高い熱伝導性を応用した熱電極プローブを利用して、ダイヤモンドとそのイミテーションを判別している。1組2本のプローブの先端には高純度の銅が取り付けられ、電池式のサーミスタとして成立する。一方のプローブは熱を発生させ、それを他方のプローブが温度を測定している。もし検査対象がダイヤモンドなら、プローブから発せられた熱エネルギーが、もう一つのプローブで温度変化を瞬時に観測でき、時間にしてわずか2、3秒しか要しない。しかし、1998年にダイヤモンドの熱伝導率に近い炭化ケイ素の熱電極プローブが導入され、将来ダイヤモンドと代替する物質として注目されている。
※この「熱伝導性」の解説は、「ダイヤモンドの物質特性」の解説の一部です。
「熱伝導性」を含む「ダイヤモンドの物質特性」の記事については、「ダイヤモンドの物質特性」の概要を参照ください。
- 熱伝導性のページへのリンク
