あやめ
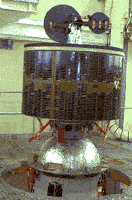
名称:実験用静止通信衛星「あやめ」/Experimental Communications Satellite(ECS)
小分類:通信放送衛星
開発機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
運用機関・会社:宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げ年月日:1979年2月6日
運用停止年月日:1979年2月9日
打ち上げ国名・機関:日本/宇宙開発事業団(現 宇宙航空研究開発機構(JAXA))
打ち上げロケット:Nロケット5号機(F)(N-Iロケット)
打ち上げ場所:種子島宇宙センター(TNSC)
国際標識番号:1983058A
実験用静止通信衛星「あやめ」は、通信衛星の打上げ技術の確立、ミリ波による通信実験などを目的として打上げられましたが、故障によってミッションを達成することはできませんでした。
「あやめ」は、スピン安定方式で姿勢を制御し、設計寿命は1年でした。
1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?
直径約141cm、高さ約95cmの大きさで円筒形をしています。重量は約130kgです。
各1チャンネルの準ミリ波(35/31ギガヘルツ・予備なし)通信中継器とマイクロ波(6/4ギガヘルツ・予備なし)通信中継器を搭載しています。
2.どんな目的に使用されるの?
「あやめ」は、ミリ波の周波数帯による、通信実験および電波伝播特性の調査と、静止衛星の打上げ技術・追跡管制技術・姿勢制御技術の確立を目的に開発されました。
3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?
予定のトランスファ軌道に投入されましたが、2月9日のアポジモーター点火後に電波が途絶しました。衛星分離後の第3段ロケットが衛星に接触して種々の異常が発生し、電波が途絶したと考えられています。
4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?
「あやめ2号」(ECS-b)があります。
5.どのように地球を回るの?
高度約3万6,000km、傾斜角0度、周期約24時間、東経145度の静止衛星軌道の予定でした。
※参考文献:大林辰蔵・監修「日本の宇宙科学1952→2001」(東京書籍)、斎藤成文・著「日本宇宙開発物語」(三田出版会)
ECS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/15 07:51 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動ECS
ECS
- ECS(Electrical cell stimulation)- 高周波電流で細胞に刺激を与えて代謝増進効果を得ること。高周波による細胞刺激。100Khz~10Mhzの高周波電流は細胞の原形質膜を透過し細胞のイオンフローなどに影響を与えATPをの生成を増進する。
- Emergency Coma Scale - 意識障害のレベルを表す指標
- エリートグループコンピューター・システムズ (Elitegroup Computer Systems) - 台湾のマザーボードメーカー
- エコノミークラス症候群 (economy class syndrome)
- 東シナ海 (East China Sea)
- エクアドル・スクレ (Ecuadorian sucre) - エクアドルの1884–2000年の通貨
- エンティティ・コンポーネント・システム (Entity_component_system)
- 環境制御システム(Environmental Control System)
ECs
- 欧州諸共同体 (European Communities) - EUの原形となった諸同盟
eCS
- eComStation - オペレーティングシステム
ECS
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/12 06:34 UTC 版)
「電気二重層コンデンサ」の記事における「ECS」の解説
ECS(Energy capacitor system)と呼ばれる大型の電気二重層キャパシタと電子回路を組み合わせることで動力源として利用できる装置が開発されている。
※この「ECS」の解説は、「電気二重層コンデンサ」の解説の一部です。
「ECS」を含む「電気二重層コンデンサ」の記事については、「電気二重層コンデンサ」の概要を参照ください。
- ECSのページへのリンク

