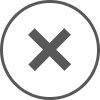冬の日 (小説)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/25 01:47 UTC 版)
作品背景
※梶井基次郎の作品や随筆・書簡内からの文章の引用は〈 〉にしています(論者や評者の論文からの引用部との区別のため)。
結核の進行・血痰
1924年(大正13年)に東京帝国大学文学部に入学し、翌1925年(大正14年)1月に同人誌『青空』を創刊した梶井基次郎は、三高時代のような狂的な泥酔や放蕩は治まったものの、神経衰弱のような気分になることがあり、銀座の高級レストラン「カフェー・ライオン」でビフテキなどのご馳走を食べ、贅沢な一流品を買っても満たされないものがあった[15][16]。
1926年(大正15年)1月あたりから持病の結核がまた悪化し、春頃から再び泥酔して暴れる行状が出てくるようになった[15]。夏の猛暑の中、『青空』の広告取りなどの無理がたたって病状が進み、9月下旬頃から血痰が長く続くようになった[15][17][18]。基次郎は、麻布の医者から「右肺尖に水泡音(ラッセル)、左右肺尖に病竈あり」と診断されていた[15][18]。
その後も体調は悪化し、11月に入ると6週間も血痰が続いた[17]。ちょうどその頃病気だった飯島正の見舞いに行った際、たまたまそこに居合わせた医者に自分も診てもらった基次郎は、麻布の医者と同様の診断を受けて転地療養や食事療法を勧められていたが[15][17][19]、年末には、東京帝国大学の卒業論文を出さなければならなかった[15][19]。
基次郎が当時住んでいた東京市麻布区飯倉片町32番地(現・港区麻布台3丁目4番21号)の下宿の隣部屋に10月から三好達治が同居しはじめていた[20]。ある晩基次郎は「葡萄酒を見せてやらうか…美しいだらう…」と襖越しに三好に声をかけ、ガラスのコップを電灯にかざし透かして見せた[19][20]。その美しい赤々としたものは、基次郎の血痰であった[19][20]。
三好は基次郎の病状がかなり悪いことに気づいていた[21]。そのため基次郎に、大学卒業をあきらめ転地療養を実行し、文筆で生計を立てることを強く勧めるが、学費を苦労して捻出している親のためにも卒業したかった基次郎は、まだ身体はなんとかなると考え、卒論提出を来年に延ばすつもりだった[15][17][19][20][21]。しかし留年するなら学費は自分で稼ぐように母から通告されていた[15][17][19]。
基次郎は、翻訳の仕事や少女小説を書くか、あるいは英語教師になるかして自活しようか考えるが、病状のことを思うと不安と憂鬱な気分に苛まれた[5][15][22]。この頃に『冬の日』の執筆に一度取りかかっていたが一旦中断したままとなった[19]。三好の説得を聞き入れて転地療養を決めた基次郎は、大晦日に伊豆の湯ヶ島に向け、〈亡命といふやうな感じ〉の気持で東京を発つことになった[5][15][21][23](その後の詳細は梶井基次郎#伊豆湯ヶ島へ――『青空』廃刊を参照)。
湯ヶ島の旅館で孤独な正月を迎え、元日の夜にひどく体調を悪くした基次郎は、〈苦しかつたときには子供のやうにさみしかつた〉思いを痛感し[24]、5日から改めて本格的に〈悲しい小説〉の『冬の日』の執筆に取り組み始めた[1][25]。
松尾芭蕉の影響
湯ヶ島へ発つ前の1926年(大正15年)の冬、基次郎は下宿に同居していた三好達治と共に、松尾芭蕉を研究していた。2人は注釈書を参考に芭蕉の『冬の日』抄、『曠野』抄を毎晩のように耽読していた[3][15][19]。この時期、基次郎は以下のような俳句を詠んだ[15][19][26]。
- 凩やいづこガラスの割るゝ音
それ以前の三高時代から、松尾芭蕉の紀行文は基次郎にとって座右の書であり[3][27]、大学入学後の1926年(大正15年)9月中旬にも、友人の近藤直人と比叡山や琵琶湖に行って、芭蕉の『奥の細道』について語り合っていた[15][28][29]。
基次郎は翌1927年(昭和2年)2月に『冬の日』の前篇を発表した後、友人・近藤直人への書簡で、〈私の云つてゐました象徴主義なるもの甚だ遅々ながら文中に発展してゐることを認めていただければ幸甚です〉と述べつつ、『青空』同人に新加入した北川冬彦と三好達治の詩を推奨し[30]、『青空』同人の古いグループについては、〈今アナーキストかポルシェビストか、そんな岐路に立つてゐるやうに思はれます〉として、自分の目標を、〈資本主義的芸術の先端リヤリスチック シンボリズムの刃渡りをやります〉と語っていた[30]。
そしてその後段で、松尾芭蕉の梅の句を引き、〈此度の冬の日の続きは冬が去つて春が来ようとし梅の花の匂のやうなものが街上で主人公をつかまへるところを書かうと思つてゐます〉と『冬の日』後篇の構想に触れて(実際には暗いトーンのまま終わっている)[30]、芭蕉と並んで向井去来の梅の句も挙げながら、〈ナイーヴな、そして下手なユーモアでこれを詠まうとしてゐますが、僕はもう少し烈しくこれを書かうと思つてゐます。少くとも近代的に。どうか待つてゐて下さい〉と告げ、芭蕉や去来の精神の「近代的表現」を目指していたことが看取されている[3][27][30]。
風景描写の特色
『冬の日』の作中で描かれる風景は、おもに当時基次郎が下宿をしていた東京市麻布区飯倉片町(現・港区麻布台3丁目)の町の風景である。ここは1925年(大正14年)5月末から住んでいた地で、部屋からの眺めの見晴らしの良い場所であった[31]。
上記のように風景や事物を叙述する修辞は、冗漫さが避けられ、俳句のように象徴的なまでに吟味されており、散文詩的、詩的な文体となっている[4][20]。また、枯葉が四散する欅の枝の描写というよりも、その向う側を見ようとする主人公の心が主となっており、風景描写と心理描写との境界が明瞭でなく、ある意味一体化しているような表現方法となっているため、その意味でも西欧的な小説とは違って、詩に近い印象となっている[7]。
〈欅が風にかさかさ身を震はすごとに隠れてゐた風景の部分が現はれて来た〉の一節での、多くの枯葉が吹き飛んでいく様が省略され、〈風景の部分が現はれて来た〉に力点がおかれているような描写の方法を、詩人の三好達治は、「修辞の素朴な上に極めて洒落つ気に富んだあたりも最も梶井式な点」だと解説している[20]。
ちなみに、三好によれば、〈冬陽は郵便受のなかへまで射しこむ。路上のどんな小さな石粒も一つ一つ影を持つてゐて、見てゐると、それがみな埃及のピラミッドのやうな巨大な悲しみを浮べてゐる〉という一節の中のピラミッドの比喩は、三好の言からヒントを得た「入れ智恵」だという[20]。
挿話の題材・異動
『冬の日』は多くの実体験に基づいているが、その種々の体験を複合し、虚実織り交ぜながら作品世界を形づくっていることが窺える[7][15]。また草稿で書かれている挿話などが、完成稿では削られたものもあり、説明の言葉を熟考し切りつめている様子が看取される[1][4][10][20][32][33]。
折田が堯の普段使用している茶碗で茶を飲み、その平然さに堯の意識が向く場面の題材に関しては、その当時、基次郎の下宿で5日間ほど過ごした後輩の北神正が、一つしかない基次郎のコーヒー茶碗を平気で使っていたことが実際にあった[15]。年下の北神がそれでコーヒーを飲んでいると、「おいお前、そないしたらあかんで」と基次郎は落ち着いて言ったとされる[15]。その時に北神は基次郎から、萩焼の徳利と猪口をもらった[15]。
それに類する題材として、『青空』同人たちが誰かの下宿に集合し、コーヒーを入れた時に茶碗が足りないと、基次郎は自分が飲み終わった茶碗を簡単に拭いただけで、差し出したこともあった[15]。それは基次郎が無神経でやっているのではなく、病気に抵抗しているんだと忽那吉之助は感じた[15]。
折田が堯に、大学の焼けた煉瓦塀を壊す作業員の見事さを話して聞かせる場面があるが、この題材は実際に関東大震災の被災によって東京帝国大学の講堂の煉瓦塀が焼け、それを足場も組まず塀の上に乗りながらツルハシで取り壊す作業員の職人芸が学生の間で話題となり、多くの見物人が集まった話による[7][10]。この壮観な作業の面白さを三好達治が基次郎に伝え、実際に基次郎は中谷孝雄を誘って見物に行った[10]。この職人の取り壊しのことは、当時仏文科にいた中島健蔵も回想録で綴っている[7]。
堯が質屋から冬外套を取り出しに行く場面で、〈それと一緒に処分されたもの〉とだけ書かれているものは、草稿では、永年かかって収集した〈楽譜〉が流れたことが記されている[10][32][33]。基次郎はクラシックやオペラ好きで譜面が読め、多くの楽譜を持っていた[34][35]。
草稿では、血痰の匂いが染みついているような気がした堯が、部屋に香水をまき、〈正月の客〉がその香水の匂いに言及するくだりがある[1][33]。また、母の恩師の子息で顔なじみの医師・津枝が堯の下宿に実際に登場する場面が草稿にはある[8][33]。
永遠の未完作
1927年(昭和2年)4月の『青空』26号に発表された後篇の末尾には、「未完」と記されており、基次郎はこの続きを書くつもりであった[1][8]。
同年2月の『青空』24号に前篇を発表し終えた時点の構想では、後篇は陰鬱な冬から、やがて梅の咲く春の気配が主人公に訪れる終り方であったが、実際はますます暗い心象のままの冬の結末となった[8][36]。
後篇の草稿は2月中から書き始められ、3月の4、5日頃から15日までに『青空』に載せる原稿として19枚ほどを書き終わるが、作品としての完成には至らなかった[8][32][33][37]。
基次郎は後篇を発表した後も、その続きを書こうと思いつつ、書けば暗いものにならざるをえないことを自覚し、〈あの続きは最も憂鬱なるもので書く元気がまだ出ない〉と淀野隆三に告げていたが[8][38]、その後には、その暗さを肯定的に捉え、続篇への意欲を見せてもいた[39]。
一年経つても依然希望は新しくならない。変転の多かるべき二十七歳頃の身体を病気とは云ひながらなにもせず湯ヶ島へ埋めてしまつたのはわれながら腑甲斐なく思ふ 心に生じた徴候は生きるよりも寧ろ死へ突入しようとする傾向だ(しかしこれは現実的にといふよりも観念的であるから現実的な心配はいらない) 僕の観念は愛を拒否しはじめ社会共存から脱しようとし、日光より闇を嬉ばうとしてゐる。
僕は此頃になつて「冬の日」の完結が書けるやうになつたことを感じてゐる 然しこんなことは人性の本然に反した矛盾で、対症療法的で、ある特殊な心の状態にしか価値を持たぬことだ 然し僕はそういつた思考を続け作を書くことを続ける決心をしてゐる。 — 梶井基次郎「北川冬彦宛ての書簡」(昭和2年12月14日付)[39]
なお草稿には、完成稿では登場しなかった医師・津枝が堯の下宿を訪ねる場面があり、津枝との会話で、〈死んだ延子が堯と一緒に東京にゐるやうに思へてならない〉という母の心情を知った堯が、はっとして陰鬱になるくだりがある[8][33]。その挿話は堯の死を暗示させるようなものとなっているため[8][33]、基次郎が自身の死を描くところまで考えていたと見られている[8][40]。
丸山薫によると、基次郎が『冬の日』の結末について、「堯の死ぬところはどうしても書けない、書けば自分も死ぬやうな気がする」という言葉を三好達治に語った後に、郷里の大阪に帰っていったという[8][40]。
注釈
出典
- ^ a b c d e f g h 「第三部 第一章 『冬の日』」(柏倉 2010, pp. 237–244)
- ^ a b c d e f 「第九章 白日の闇――湯ヶ島その一」(大谷 2002, pp. 196–215)
- ^ a b c d e f g h i j 遠藤誠 1978
- ^ a b c d 黒田 1975
- ^ a b c d 「湯ヶ島の日々」(アルバム梶井 1985, pp. 65–83)
- ^ a b 淀野隆三「解説」(新潮文庫 2003, pp. 325–349)
- ^ a b c d e f g h i j k l m 「第三部 第二章 『冬の日』の評価」(柏倉 2010, pp. 245–254)
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o 「第三部 第三章 闇と光」(柏倉 2010, pp. 255–264)
- ^ a b c d e f g 遠藤祐 1956
- ^ a b c d e 浅見淵・中谷孝雄・外村繁・北川冬彦・三好達治・淀野隆三「座談会 梶井基次郎の思い出」(『決定版 梶井基次郎全集』月報[檸檬通信(1)(2)]筑摩書房、1959年2月・5月・7月)。別巻 2000, pp. 350–367に所収
- ^ a b 鈴木貞美「梶井基次郎年譜」(別巻 2000, pp. 454–503)
- ^ 藤本寿彦「書誌」(別巻 2000, pp. 516–552)
- ^ a b ウィリアム・J・タイラー編「外国語翻訳及び研究」(別巻 2000, pp. 640–642)
- ^ Dodd 2014
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s 「第八章 冬至の落日――飯倉片町にて」(大谷 2002, pp. 162–195)
- ^ 「日記 草稿――第六帖」(大正14年)。旧2巻 1966, pp. 269–307に所収
- ^ a b c d e f 「近藤直人宛て」(昭和2年1月2日付)。新3巻 2000, pp. 161–163に所収
- ^ a b 「第二部 第六章 『新潮』への誘い」(柏倉 2010, pp. 190–199)
- ^ a b c d e f g h i 「第二部 第八章 大正末」(柏倉 2010, pp. 215–236)
- ^ a b c d e f g h i j k l m 三好達治「梶井基次郎」(文藝 1950年2月号-3月号)。別巻 2000, pp. 182–197に所収
- ^ a b c 三好達治「梶井基次郎君の憶出」(文藝春秋 1934年3月号)。別巻 2000, pp. 83–85に所収
- ^ 「畠田敏夫宛て」(昭和2年2月5日付)。新3巻 2000, pp. 194–196に所収
- ^ 「北神正宛て」(昭和2年2月3日付)。新3巻 2000, pp. 188–190に所収
- ^ 「北川冬彦宛て」(昭和2年1月2日付)。新3巻 2000, p. 160に所収
- ^ 「淀野隆三宛て」(昭和2年1月6日付)。新3巻 2000, pp. 167–169に所収
- ^ 「北川冬彦宛て」(大正15年11月20日付)。新3巻 2000, pp. 153–154に所収
- ^ a b 中谷孝雄『梶井基次郎』(筑摩書房、1961年6月)。『中谷孝雄全集 第4巻』(講談社、1975年)。遠藤誠 1978, p. 24
- ^ 「近藤直人宛て」(大正14年10月26日付)。新3巻 2000, pp. 128–131に所収
- ^ 「第二部 第二章 行き悩む創作」(柏倉 2010, pp. 123–139)
- ^ a b c d 「近藤直人宛て」(昭和2年2月4日付)。新3巻 2000, pp. 190–194に所収
- ^ 「近藤直人宛て」(大正14年6月1日付)。新3巻 2000, p. 113に所収
- ^ a b c 「日記 草稿――第九帖」(昭和2年)。旧2巻 1966, pp. 366–386に所収
- ^ a b c d e f g 「日記 草稿――第十帖」(昭和2年)。旧2巻 1966, pp. 387–409に所収
- ^ 外村繁「梶井基次郎のこと」(創元 1941年9月号)。別巻 2000, pp. 75–77に所収
- ^ 飯島正「梶井君の思ひ出」(評論 1935年9月号)。別巻 2000, pp. 52–55に所収
- ^ a b c 「近藤直人宛て」(昭和2年3月17日付)。新3巻 2000, pp. 202–203に所収
- ^ a b 「淀野隆三宛て」(昭和2年3月17日付)。新3巻 2000, pp. 201–202に所収
- ^ 「淀野隆三宛て」(昭和2年4月10日付)。新3巻 2000, pp. 207–211に所収
- ^ a b 「北川冬彦宛て」(昭和2年12月14日付)。新3巻 2000, pp. 253–256に所収
- ^ a b 丸山薫「ユーモラスな面影」(作品 1932年5月・追悼特集号)。別巻 2000, pp. 305–307に所収
- ^ a b c 阿部知二「梶井氏の想出など」(作品 1932年5月・追悼特集号)。別巻 2000, pp. 295–297に所収
- ^ a b 武田泰淳「微妙なくりかえし」(『決定版 梶井基次郎全集3巻 書簡・年譜・書誌』月報[檸檬通信(3)]筑摩書房、1959年7月)。別巻 2000, pp. 377–379に所収
- ^ a b 「北川冬彦宛て」(昭和2年2月2日付)。新3巻 2000, pp. 183–185に所収
- ^ 「北川冬彦宛て」(昭和2年3月21日付)。新3巻 2000, pp. 205–207に所収
- ^ 梶井基次郎「詩集『戦争』」(文學 1929年12月号)。旧2巻 1966, pp. 72–77に所収
- ^ 三好行雄「注解――城のある町にて」(新潮文庫 2003, pp. 319–320)
- 冬の日 (小説)のページへのリンク