はま‐や【破魔矢】
破魔矢(はまや)・破魔弓(はまゆみ)について
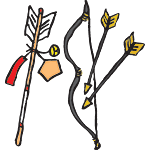 元々は武家の風習で、戦場に赴く前に武運長久を祈願して神社に甲冑・刀・槍・弓矢などを奉納した際、参拝した神社から守護神のご加護の証として模擬の弓矢をいただき、これを戦場での御守護として奉ったことが発祥の由来と言われています。
元々は武家の風習で、戦場に赴く前に武運長久を祈願して神社に甲冑・刀・槍・弓矢などを奉納した際、参拝した神社から守護神のご加護の証として模擬の弓矢をいただき、これを戦場での御守護として奉ったことが発祥の由来と言われています。
江戸時代の後期には一般庶民の間にも広がり、男児の成長を祈願して神社に参拝した際に、破魔矢と破魔弓をセットしたものを授かったとされています。明治以降は、魔を射り破るという意味合いから魔除けの弓矢と言われ、現在では主に初詣に神社へ参拝した際に、「開運厄除・家運隆昌」を祈願して破魔矢を持ち帰り、神棚に立て祀ります。神棚のない家は、玄関の扉の内側上部に取り付けて「厄い封じ」として用いるのも良いとされています。
通常は購入後1年を経過すると効力を失うとされて買い替えるのが一般的ですが、古いものは次年正月の初詣の機会にでも神社に持参して焼却してもらいます。
破魔矢
破魔矢
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/05/29 16:41 UTC 版)
|
|


破魔矢(はまや)とは、正月の縁起物[2]や神具として神社・寺院で授与される矢である。破魔弓(はまゆみ)と呼ばれる弓とセットにすることもある。

このほか、家屋を新築した際の上棟式に呪いとして鬼門に向けて棟の上に弓矢を立てる。新生児の初節句に親戚や知人から破魔矢・破魔弓を贈る習慣もある[要出典]。
正月に行われていた弓の技を試す「射礼」(じゃらい)という行事に使われた弓矢に由来するとされている。元々「ハマ」は競技に用いられる的のことを指す。これを射る矢を「はま矢(浜矢)」、弓を「はま弓(浜弓)」と呼んだ。「はま」が「破魔」に通じるとして、正月に男児のいる家に弓矢を組み合わせた玩具を贈る風習が生まれた。後に、一年の好運を射止める縁起物として初詣で授与されるようになった[要出典]。
破魔矢の概念
 |
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2017年8月)
|

仏教において、青面金剛に従う四夜叉の一人、烏摩勒伽(うまろきゃ)が持つ金の弓矢が破魔矢の発祥であるという伝承があり、烏摩勒伽ら四夜叉を祀る日光の輪王寺では、それにちなんだ龍神破魔矢が販売されている[3]。
日本では古来、呪術をかける事は少ないが、呪術に対する破邪の慣習は多くある。一般に破魔矢の先が鋭く尖っていないのは、目標とする人や物自体ではなく邪魔が発する邪気・邪意・邪道・邪心等の妖気を破り浄化する用を為せばよいので、鋭利な刃物である必要が無い為である。
一般には破魔矢のみがよく流通しているが、正式には、破魔弓で射て初めて邪魔を破り浄化する効力を発揮する。一般人が破魔矢を持つ意味は、破魔弓は神や神主や破邪の能力を有する者が持って方向と力と気を定めて構え、破魔矢の所有者は破りたい魔に対する矢を提示する形で射られる、との仕組から来る。
商標
 |
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2017年8月)
|
小型の弓にお守りなどをつけた神社の縁起物の「破魔矢」は、神奈川県の破魔矢奉製所という会社が商標登録していたが、広く使われるようになったとして、数年前に[いつ?]商標登録の更新をしなかった。このため、以前は「魔除けの矢」などとニュースで表現していたNHKも近年は[いつから?]「破魔矢」という語を使うこともある。
脚注
- ^ 破魔矢建築用語集、タクミホーム
- ^ “正月「破魔矢」作りピーク 名古屋・熱田神宮”. 産経ニュース (2021年12月2日). 2021年12月2日閲覧。
- ^ 日光山輪王寺大猷院・「龍神破魔矢」解説より
関連項目
「破魔矢」の例文・使い方・用例・文例
- 破魔矢の的
破魔矢と同じ種類の言葉
- 破魔矢のページへのリンク



