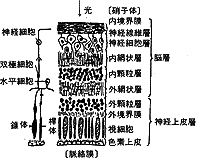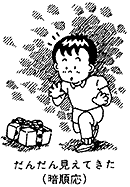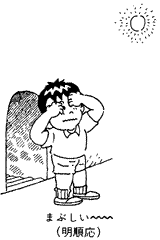網膜
|
|
網膜とはカメラでいえばフィルムにあたりますが,10層からできているとてもうすい膜で,厚さは中央部で0.3mm~0.4mm,周辺では0.15mmです。 視細胞には,桿体と錐体とよばれる二種類の細胞があり,桿体はうす明かりを感じ視力はよくなく,錐体は明るいところではよく感じ,色を見わけ,視力のよい細胞です。 光は視細胞にとどくと電気信号に変えられ,神経線維層を通って神経にいき,この信号が大脳の中枢にいってはじめてものが見えるのです。 また,網膜の後ろの中心には黄斑部があり、その中心に中心窩があります。ここには錐体のみがあり,視力のもっともよいところです。 |
|
|
Q.盲点とは何ですか
視神経が脳へ行くところは、光りを感じる細胞がないので、盲点などといわれている 左目を手でおおい、右目で上の絵のイヌを見つめながら、目をはなしたり近づけたりします。イヌの絵から約20cmのところで、カエルが見えなくなるはずです。 |
人間はだれでも,見ようとする点より耳側に視野の欠けている部分があります。これを盲点(マリオット盲点)といいます。もちろん左目,右目ともにあります。その位置は注視点の耳側約15゜のところに,幅約5゜のややたて長の楕円形として存在します。これは眼底の視神経乳頭にあたる部分です。ここには網膜がなく,視細胞がないので,光があたっても感じないわけです。マリオットとはフランスの物理学者の名前からとったものです。 |
|
|
Q.網膜はどんな色をしていますか |
網膜は眼底鏡(直像鏡,倒像鏡)という器械で見ると簡単に観察できます。しかし,網膜そのものは透明であるため,見えるのは網膜色素上皮と脈絡膜の色素に含まれるメラニン色素,および,脈絡膜血管の血液の色が重なり合って赤かっ色に見えます。白色人種では,メラニン色素が非常に少ないので,脈絡膜がよく見えてあわい紅色でかがやいて見えます。 |
|
|
|
たとえば,明るいところから急に暗いところへ入ると,はじめは何も見えないのにしばらくすると,だんだんと見えてきます。このように暗い中で目がなれてくるのを暗順応,その逆を明順応といいます。これは,網膜にある視細胞の桿体,錐体の働きによって決まります (1)暗順応 一 暗いところでは桿体が中心になって働きます。この桿体は、黄斑部から離れるにしたがって、網膜のまわりに多くなり、視角の20~30°にあたる部分に最も多くあります。また、視力にはあまり関与しません。桿体細胞には,ロドプシンとよばれる物質がふくまれ,光があたるとビタミンAに変わります。暗いところではこれと逆のことが起こります。そのため,ビタミンAが不足すると,暗いところで見えなくなる夜盲症(とり目)になるのです。 (2)明順応 一 明るいところでは錐体が中心になって働きます。この錐体は,網膜の中心部に多く,視力にすぐれています。明順応は暗順応にくらべてはるかに短時間ですみます。暗順応は30分~1時間かかるのに対して,明順応は40秒~1分です。 |
網膜と同じ種類の言葉
- >> 「網膜」を含む用語の索引
- 網膜のページへのリンク
「網膜」の関連用語
| 網膜のお隣キーワード |
網膜のページの著作権
Weblio 辞書
情報提供元は
参加元一覧
にて確認できます。
| Copyright (C) 医療法人社団 医新会 All Right Reserved. |
ビジネス|業界用語|コンピュータ|電車|自動車・バイク|船|工学|建築・不動産|学問
文化|生活|ヘルスケア|趣味|スポーツ|生物|食品|人名|方言|辞書・百科事典
|
ご利用にあたって
|
便利な機能
|
お問合せ・ご要望
|
会社概要
|
ウェブリオのサービス
|
©2025 GRAS Group, Inc.RSS