退官・定年退職
贈答慣習
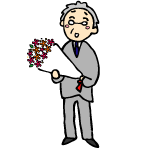 昨今では内輪で祝うことが多いようですが、会社の部課単位で行なう場合は合同で歓送会を催したり、お祝いの金品を贈ったりするのが一般的のようです。
昨今では内輪で祝うことが多いようですが、会社の部課単位で行なう場合は合同で歓送会を催したり、お祝いの金品を贈ったりするのが一般的のようです。
目上の人にお金を贈ることが失礼となる場合がありますので贈答品が最適です。
お祝いを贈る時期
お祝い返しの時期
一般的にはお礼状程度に留めるようですが、気になる先様には一週間以内に贈ります。記念品として贈るのも一興です。
ひとくちMEMO
通常は部課単位や同僚・有志が歓送会などを催したりして、お祝いの贈り物をするのが一般的。
ご贈答のマナー
| 贈答様式 | 贈り元 | 献辞(表書き) | 慶弔用品 |
|---|---|---|---|
| 祝い品を贈る | 身内 身内以外 |
御退官お祝 祝定年御退職 祝御無事退官 ご苦労様 |
【のし紙】花結び祝 |
| 祝い金を贈る | 身内 身内以外 |
【のし袋】花結び祝 【金封】赤白花結び/赤白あわび結び |
|
| 祝い返し | 本人 | 御礼 退官記念 |
【のし紙】花結び祝/赤棒 |
使用例(のし紙/金封/のし袋の様式)
| のし紙/金封/のし袋の様式 | 使い方 |
|---|---|

 |
退官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/10/12 23:37 UTC 版)
退官(たいかん)とは、官職を退くこと。以下に概説する。
退官とは官吏の職にある者が退職すること。おもに上級の国家公務員に用いられることが多い。かつては一般の公務員に対しても用いられる正式な法令上の用語であったが、現行の公務員法制の元では退職、辞職などといい下記の例外を除いて退官とは言わない。
現行法上、「退官」の用語が用いられている法令および該当する公務員は下記のとおり。
- 日本国憲法第79条第5項(最高裁判所裁判官)および同第80条第1項(下級裁判所裁判官)
- 検察庁法第22条(検察官の定年)
- 会計検査院法
- 第4条第3項(国会による任命の事後承認が得られなかった検査官の当然退官)
- 第5条第3項(検査官の定年)
- 第6条(国会の議決による検査官の退官)
- 労働基準法第105条(労働基準監督官の守秘義務)
大学の教員も教官と通称・俗称されるため、国公立大学のみならず私立大学でも(私立大学には「教官」はいない[1]ので、本来ならあり得ない表現方法)教員が退職することをしばしば退官ということがある。 なお、大学の教員は旧制度では教授は高等官と「官僚」であり、新制度では「文部教官」、そして文部省と科学技術庁が統合され、文部科学省となってからは「文部科学教官」が正式な職名であったが、大学法人化以降に この「文部科学教官」という名称はなくなった。現在でも、教官と言えるのは国立の文部科学省以外の省庁が作る学校の教員である。たとえば、防衛大学校の教員の正式名称は教官である。私立学校は本来民間のため、「退職」または「退任」が正しい。
対義語は任官。
関連項目
脚注
- ^ 「私立大学教官」と「大学生徒」1998/11/30 2022年10月閲覧
退官
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/14 00:00 UTC 版)
「サラット・フォンセカ」の記事における「退官」の解説
翌年1月に行われる大統領選挙に出馬するため、同年11月12日に防衛大臣ゴーターバヤ・ラージャパクサを通じて辞任届けを大統領に提出した。彼は月末まで仕事を続けるよう留任されたが結局16日に辞任し、後任には空軍司令官のロシャン・ゴーナティラカが就任した。
※この「退官」の解説は、「サラット・フォンセカ」の解説の一部です。
「退官」を含む「サラット・フォンセカ」の記事については、「サラット・フォンセカ」の概要を参照ください。
「退官」の例文・使い方・用例・文例
退官と同じ種類の言葉
品詞の分類
- >> 「退官」を含む用語の索引
- 退官のページへのリンク


