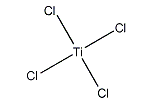テトラクロロチタン(IV)
塩化チタン(IV)
(四塩化チタン から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/01/02 07:15 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2023年1月)
|
| 塩化チタン(IV) | |
|---|---|
 |
|
|
別称
四塩化チタン
|
|
| 識別情報 | |
| CAS登録番号 | 7550-45-0 |
| PubChem | 24193 |
| MeSH | Titanium+tetrachloride |
| RTECS番号 | XR1925000 |
|
|
|
|
| 特性 | |
| 化学式 | TiCl4 |
| モル質量 | 189.71 g mol−1 |
| 外観 | 無色から淡黄色の液体 |
| 密度 | 1.730 (g cm−3)(液体) |
| 融点 | −24 度 |
| 沸点 | 136.4 度 |
| 危険性 | |
| 安全データシート(外部リンク) | MSDS |
| EU分類 |  C C |
| NFPA 704 | |
| Rフレーズ | R14, R34 |
| Sフレーズ | (S1/2), S7/8, S26, S30, S36/37/39, S45 |
| R/Sフレーズ | R14, R34 |
| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |
塩化チタン(IV)(えんかチタン、titanium(IV) chloride)は化学式 TiCl4 で表されるチタンの塩化物で、融点 −24 ℃、沸点 136.4 ℃ の無色から淡黄色の液体。四塩化チタンとも呼ばれる。CAS登録番号は [7550-45-0]。水と反応して酸化チタン(IV) と塩化水素を生じる。空気中の水分とも反応して塩化水素の白煙を生じる。
工業的にはチタン鉄鉱またはルチル鉱石をコークスと塩素とともに炉で 900 ℃に熱して粗塩化チタン(IV) を作り(クロール (Kroll) 法、塩素法)、これを蒸留精製して純粋なものを得る。塩化チタン(IV) は主に顔料や化粧品の原料として利用される酸化チタン(IV) を生成するのに使われる。
有機化学ではルイス酸として向山アルドール反応などに利用されるほか、オレフィンの重合に用いる触媒であるチーグラー・ナッタ触媒の原料としても使用される。
空気中の水分と反応して白煙を生じる特性があるため、曲技飛行でのスモークや特撮で煙の表現に使われる。特撮では火薬や火を使わずに対象物から煙を出せるので、破壊されたミニチュアセットや怪獣やヒーローがやられた表現演出に多用された。使い方は筆で直接塗ったり、注射器でかけることで任意の場所から煙を発生させることができる。ただし塩化水素の白煙であるため刺激性があり、現代ではCGで代用される。航空機のスモークとしてもミシン油やパラフィン系のオイルで代用されるなど煙としての利用は行われなくなった。軍用としては煙幕として使われていたが、より効果の高いリン系に置き換わっている。
関連項目
四塩化チタン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/18 04:07 UTC 版)
四塩化チタン(FM)は、黄色をした不燃性で腐食性の液体である。 水分を含んだ空気と接触すると直ちに加水分解を始め、塩化水素の液滴とチタン酸塩化物の微粒子からなる濃い白煙を生じる。 チタン四塩化物の煙は刺激性で、呼吸に著しい不快感を伴う。液体のFMを取り扱う際には防護服とゴーグル、人工呼吸装置の着用が必須とされる。 航空機から散布することで垂直の煙幕をつくるほか、第二次世界大戦中には軍艦が煙幕を形成する際に好まれた。
※この「四塩化チタン」の解説は、「煙幕」の解説の一部です。
「四塩化チタン」を含む「煙幕」の記事については、「煙幕」の概要を参照ください。
四塩化チタンと同じ種類の言葉
- 四塩化チタンのページへのリンク