木本氏房(きもとうじふさ 1884-?)
木本氏房は、「大正三年度作業部署表」に測量師、工兵中尉とある。以後彼の著作物に残る履歴によれば、昭和12年(1937)、陸軍士官学校卒、同16年陸軍砲工(科学)学校卒、陸軍野戦砲兵学校教官(陸軍少佐)とあり、戦後は民間航空測量会社に永く勤務した。
大正10年、第一次世界大戦後ドイツからハイデ杜で作ったフーゲルスホフの地上および空中写真測量用のオートカルトグラフ(現在科学博物館に残る)が第一次大戦の賠償として持ち込まれ、陸軍省から陸地測量部に依託された。その際陸地測量部は、大村斉工兵大佐以下9名に空中写真測量研究委員を命じ、具体的な研究を開始した。この作業の中心にいたのが木本氏房である。
そのとき木本氏房らは、所沢地区を撮影した気球写真から図化した(大正11年 1922)。これは、わが国で行なわれた初めての空中写真測量となるもので、座標測定機(コンパレータ)によって写真座標を測定し、計算によって標定を行なったのち図化を実施した。木本が担当した本作業は、電子計算機もない当時には多くの困難があったと思われ、空中写真測量の解析標定と機械図化の嚆矢となるものである。しかし、これは実用化にはつながらなかった。その後大正14年に下志津飛行場の1万分の1地図修正、翌15年の飯能付近の5千分の1図化が行われて、これらは一定の成果を得た。
一方、昭和7年には満洲航空株式会社が設立され、ここで航空写真測量が実施されることになり、予備役陸軍工兵大佐木本氏房が嘱託に任命されて(昭和8年)、満洲国内における航空写真に関する基礎的調査が開始される。陸軍参謀本部の手によって開発された航空写真測量技術が、意外にも満蒙経営の一環を担うことになる。そのときの初代写真班長が木本氏房である。
木本は、ツアイス製図化機ステレオ・プラニグラフ(C4)、アメリカ製フェアチャイルド製カメラ(K8)その他の購入を担当し、これを機に大陸での航空写真測量が開始される。その実績は昭和19年までに満州全土の90%の撮影が完了し、その他広範な地図作成が行われた。
前述のように、木本をはじめとする満洲航空の技術者の多くは、戦後民間航空測量会社の設立などにかかわり日本の復興に貢献する。 木本には、「航空写真測量」(1941)など多数の著書がある。
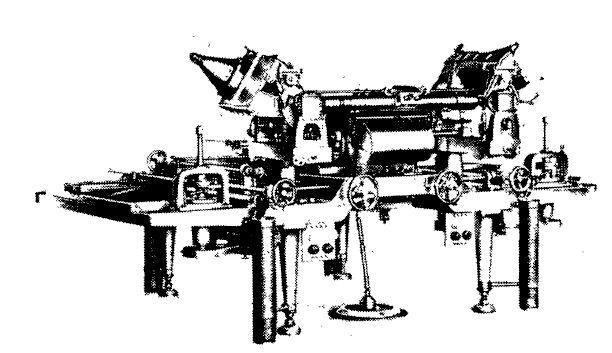
- きもとうじふさのページへのリンク
