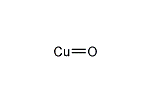テノライト
酸化銅(II)
(酸化第二銅 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/20 22:46 UTC 版)

|
|

|
|

|
|
| 物質名 | |
|---|---|
|
Copper(II) oxide |
|
|
別名
Cupric oxide |
|
| 識別情報 | |
|
3D model (JSmol)
|
|
| ChEBI | |
| ChEMBL | |
| ChemSpider | |
| ECHA InfoCard | 100.013.882 |
| EC番号 |
|
|
PubChem CID
|
|
| RTECS number |
|
| UNII | |
|
CompTox Dashboard (EPA)
|
|
|
|
|
|
| 性質 | |
| CuO | |
| モル質量 | 79.545 g/mol |
| 外観 | 黒色から茶色の粉末 |
| 密度 | 6.315 g/cm3 |
| 融点 | 1,326 °C (2,419 °F; 1,599 K) |
| 沸点 | 2,000 °C (3,630 °F; 2,270 K) |
| 溶けない | |
| 溶解度 | 塩化アンモニウム、シアン化カリウムに溶ける。エタノール、炭酸アンモニウムに溶けない。 |
| バンドギャップ | 1.2 eV |
| 磁化率 | +238.9·10−6 cm3/mol |
| 屈折率 (nD) | 2.63 |
| 構造 | |
| 単斜晶系, mS8[1] | |
| C2/c, #15 | |
|
a = 4.6837, b = 3.4226, c = 5.1288
α = 90°, β = 99.54°, γ = 90°
|
|
| 熱化学 | |
| 標準モルエントロピー S |
43 J·mol−1·K−1 |
| 標準生成熱 ΔfH |
−156 kJ·mol−1 |
| 危険性 | |
| GHS表示: | |
  |
|
| Warning | |
| H302, H410, H412 | |
| P264, P270, P273, P301+P317, P330, P391, P501 | |
| NFPA 704(ファイア・ダイアモンド) | |
| 引火点 | 不燃性 |
| NIOSH(米国の健康曝露限度): | |
|
PEL
|
TWA 1 mg/m3 (as Cu)[2] |
|
REL
|
TWA 1 mg/m3 (as Cu)[2] |
|
IDLH
|
TWA 100 mg/m3 (as Cu)[2] |
| 安全データシート (SDS) | Fisher Scientific |
| 関連する物質 | |
| その他の 陰イオン |
硫化銅(II) |
| その他の 陽イオン |
酸化ニッケル(II) 酸化亜鉛 |
| 関連物質 | 酸化銅(I) |
|
特記無き場合、データは標準状態 (25 °C [77 °F], 100 kPa) におけるものである。
|
|
酸化銅(II)(さんかどう に、英: copper(II) oxide)は化学式 CuO で表される銅の酸化物で、黒色の粉末。CAS登録番号は[1317-38-0]。水、アルコールに不溶。塩酸、硫酸、塩化アンモニウム溶液、アンモニア水などに可溶。融点1,026 °C。1,050 °C以上で分解して酸化銅(I)になる。
酸化銅(II)は塩基性酸化物であるので、酸と反応して塩を作る。水素または一酸化炭素気流中で250 °Cに加熱すると容易に金属銅に還元される。また、黒鉛粉末とともに加熱することによっても還元される。天然では黒銅鉱として産出する。
釉薬の着色剤として利用される。陶磁器に酸化銅(II)を添加した釉薬をかけて焼成すると、酸化焼成では青色-緑色に、還元焼成では赤色に発色する。還元焼成で現れる赤色はかつては釉薬中の酸化銅(II)が金属銅に還元されて発色したものと考えられたが、今日では酸化銅(II)が酸化銅(I)に還元されて赤く発色すると考えられている。
生成
「酸化第二銅」の例文・使い方・用例・文例
- 酸化第二銅のページへのリンク