ミグ溶接
シールドガスとしてアルゴンやヘリウムなどの不活性ガスを使う金属消耗電極を採用したアーク溶接。おもにステンレスやアルミ合金の溶接に使われ、鉄鋼にはアルゴンに少量の炭酸ガス、あるいは酸素を混ぜたシールドガスを使う。アルゴンと炭酸ガスの混合ガスを使用する大電流ミグ溶接はアルミ合金の厚板溶接に適している。
ティグ溶接・ミグ溶接・炭酸ガス溶接
アーク溶接法における、溶接部の大気元素との反応による特性劣化を防ぐ手段として各種のイナート(不活性)ガス雰囲気中で溶接する方法がある。
その代表的なイナートガスとして、アルゴンやヘリウムを使う場合(ティグ溶接・ミグ溶接)と、炭酸ガスを使う場合が挙げられる。
イナートガス溶接では、電極と材料(母材)との間にアークを発生させ、溶接部には電極周囲よりイナートガスを吹きつけ、大気と遮断する。
ティグ溶接(タングステン・イナート・ガスアーク溶接)は、電極にタングステンまたは酸化物入りタングステンを用いるが、タングステン電極の先端はほとんど溶融しない(非消耗電極)。溶接に際しては側面から充填棒を挿入し、この充填棒と母材とが溶融して接合を行う方法である。
ミグ溶接(メタル・イナート・ガスアーク溶接)は、溶接ワイヤとして電極線を用い、その先端と母材との間にアークを発生させ、両者を同時に溶融させて溶接する。
これらのイナートガスアーク溶接は、フラックスが不要なためアークが安定しており、溶接方向に自由度が高く、また大気を遮断するため化学的に大気と反応しやすい金属(アルミ、銅、チタンなどの非鉄金属及びステンレス)であっても溶接が可能である。
炭酸ガスアーク溶接は、イナートガスの代わりに、安価な炭酸ガス(CO2)を用いて鋼を溶接する方法である。炭酸ガスアーク溶接ではミグ溶接と同様、電極には主に溶接ワイヤが使用される。CO2は高温で分解し、COとO2に分離、特にO2により溶接部への酸化が起こるため、溶接ワイヤ自体に脱酸化性元素を加える。軟鋼に対してのイナートガス溶接は高価につくため、こうして酸化対策を施した炭酸ガス溶接が普及し、自動車、造船、橋梁など軟鋼、低合金鋼の溶接方法として、被覆アーク溶接に代わって利用が拡大している。
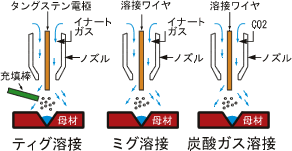
適している分野・使用事例
ティグ溶接、ミグ溶接=アルミ合金、銅合金、チタン、ステンレスなどの溶接。炭酸ガス溶接=軟鋼、低合金鋼の溶接。
用語解説
ミグ溶接
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/12/29 09:16 UTC 版)

|
この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2011年12月)
|
ミグ溶接またはMIG溶接(ミグようせつ、metal inert gas welding)とは溶接工法の一種である。マグ溶接と合わせて、ガスシールドアーク溶接に分類される。
概要
アーク溶接のうち、シールドガスに不活性ガスのみを使い、金属電極棒が溶加材として送給ローラーで自動的に母材に送り込まれ、そのまま溶融して溶接する方式であり、通常半自動溶接として使われる。一般的には半自動溶接の一種と考えてよい。ミグ溶接のしくみについては半自動溶接の項を参照のこと。
鉄系材料のほか、非鉄金属にも使用される。ミグ溶接は溶接速度が速く、シールドガスによって、大気と遮断された状態で溶接作業が行われるので、空気中の酸素の影響を受けずに溶接が進行し、熱の発生が局部に止まるので、ひずみの発生が少なく、薄板鋼板の溶接に適している。
不活性ガスとしてアルゴン、ヘリウムの他、さまざまな混合ガスが使われる。日本ではこれらのガスはやや高価なため、ユーザーから高い溶接品質が求められない限り炭酸ガスアーク溶接が使われることが多い。一般に産業ガスメーカーが溶接機器・機材などと合わせて販売する。不活性ガスが比較的な安価なヨーロッパやアメリカではよく使われる。
類似の溶接方法
- 炭酸ガスアーク溶接:シールドガスに炭酸ガス(CO2)のみを使う。
- ミグ溶接:シールドガスに不活性ガスのみを使う。
- マグ溶接:シールドガスに不活性ガスと炭酸ガスを混合して使う。
- ティグ溶接:シールドガスに不活性ガスのみを使う。溶接材の他に非消耗電極を使う。
関連項目
ミグ溶接と同じ種類の言葉
- ミグ溶接のページへのリンク

