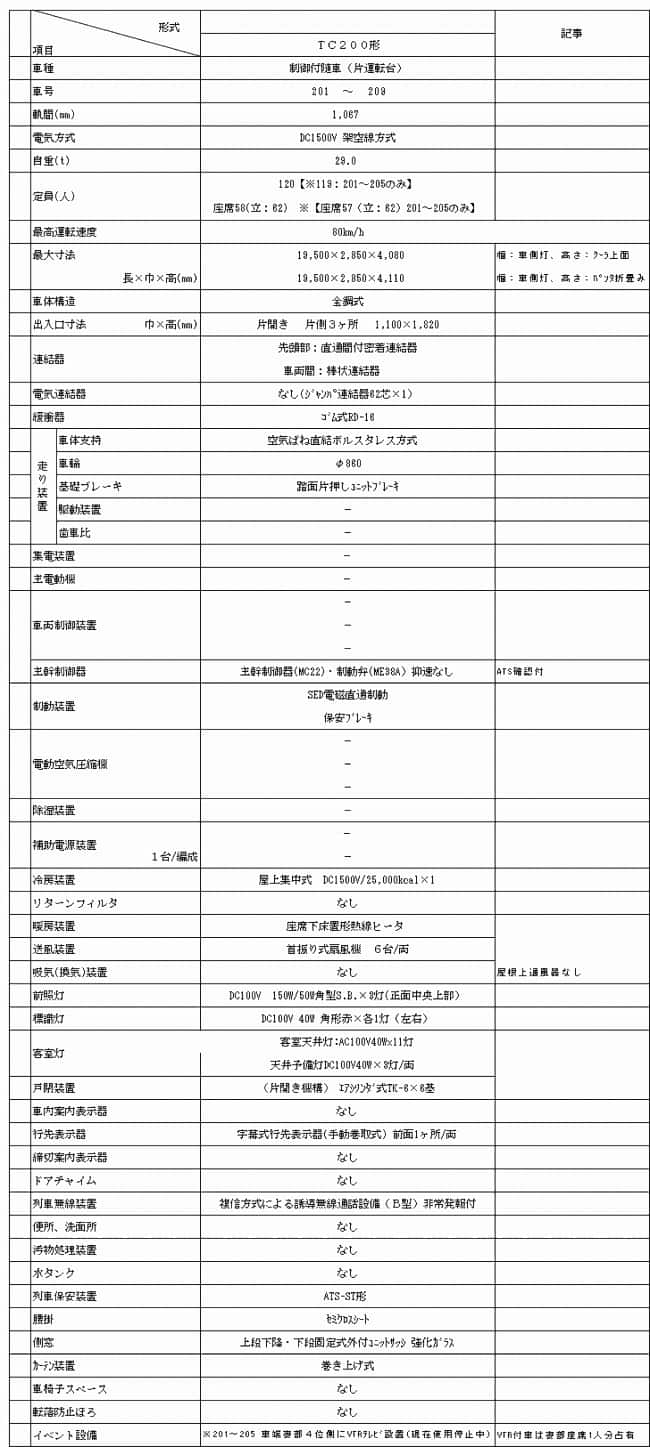200型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/19 03:13 UTC 版)
上記の通り、制御器を交換して連結運転を可能とした20両を1929年の改番で200型とした。この中には木造車と半鋼製車が混在していた。100型同様、1932年に集電装置をパンタグラフに交換している。連結運転が可能だったことから、100型よりも長く京阪線で運用された。100型の項で記した通り、1942年にさらに10両が100型から改造を受けて本形式に編入されている。1947年(昭和22年)には1両が当時同一会社だった京阪神急行電鉄神戸線に転属、2両が100型2両と共に1300系製造に伴う供出車として広島電鉄宮島線に送られ1050形になった。 1949年(昭和24年)に起きた京津線の四宮車庫火災への救済策として、2両が石山坂本線に移っている。その後木造車の一部は大津線と京阪線の間を行き来した。1953年(昭和28年)から1954年(昭和29年)にかけて半鋼製車6両が、電気制動の取りつけを行った上で大津線に転属した。同時期に京津線ではホームを2両編成対応に改造し、転属した半鋼製の本形式は2両編成で京津線の急行運用に就くことになった。それ以外の木造車については1957年(昭和32年)から廃車が始まり、台車や電装品は大津線の260型に再利用された。木造車は1962年(昭和37年)で消滅した。 大津線に残った半鋼製車も1968年(昭和43年)に全車が廃車となり、やはり260型に電装品を提供している。
※この「200型」の解説は、「京阪100型電車」の解説の一部です。
「200型」を含む「京阪100型電車」の記事については、「京阪100型電車」の概要を参照ください。
- 200型のページへのリンク