日本のウイスキーの歴史
| ウイスキーが日本に伝来したのは、江戸時代の末期のこと。1853年、アメリカのペリーが艦隊を率いて日本を訪れたとき、他の多くの洋酒とともにスコッチウイスキーとバーボンウイスキーを持参しました。文献にも、献上物の中に「ウイスキー樽」と明記されています。明治維新後の1871年、主に薬種問屋が輸入元となり、日本は初めて公式にウイスキーの輸入を開始しました。当時は、舶来品一辺倒の時代、国産ウイスキーをつくるというまでには至らず、本格的ウイスキーの誕生までには、さらに50年近くの歳月が必要となります。 | |
|
日本における本格的ウイスキー生産の歴史は、壽屋(サントリーの旧名)の鳥井信治郎によって幕が切っておとされました。鳥井信治郎は関東大震災から1カ月後の1923(大正12)年10月、京都郊外の山崎の地に、わが国初のモルトウイスキー蒸溜所(現在のサントリー山崎蒸溜所)を建設し、ウイスキーづくりをはじめました。これは、創業以来24年目、赤玉ポートワインの人気などでようやく軌道に乗った壽屋の全資金をかけた冒険でした。 |
 |
|
そして6年後の1929(昭和4)年、本格国産ウイスキー「サントリーウイスキー白札」が誕生したのです。満を持して発売した「白札」でしたが、当時ウイスキーはまだ一般のものではなかったこと、ピートによるスモ-キーフレーバーが強すぎ焦げ臭かったことなどから評判があまりよくなく、すぐには売れませんでした。ところが、「白札」が売れなかったことにより、原酒が貯蔵庫に眠ることになり、1937(昭和12)年には「十二年もの」(のちの「角瓶」)が発売され、この時には好評をもって迎えられたのです。 |
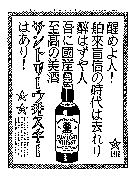 |
- 日本のウイスキーの歴史のページへのリンク
