小川一真(おがわいっしん・かづま1860-1929)
写真師、写真業・写真出版業の先覚者。
武蔵国忍藩(現埼玉県行田市)藩士原田庄左衛門の二男として生まれ、行田藩士小川石太郎の養子となり、名を一眞と改める。明治6年(1873)、旧藩主松平忠敬の給費で東京の有馬学校に入り土木工学を、同13年築地のバラー学校で英語を学ぶ。
同15年有馬学校時代に興味を抱いた写真術を極めようと渡米し、最新の写真技術やコロタイプ印刷術などを習得し、明治17年帰国。同年、東京飯田町に玉潤(写真)館を開業、最新技術で写真撮影をする写真館として評判をとる。明治20年内務省の委嘱でアメリカ トッド博士らの日蝕観測団に参加し皆既日食のコロナ撮影を行う。翌21年には、枢密院顧問官図書頭の九鬼隆一に同行し、奈良の古寺に遺された仏像など文化財の調査撮影を行うなど、日本における写真界の発展に尽力した。
同22年には、小川写真製版所を開設し、コロタイプ印刷やカラー印刷の実用化に取り組む。
地図測量の関連では、陸軍参謀本部陸地測量部の大本営写真班(小倉倹司ら)の嘱託写真師でもあったことから、各地で行われた「陸軍大演習写真帖」(陸地測量部撮影)のほか、「日清戦争写真石版」(明治28年)、「日露戦役写真帖第1ー3」(明治37・38年)の発行を行うなど、日本における写真界の発展に尽力した。
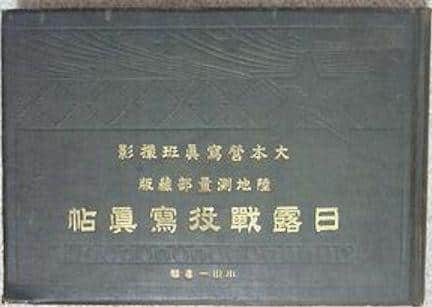
武蔵国忍藩(現埼玉県行田市)藩士原田庄左衛門の二男として生まれ、行田藩士小川石太郎の養子となり、名を一眞と改める。明治6年(1873)、旧藩主松平忠敬の給費で東京の有馬学校に入り土木工学を、同13年築地のバラー学校で英語を学ぶ。
同15年有馬学校時代に興味を抱いた写真術を極めようと渡米し、最新の写真技術やコロタイプ印刷術などを習得し、明治17年帰国。同年、東京飯田町に玉潤(写真)館を開業、最新技術で写真撮影をする写真館として評判をとる。明治20年内務省の委嘱でアメリカ トッド博士らの日蝕観測団に参加し皆既日食のコロナ撮影を行う。翌21年には、枢密院顧問官図書頭の九鬼隆一に同行し、奈良の古寺に遺された仏像など文化財の調査撮影を行うなど、日本における写真界の発展に尽力した。
同22年には、小川写真製版所を開設し、コロタイプ印刷やカラー印刷の実用化に取り組む。
地図測量の関連では、陸軍参謀本部陸地測量部の大本営写真班(小倉倹司ら)の嘱託写真師でもあったことから、各地で行われた「陸軍大演習写真帖」(陸地測量部撮影)のほか、「日清戦争写真石版」(明治28年)、「日露戦役写真帖第1ー3」(明治37・38年)の発行を行うなど、日本における写真界の発展に尽力した。
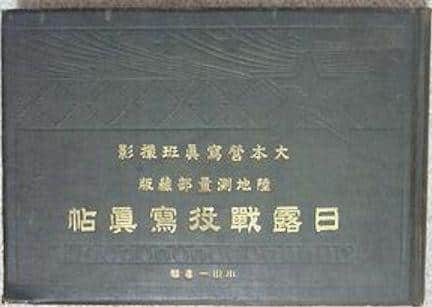
- おがわいっしんのページへのリンク
