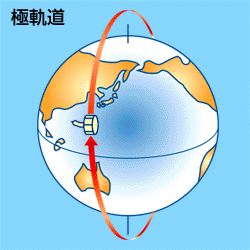人工衛星の代表的な軌道(1)
地上からつねに静止して見える、「静止軌道」の衛星
軌道傾斜角度0度、つまり、赤道上空の高度約36,000kmの円軌道を毎秒約3kmの速度で周回する軌道です。衛星の周期は、地球の自転周期と同じ約24時間なので、地上から見るとつねに静止しているように見えます。そのため「静止衛星」といわれるのです。気象衛星や放送衛星など、広く利用されています。
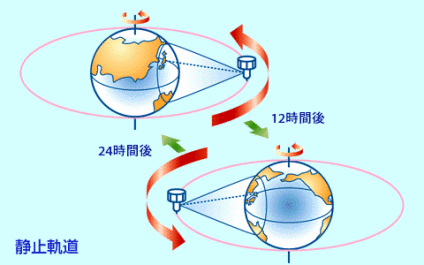
衛星の周期が地球と同じため、つねに同じ上空を飛行しているように見えます。
「同期軌道」の衛星は1日1回地球を回り、もとの場所にもどる
1日に1回、地球のまわりを回って、またもとの地表面上空にもどってくる軌道を「同期軌道」(どうききどう)といいます。衛星の公転周期は地球の自転周期と同じです。静止軌道もこの同期軌道の一種ですが、静止軌道とのちがいは、軌道傾斜角度が0度にかぎらないことと、だ円軌道の場合もあることです。静止軌道ではカバーの困難な地球の高緯度地方の観測や通信に適しています。

円軌道の場合、北緯60度の上空を飛んでいた衛星が、12時間後には南緯60度、さらに12時間後には北緯60度の同一地点の上空にもどります。
「回帰軌道」の衛星は、その日のうちにもとの場所の上空にもどる
「回帰軌道」(かいききどう)とは、24時間以内に地球上空を何周か回り、元の地表面上空にもどってくる軌道です。衛星の公転周期は地球の自転周期の整数分の1で、近地点約600km、遠地点約4万kmの長だ円軌道の衛星の周期は約12時間で、1日に2度、同一地点の上空にもどってきます。この軌道に打ち上げられた衛星は、高緯度地方の通信や観測に適しています。
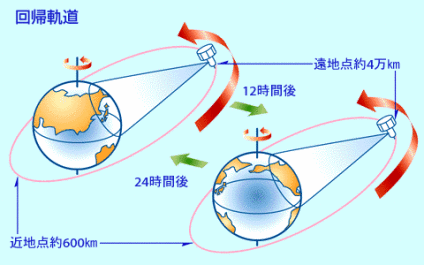
近地点が約600km、遠地点約40,000kmの長だ円軌道の衛星の周期は、約12時間となり、1日に2度、同一地点の上空へもどってきます。
「準回帰軌道」は、数日後に同じ場所の上空に衛星がもどる
1日に地球を何周も回り、数日後に定期的に元の地表面上空にもどってくる軌道です。地球観測衛星「ランドサット」も近地点約680km、遠地点約700km、周期98.5分で、1日に地球を15周し、16日後にはもとの地表面上空にもどってきます。この場合、「回帰日数16日の準回帰軌道」といいます。長期間、定期的に地球を観測するのに適しています。
人工衛星の代表的な軌道(2)
北極、南極の上空付近を回る「極軌道」
軌道傾斜角が90度、もしくはこれに近い角度の軌道のことを「極軌道」といいます。衛星が軌道を周回しているあいだ、地球が自転するため、北極・南極を含め、数日後には地球全体をカバーすることができます。そのため、全地球の観測に適しており、多くの地球観測衛星は極軌道、あるいは極軌道に近い軌道に投入されています。
衛星の軌道面と太陽方向がつねに一定になる「太陽同期軌道」
太陽同期軌道とは、衛星の軌道面の回転方向と周期(1日あたりの回転角)が地球の公転周期(1日あたりの回転角)に等しい軌道。つまり、地球を回る衛星の軌道面全体が1年に1回転し、衛星の軌道面と太陽方向がつねに一定になる軌道のことです。このような軌道は極軌道でのみ可能となりますが、軌道傾斜角90度の完全な極軌道では、衛星軌道面の回転は起こらず、90度より大きな傾斜角の場合に、地球と同じ方向に回転します。また、この軌道傾斜角は、衛星の軌道高度によってちがってきます。たとえば、高度800キロメートルの円軌道の場合、傾斜角を98.4度にすると太陽同期軌道となります。この軌道を回る衛星から地球を見た場合、地表に当たる太陽光線がつねに一定の角度であるため、同一条件下での地球観測をおこなうのに適しています。
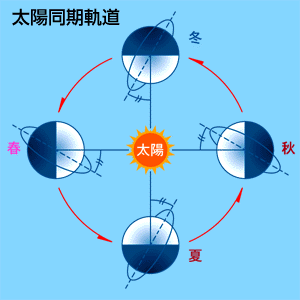
太陽同期軌道の場合は、同じ時間帯に同一地点の上空を通過します。
地球観測衛星の多くは「太陽同期準回帰軌道」で打ち上げられている
太陽同期準回帰軌道は、太陽同期軌道と準回帰軌道を組み合わせた軌道です。この軌道に打ち上げられた衛星は、何日かの周期ごとに同一地点の上空を、同一時間帯に通過するため、同一条件でくりかえし地表を観測できます。そのため、地球を広範囲にわたって恒常的に観測するのにきわめて有効で、多くの地球観測衛星がこの軌道に打ち上げられ、全地球の観測をおこなっています。
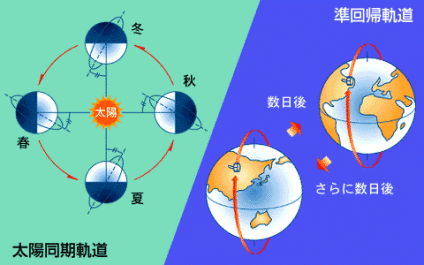
太陽同期準回帰軌道では、10数日後に同一地点の上空にもどってきますが(準回帰軌道)、そのときにはかならず前回と同じ時間帯に通過します。(太陽同期軌道)
- 人工衛星の代表的な軌道のページへのリンク