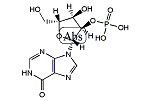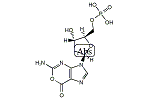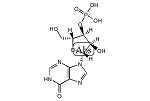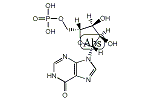2′‐IMP
2′‐デオキシオキサノシン5′‐モノホスファート
| 分子式: | C10H13N4O8P |
| その他の名称: | 3-(5-O-Phosphono-2-deoxy-β-D-erythro-pentofuranosyl)-5-aminoimidazo[4,5-d][1,3]oxazine-7(3H)-one、5-Amino-3-(5-O-phosphono-2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)imidazo[4,5-d][1,3]oxazine-7(3H)-one、2'-デオキシオキサノシン5'-モノホスファート、2'-Deoxyoxanosine 5'-monophosphate |
| 体系名: | 3-(5-O-ホスホノ-2-デオキシ-β-D-erythro-ペントフラノシル)-5-アミノイミダゾ[4,5-d][1,3]オキサジン-7(3H)-オン、5-アミノ-3-(5-O-ホスホノ-2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)イミダゾ[4,5-d][1,3]オキサジン-7(3H)-オン |
3′‐IMP
| 分子式: | C10H13N4O8P |
| その他の名称: | Ip、Ino-3'-P、3'-Inosinic acid、3'-IMP、Inosine 3'-phosphate |
| 体系名: | イノシン3'-りん酸、3'-イノシン酸、イノシン3'-ホスファート |
IMP
| 分子式: | C10H13N4O8P |
| その他の名称: | イノシン酸、ヒポキサンチンリボシド5-りん酸、pI、IMP、Ino-5'-P、Inosinic acid、5'-Inosinic acid、Hypoxanthine riboside-5-phosphoric acid、9-(5-O-Phosphono-β-D-ribofuranosyl)-9H-purin-6(1H)-one、Inosine 5'-phosphoric acid、5'-IMP、Inosine 5'-phosphate、2-Deamino-5'-guanylic acid、9-[5-O-(Dihydroxyphosphinyl)-β-D-ribofuranosyl]-1,6-dihydro-9H-purine-6-one |
| 体系名: | 9-(5-O-ホスホノ-β-D-リボフラノシル)-9H-プリン-6(1H)-オン、イノシン5'-りん酸、5'-イノシン酸、イノシン5'-ホスファート、2-デアミノ-5'-グアニル酸、9-[5-O-(ジヒドロキシホスフィニル)-β-D-リボフラノシル]-1,6-ジヒドロ-9H-プリン-6-オン |
ara‐IMP
| 分子式: | C10H13N4O8P |
| その他の名称: | ara-IMP、9-(5-O-Phosphono-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6(1H)-one |
| 体系名: | 9-(5-O-ホスホノ-β-D-アラビノフラノシル)-9H-プリン-6(1H)-オン |
アロプリノールリボチド
| 分子式: | C10H13N4O8P |
| その他の名称: | アロプリノールリボチド、Allopurinol ribotide、1-Deoxy-1-[(1,5-dihydro-4-oxo-4H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin)-1-yl]-β-D-ribofuranose 5-phosphoric acid、1-[5-O-(Dihydroxyphosphinyl)-β-D-ribofuranosyl]-4,5-dihydro-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-one、1-(5-O-Phosphono-β-D-ribofuranosyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-4-ol、Allopurinol-3-riboside 5'-monophosphate、アロプリノール3-リボシド5'-りん酸 |
| 体系名: | 1-デオキシ-1-[(1,5-ジヒドロ-4-オキソ-4H-ピラゾロ[3,4-d]ピリミジン)-1-イル]-β-D-リボフラノース5-りん酸、1-[5-O-(ジヒドロキシホスフィニル)-β-D-リボフラノシル]-4,5-ジヒドロ-1H-ピラゾロ[3,4-d]ピリミジン-4-オン、1-(5-O-ホスホノ-β-D-リボフラノシル)-1H-ピラゾロ[3,4-d]ピリミジン-4-オール |
イノシン酸
(C10H13N4O8P から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/21 03:32 UTC 版)
| イノシン酸 | |
|---|---|
 |
|
| 識別情報 | |
| CAS登録番号 | 131-99-7  |
| PubChem | 8582 |
| ChemSpider | 8264  |
| E番号 | E630 (調味料) |
| KEGG | C00130 |
| MeSH | Inosine+monophosphate |
|
|
|
|
| 特性 | |
| 化学式 | C10H13N4O8P |
| モル質量 | 348.206 g/mol |
| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |
イノシン酸(イノシンさん、inosinic acid)は、ヌクレオチド構造を持つ有機化合物の一種である。ヒポキサンチン(6-ヒドロキシプリン)と D-リボースとリン酸各1分子ずつで構成されたリボヌクレオチドで、イノシン 5'-リン酸、イノシン 5'-モノリン酸、イノシン一リン酸などとも呼ばれ、IMP と略記される。主に肉類の中に存在する天然化合物である。
呈味性ヌクレオチドの1つであり、日本では鰹節に含まれるうま味成分のひとつとして語られることが多い。
致死量はLD50=14.4g/kgである。
生合成と反応
生合成
イノシン酸は、リボース5-リン酸から出発してプリンヌクレオチド(アデノシン一リン酸 (AMP)、グアノシン一リン酸 (GMP))へ至るプリンヌクレオチド生合成において、分岐点にあたる中間体である。イノシン酸から、AMP へ至る経路と GMP へ至る経路が分かれている。
また、アデノシン一リン酸を分解して尿酸とする経路の中では、アデノシン一リン酸に脱アミノ酵素(デアミナーゼ)が作用してイノシン酸が生じる。
反応
酸で処理すると加水分解を受け、等モルのヒポキサンチン、D-リボース、およびリン酸を生じる。
利用
イノシン酸のナトリウム塩(イノシン酸ナトリウム)は、かつお節の旨味の主成分であり、うま味調味料として重要である。核酸系調味料の多くはシイタケ旨味成分である5'-GMPと5'-IMPの混合物であり、工業的には酵母のRNAを原料にして、アオカビのヌクレアーゼP1(EC. 3.1.30.1)を作用させて5'-GMPと5'-AMPの混合物にし、コウジ菌のAMPデアミナーゼで5'-AMPのみを5'-IMPに転換して酵素的に核酸系調味料を製造している。[1]
鰹節等からのイノシン酸の抽出には水に含まれるミネラルが悪影響を及ぼすので軟水の使用が望ましい[2][3][4]という話がよくあるが、軟水・中硬水・硬水を用いた実験で軟水と中硬水でほとんど差が出ない一方硬水で最も多くイノシン酸が抽出できたとする報告もあり(好ましさの官能検査の結果では有意差がなかった)[5]、必ずしも硬水の使用がイノシン酸抽出における悪条件とはならないようである。
関連化合物
参考文献
- ^ 一島英治、『酵素の化学』p183 ISBN 4-254-14555-1
- ^ 軟水と硬水について
- ^ 硬水・軟水で料理の味が変わる
- ^ 軟水、硬水はどのように使い分けされているのでしょうか。
- ^ 坂本真里子、河野一世、熊谷まゆみ、赤野裕文、畑江敬子、鈴野弘子「水の硬度が煮出し汁の嗜好性と溶出成分に及ぼす影響」『日本調理科学会誌』第40巻第6号、日本調理科学会、2007年、doi:10.11402/cookeryscience1995.40.6_427、ISSN 2186-5787。
- C10H13N4O8Pのページへのリンク