大岡金太郎(おおかきんたろう? 1844?- 1900?)
大岡金太郎は函館戦争に際して、幕臣松平太郎の従者として参戦した。明治7年、海軍中将榎本武揚が特命全権大使としてロシア赴任するに際し、大岡金太郎および寺見機一らは従者としてこれに随行し、そのペテルプルグ(サンクトペテルブルク)滞在中に大岡は写真電気銅版製版法などを学び、明治11年に榎本とともに帰国した。
それ以前、榎本武揚は函館戦争後開拓使に出仕していたが、明治5年(1872)の北海道出張に同行、同6年には宮城県涌谷移民跡地を大岡金太郎名義での払下げを受けて、北海道江別市の対雁に農場を開設しているという。これは、榎本武揚が在ロシアのころ、大岡ののことを「大金」と手紙に書いて留守宅に知らせていたことも含めて、榎本と大岡の特別な関係を示すものである。
明治12年(11年10月雇い入れたが翌年から勤務を始めた?)、陸地測量部は地図の製版に写真電気銅版製版法を導入するにあたり大岡金太郎を雇用した。翌13年、新たに雇用した写真の専門家斉藤藤太郎と協力して、写真電気銅版製版の開発に着手する。明治18年、19年には東京5千分の1図9面の銅版彫刻、迅速2万分の1図4面にも着手した。写真電気銅版製版法の研究は、その後も大岡金太郎と石丸三七郎らにより続けられ、その有効性が認められて、20万分の1帝国図は彫刻銅版とし、地形図は写真電気銅版によって迅速に製版することが決められた(明治19年)。
その後、明治9年開業の秀英舎(大日本印刷の前身)の石版部開設に伴い、ここでも電気銅版製版法の技術指導を行った。秀英舎は石版部を、あの大岡金太郎を示す「大金」に由来する「泰」、「錦」の文字を当てて、「泰錦堂」と命名し絵画印刷などに適した石版印刷などを開始したという。
明治33年(1900)、故人となっていた大岡金太郎に対し陸地測量部長から褒賞が与えられた。
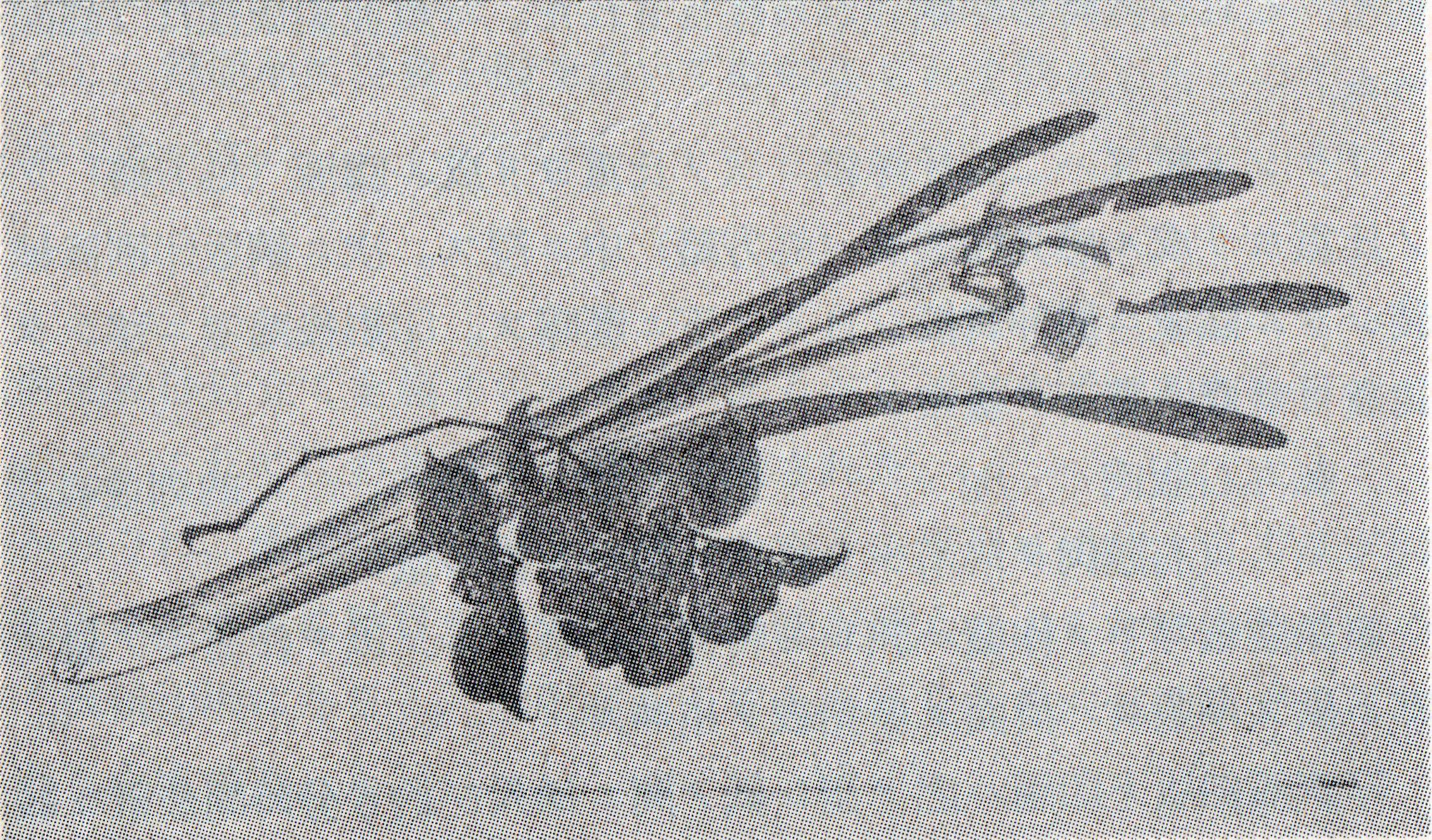
詳細不明だが、バンダイク製版法の説明として「測量地図百年史」にある
- 大岡金太郎のページへのリンク
