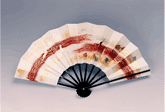舞扇
舞扇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2008/05/04 14:28 UTC 版)
舞扇(まいおうぎ)は、日本舞踊に用いられる扇子である。普通の扇子と材質は同じで、10本ある骨には竹や木、扇面は紙が用いられる。しかし舞踊では扇を投げたり、指で挟んで回す「要返し」などの動作を行ったりするため、扱いやすいよう要の部分に鉛の重りが仕込まれている。また耐久度を上げるため、親骨と紙は糊で貼られた上に糸で結ばれ強化されている。
扇面は無地のものや、各流派の流紋がデザインされたものがある。また舞台用には演目に沿った絵が描かれたものが用いられる。舞扇のデザインで稽古の進度を示す井上流のように、デザインに意味を持たせる場合もある。
なお日本舞踊には必ず舞扇が用いられるわけではなく、中啓や軍扇など他の扇子が用いられる演目もある。
画像
参考文献
- 藤田洋『日本舞踊ハンドブック』三省堂、2001年、64-65頁。
舞扇
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/11 00:28 UTC 版)
金地に白ぬきで井菱の定紋、扇の図柄の根本は"近衛引-このえびき-"の段々。お稽古が進むほどに模様の段数が増える。大人用は白骨で9寸5分。 芸妓用 - 金地近衛引萌黄段紋入、または 金地近衛引紫段紋入 舞妓用 - 金地近衛引紅段紋入 稽古用 - 白地金砂子に井菱の紋 子供用 - 薄紅地(ピンク)に金砂子。8寸5分 名取の扇 - 紅地金砂子に白椿一輪、黒骨(くろぼね)
※この「舞扇」の解説は、「井上流」の解説の一部です。
「舞扇」を含む「井上流」の記事については、「井上流」の概要を参照ください。
- >> 「舞扇」を含む用語の索引
- 舞扇のページへのリンク