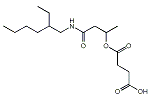こはく酸水素ブトクタミド
| 分子式: | C16H29NO5 |
| その他の名称: | M-2H、こはく酸水素ブトクタミド、Butoctamide hydrogen succinate、Butanedioic acid hydrogen 1-[3-[(2-ethylhexyl)amino]-1-methyl-3-oxopropyl] ester、3-[1-Methyl-2-(2-ethylhexylcarbamoyl)ethoxy]carbonylpropionic acid、N-(2-Ethylhexyl)-3-[(3-carboxypropionyl)oxy]butyramide、リストミンS、Listomin S、セミコハク酸ブトクタミド、Butoctamide semisuccinate |
| 体系名: | 3-[1-メチル-2-(2-エチルヘキシルカルバモイル)エトキシ]カルボニルプロピオン酸、N-(2-エチルヘキシル)-3-[(3-カルボキシプロピオニル)オキシ]ブチルアミド、ブタン二酸水素1-[3-[(2-エチルヘキシル)アミノ]-1-メチル-3-オキソプロピル] |
M-2H
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/02 21:08 UTC 版)
1974年に考案されたミューロケットの改良型である。当時具体計画の検討段階であったM-3Hの第1段(SB-310 + M-11)の上に上段として宇航研の開発した推力7t級のLOX/LH2エンジンES-702を用いたステージを採用する計画であり、当初は仮にM-Xという名称だったが、後にM-2Hという名称になった。低軌道投入能力は500kgと見積もられていた。また、Μ計画とN計画を引き継ぐ低軌道打ち上げ能力10tの大型人工衛星打ち上げロケットAロケットへのステップとなるよう計画されていた。技術試験衛星や惑星探査機を10機打ち上げる予定であったが、予算不足やLOX/LH2エンジンの開発リソースをLE-5に集中させることが決定されたために実現しなかった。 仕様 全長:25m強 直径:1.4m 搭載重量:500kg 打ち上げ計画 1979年:試験機 1980年:AST-T1 1981年:AST-E1, PLP-A 1982年:AST-E2 1983年:AST-T2, PLP-B 1984年:AST-E3, AST-B1 1985年:AST-T3, AST-E4
※この「M-2H」の解説は、「ミューロケット」の解説の一部です。
「M-2H」を含む「ミューロケット」の記事については、「ミューロケット」の概要を参照ください。
- M-2Hのページへのリンク