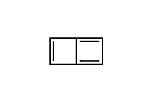p‐ベンザイン
| 分子式: | C6H4 |
| その他の名称: | (Benzene-1,4-diyl) radical、1,4-Phenylene radical、p-ベンザイン、p-Benzyne、p-Phenylene radical、(1,4-Benzenediyl)radical |
| 体系名: | (1,3,5-シクロヘキサトリエン-1,4-ジイル)ラジカル、(ベンゼン-1,4-ジイル)ラジカル、1,4-フェニレンラジカル、p-フェニレンラジカル、(1,4-ベンゼンジイル)ラジカル |
ブタレン
p-ベンザイン
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/07/30 19:23 UTC 版)
p-ベンザインもm-ベンザイン同様、1,4-ジヨードベンゼンやp-ベンゼンジアゾニウムカルボキシラートの熱分解の研究がまず行なわれた。しかし、これらの研究ではp-ベンザインの存在を示すようなデータは得られなかった。これはp-ベンザインが開環して1,5-ヘキサジイン-3-エンへと異性化しやすいためである。 p-ベンザインは1971年に正宗・バーグマン環化の反応中間体として提唱された。1,5-ヘキサジイン-3-エン構造を持つ化合物を加熱すると、環化しながら還元が起こりベンゼン環が生成する。重水素化された溶媒中でこの反応を行なうと1,4-位に重水素化されたベンゼン環が生成する。これは反応中間体としてp-ベンザインが生成し、これが溶媒からの水素引き抜き反応を起こしてベンゼン環となったとすると説明できる。 スペクトルによる確認がはじめてなされたのは1976年にL.O.チャップマンらによってで、アントラキノンビスケテンを光分解して生成した9,10-ジデヒドロアントラセンをマトリックス単離法で確認している。無置換のp-ベンザインは1998年に10 Kのアルゴン中でテレフタル酸と酢酸の混合過酸化物の光分解で生成されたものが、赤外吸収スペクトルにより確認された。 p-ベンザインは溶媒などから水素を引き抜いてベンゼンになりやすい。カリケアミシンのような環状エンジイン構造を持つ物質は生体内で正宗・バーグマン環化を起こしてp-ベンザインを生成し、DNAから水素引き抜き反応を起こしてDNAを切断する。このメカニズムを利用して、白血病の治療薬としての利用が行なわれている。また、加熱下や光照射下では正宗・バーグマン環化の逆反応が進行し、開環して1,5-ヘキサジイン-3-エンとの平衡状態になる。
※この「p-ベンザイン」の解説は、「ベンザイン」の解説の一部です。
「p-ベンザイン」を含む「ベンザイン」の記事については、「ベンザイン」の概要を参照ください。
- p‐ベンザインのページへのリンク