雨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/08 00:33 UTC 版)
観測・報告
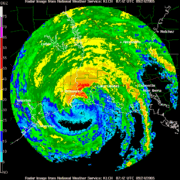
観測機器
雨の観測は主に雨量計や気象レーダーにより行われる。雨量計は標準化されており、日本では直径20cmの円筒形の器具が最も用いられている。雨量計は地点ごとの正確な雨量が分かるが、雨量は地域により大きく偏ることがあり雨量計だけでは雨の全体像を把握できない。一方、気象レーダーは面的に雨の強さの分布が分かるが、雨粒の大きさを測定できないため実際の雨量と大きな誤差が出てしまう。防災面では、両者の欠点を補うため雨量計やレーダーの情報を組み合わせてコンピューター処理した上で活用する[5][41]。
日本の場合、防災を目的に気象庁のアメダス雨量計が国内約1,300か所に設置されている[42]。また気象庁の気象レーダーは20か所に設置され、国内ほぼ全域をカバーしている[43]。このほか国土交通省、都道府県、鉄道会社、電力会社などが、独自の雨量計やレーダーなどを保有している[41]。
雨の観測の歴史は古く、最古のものとしては紀元前4世紀、マウリヤ朝時代の古代インドで行われた観測記録がカウティリヤの著書に記されている。15世紀、李氏朝鮮では世宗が銅製の計器を用いて観測を行わせたとされる。中国でも15世紀に観測が行われた。ヨーロッパでは、17世紀に雨量計が考案され、ロバート・フックが行った観測記録などが残っている。日本では、18世紀初めに徳川吉宗が雨量を観測させたとされるが、記録自体は残っていない[3][44]。
連続した雨量の観測記録の中でもっとも古く信頼できるものは、イギリス・ロンドン郊外のキューにおけるもので、1697年からの記録がある。このデータは、気候変動を論じる上で、降水量の長期変動を示す資料として引用されている。また日本では、1875年6月1日(気象記念日)に当時東京気象台で雨量の観測が始まった[44]。
気象レーダー
気象レーダーは、波長5 - 10cmの電波(マイクロ波)を放射して雨粒からの反射を検知し、半径およそ300 - 500kmの領域内の降雨分布を調べるものである。レーダー電波の反射強度は、雨粒の直径の6乗と大気中の個数(密度)の積で表される。同程度の雨量でも雨粒の大きさが異なるために誤差が生じることがあり、レーダーのみで正確な雨量は求められない[5][41][45]。
なお、雪が融けて雨に変わりつつあるとき、電波が屈折してしまうためその高度のレーダー反射は強くなる。これをブライトバンドという。さらに、雨粒以外のもの、例えば鳥や昆虫などの小動物、空気の乱れなどで異常な観測結果がみられることがあり、このようなものをエンジェルエコーと呼ぶ[41]。
気象衛星
実用投入されている気象衛星は赤外線により雲の観測を行うもので、雨の直接観測は行っていない[45]。衛星による雨の直接観測が可能となったのは1990年代であり、熱帯降雨観測衛星(TRMM)は熱帯の雨の観測を行った。その後、国際的な協力により複数の衛星による全球降水観測計画(GPM)が展開されている。
報告
観測記録や通報では、直径0.5mm以上の水滴が降る場合を「雨」と呼び、直径0.5mm未満の水滴が一様に降るものは「霧雨」として区別する[31]。さらに、対流性の雲(積雲、積乱雲)から降る雨は「驟雨」、過冷却水滴の雨は「着氷性の雨」として区別する。
国際気象通報式[注 3]では、観測時に降っているか止んでいるか、雪・霰・雹を伴うかどうか、雷を伴う否か、雨の3段階強度や雷の3段階強度などの組み合わせで区分される天気から選択して報告する。強度の3区分は、時間雨量3mm未満で弱い雨、3mm以上15mm未満で並の雨、15mm以上で強い雨。雨を表す基本の記号は [46][47]。
[46][47]。
ラジオ気象通報などの日本式天気図では、観測時に雨が降っている場合に天気を「雨」とする。天気記号は( )。ただし、時間雨量に換算して15mm以上の強度で雨が降る場合は「雨強し」(
)。ただし、時間雨量に換算して15mm以上の強度で雨が降る場合は「雨強し」( ツ)、対流性の雲から降る雨(驟雨)は「にわか雨」に分類する。また、霰や雹、雷を伴う場合はそちらを優先して報告する[48][49]。
ツ)、対流性の雲から降る雨(驟雨)は「にわか雨」に分類する。また、霰や雹、雷を伴う場合はそちらを優先して報告する[48][49]。
航空気象の通報式[注 4]では「降水現象」の欄のRAが雨を表す略号。強度を表す付加記号、驟雨や着氷性の雨を表す略号もある[50]。
注釈
出典
- ^ 岩槻、p216
- ^ a b 気象観測の手引き、p61
- ^ a b c d e f g h i j k l グランド現代大百科事典、大田正次『雨』p412-413
- ^ 荒木、p42-43
- ^ a b c d e f g h i j k l 世界大百科事典、内田英治『雨』p475-476
- ^ a b 荒木、p75-77
- ^ a b 岩槻、p112, p118-120
- ^ Robert Fovell (2004年). “Approaches to saturation” (pdf). University of California in Los Angelese. 2015年4月7日閲覧。
- ^ 岩槻、p180-184
- ^ 小倉、p78-88
- ^ 荒木、p116-128
- ^ 小倉、p81, p85-92
- ^ 荒木、p77-82, p128-129
- ^ 武田、p31-34
- ^ 小倉、p87-88, 98
- ^ a b c d 荒木、p132-148
- ^ a b 小倉、p92-99
- ^ a b 小倉、p86, 89
- ^ 荒木、p77-82, 129-131
- ^ 荒木、p23-38
- ^ 荒木、p103-104
- ^ 武田、p139-140, 142-153
- ^ 日本大百科全書、礒野謙治「雨量の分布」
- ^ a b c d 武田、p142-153
- ^ 『キーワード 気象の事典』初版、p247、朝倉書店、2002年。ISBN 4-254-16115-8
- ^ 「雨の強さと降り方 平成12年8月作成、平成14年1月一部改正」気象庁、2015年4月18日閲覧
- ^ a b 「天気予報等で用いる用語 降水」
- ^ 「気象庁ホームページにおける気象情報の配色に関する設定指針」気象庁、2020年7月、2023年2月5日閲覧
- ^ 武田、p8-9
- ^ a b c 荒木、p77-82
- ^ a b 気象観測の手引き、p61
- ^ 荒木、p78-79
- ^ 武田、p24-25
- ^ 武田、p14-15
- ^ a b c 地球と宇宙の化学事典、p154
- ^ 地球と宇宙の化学事典、p149
- ^ Daisy Yuhas. "Storm Scents: You Can Smell Oncoming Rain", Scientific American, 2012-07-18, 2015年4月20日閲覧
- ^ “あの独特な「雨の匂い」の正体、知ってる?”. TABI LABO編集部. TABI LABO (2023年11月2日). 2023年11月3日閲覧。
- ^ a b 日本大百科全書、礒野謙治「珍しい雨」
- ^ 「原爆の記録 黒い灰・黒い雨」、長崎市、2015年4月19日閲覧
- ^ a b c d 武田、p16-20
- ^ 「地域気象観測システム(アメダス)」気象庁、2015年4月18日閲覧
- ^ 「気象レーダー」気象庁、2015年4月18日閲覧
- ^ a b 日本大百科全書、礒野謙治「降雨の記録」
- ^ a b 日本大百科全書、礒野謙治「雨の観測と予報」
- ^ 「国際式の天気記号と記入方式」、気象庁、2023年2月5日閲覧。
- ^ 過去の気象データ検索 > 「天気欄と記事欄の記号の説明」、気象庁、2023年2月5日閲覧。
- ^ 理科年表FAQ > 山内豊太郎「天気の種類はいくつあるのですか。その記号も教えてください。」、理科年表オフィシャルサイト(国立天文台、丸善出版)、2008年3月、2022年2月5日閲覧。
- ^ 宮澤清冶『最新天気図と気象の本-天気図を見るとき読むとき書くとき』、国際地学協会、1991年。ISBN 978-4771810068
- ^ 「METAR報とTAF報の解説」、那覇航空測候所、2023年2月5日閲覧。
- ^ 地球と宇宙の化学事典、p151, p155
- ^ 日本大百科全書、礒野謙治「雨と人間」
- ^ 日本大百科全書、礒野謙治「人工増雨」
- ^ a b c d e f g 世界大百科事典、飯島吉晴、吉田敦彦『雨』p475-476
- ^ a b c d e f 日本大百科全書、竹内利美「雨の民俗」、板橋作美「世界の伝承と俗信」
- ^ “Rain Gardens”. Soak Up the Rain. EPA (2016年4月28日). 2023年4月7日閲覧。
- ^ 雨水浸透・貯留機能の高い植栽基盤を用いた外構創出技術
- ^ レインガーデン(雨水浸透緑地帯) | グリーンインフラ
- ^ France, R. L. (Robert Lawrence) (2002). Handbook of water sensitive planning and design. Lewis Publishers. ISBN 978-1-4200-3242-0. OCLC 181092577
- ^ “Evapotranspiration and the Water Cycle”. www.usgs.gov. 2019年8月16日閲覧。
- ^ 「金星」、宇宙航空研究開発機構 宇宙情報センター、2015年4月20日閲覧
- ^ 「土星の衛星」、宇宙航空研究開発機構 宇宙情報センター、2015年4月20日閲覧
雨…
雨と同じ種類の言葉
固有名詞の分類
「雨」に関係したコラム
-
飲用として流通しているコーヒーの木には、「アラビカ種」と「ロブスタ種」の2つの品種があります。アラビカ種は世界のコーヒー生産量のおよそ80%を占めています。一方、ロブスタ種は世界のコーヒー生産量のおよ...
- >> 「雨」を含む用語の索引
- 雨のページへのリンク