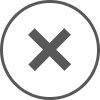【近接信管】(きんせつしんかん)
砲弾等が目標に命中しなくても、最接近時に起爆する事でダメージを与える事を目的とした信管。
概念
近接信管の概念は1930年頃には既にいくつか提案されており、ドイツでは既に開発も始まっていたといわれているが、アメリカではあまりにも複雑すぎるとしてほとんど省みられることがなかった。
これに関する特許も多数申請されていたが、概念のみで実用化へのアイデアが含まれていなかったことも関心を集めにくかった原因とされている。
しかし、1940年代に入り第二次世界大戦が激化するに伴い、航空機の進化に高射砲の性能が追いついていけないことが明らかになった。
日々高速化して行く航空機に対し、従来の時限信管や着発信管では、もはやこれらを捉えることが困難となっていた。
開発に至る経緯
アメリカでようやく近接信管の開発がはじめられた頃、イギリスではロケット弾や爆弾用の近接信管が既に実用化されていた。
しかし、20,000Gもの加速度が加わる砲弾には応用できないとされ、それ以上の研究は進んでいなかった。
航空機の進化による脅威を最も多く受けたのは海軍である。
それまで、航空機による対艦攻撃など取るに足りないと思われていたが、わずか数年で航空機の進化は艦艇の天敵となるまでに深刻さを増していた。
そのためアメリカ海軍は、主要対空火器であった5インチ砲に用いる近接信管の開発に非常に強い興味を示した。(後にイギリス海軍も開発に加わることとなった)
初期段階の研究では電気式、音響式、光学式、電波式などの様々な形式が取り上げられ、最終的には信頼性と生産性の面から光学式と電波式に絞って研究が進められた。
そして実用化には光学式の方が容易と判断されたため、まずは光学式の開発に重点がおかれた。
光学式は夜間や悪天候に弱いという弱点も認識されていたため、光学式の開発が終了すると、続いて電波式の開発に全力が注がれた。
電波式と言っても更に様々な形式に細分化することができたが、ドップラーレーダーを利用した方法が最も有効であると評価された。
実用化
砲弾が撃ち出されると、信管が作動し電波を発生させる。
信管は目標に反射された電波を自身で受信する。
砲弾が目標に近づいている間はドップラー現象により波長が小さく(高周波に)なるが、逆に遠ざかるようになると波長が大きく(低周波に)なる。
すなわち、受信する電波の波長が高周波から低周波に変化する瞬間がその砲弾が目標に最も接近した瞬間である。
電波式近接信管は、この低周波を捉えることにより起爆し、最も近くの目標に対し最も近くで砲弾を炸裂させることを可能とするものである。
開発は困難を極めた。最初に開発されたMark.32は大きすぎるだけでなく大量生産するには向いていなかった。
しかし、のべ1000人もの研究者が精密機器とも言うべきこの信管の開発に携わり、1941年9月までに世界で初めて信頼性と生産性を備えた電波式近接信管(いわゆるVT信管)の開発に成功した。
直接命中せずとも至近で砲弾を炸裂させるこの画期的な信管により、撃墜率は3倍になった。
その後の進化
この電波式近接信管は、最高軍事機密として保護されその後も改良が続けられた。
電波を斜め前方に発することで、起爆時のタイムラグを克服したりロケット弾やミサイル、野砲などにも応用された。
また、逆に自らが敵の電波式近接信管の脅威に晒された場合を想定して、これを妨害する方法も研究された。
近年では、電波式に替わってより精度の高いレーザー式の近接信管が開発され、各種の対空ミサイルで採用されている。
関連:マリアナの七面鳥撃ち
近接信管
近接信管
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 06:48 UTC 版)
信管から電磁波を発し、その反射波が一定以上の強さになった時点で動作する信管である。信管から一定の距離以内に目標が侵入した時点で動作する。最初期から現在まで最も一般的な近接信管は電波を利用する物であり、信管から発する電波の反射波が一定以上の強度になると動作する。最近ではレーザー光線を利用する近接信管も開発されている。
※この「近接信管」の解説は、「ミサイル」の解説の一部です。
「近接信管」を含む「ミサイル」の記事については、「ミサイル」の概要を参照ください。
近接信管
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/07 05:15 UTC 版)
「ドップラー・レーダー」の記事における「近接信管」の解説
詳細は「VT信管」を参照 攻撃対象に接近すると起爆する近接信管に使用される。
※この「近接信管」の解説は、「ドップラー・レーダー」の解説の一部です。
「近接信管」を含む「ドップラー・レーダー」の記事については、「ドップラー・レーダー」の概要を参照ください。
「近接信管」の例文・使い方・用例・文例
- 近接信管という起爆装置
- 近接信管のページへのリンク