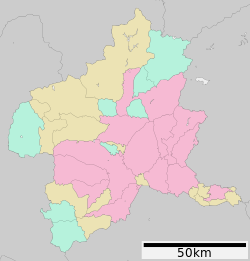甲を着た古墳人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 01:15 UTC 版)
概要
渋川市金井の金井遺跡群は、榛名山北東山麓に拡がる扇状地上に立地する。古墳時代当時の群馬県域は、浅間山や榛名山(二ツ岳)の大規模な噴火に度々見舞われており、当地域には6世紀初頭の噴火による「榛名山二ツ岳渋川火山灰(Hr-FA)」と、6世紀中頃の噴火による「榛名山二ツ岳伊香保軽石(Hr-FP)」という大量の火山噴出物(テフラ)が降下し、分厚い堆積層が形成された[1]。
榛名山二ツ岳の6世紀初頭の噴火の際には、火砕流を含む計15回にわたるHr-FAテフラの降下・堆積が確認されているが、二ツ岳の北東8キロメートルに位置する金井遺跡群の古墳時代集落は、最初の噴火と降灰の後に発生した火砕流の直撃を受け、瞬く間にテフラに埋没したと考えられている。この火砕流で被災した他の同時代遺跡として著名なものに、渋川市の中筋遺跡が知られる。また、6世紀中頃のHr-FPテフラにより被災した遺跡としては同市黒井峯遺跡が知られる[1]。
調査に至る経緯
渋川市内では、関越自動車道・渋川伊香保インターチェンジから長野県の上信越自動車道までを連絡する地域高規格道路・国道353号金井バイパス(上信自動車道)の建設が行われており、道路敷設予定地域に存在する埋蔵文化財包蔵地について公益財団法人群馬県埋蔵文化財調査事業団による発掘調査が行われていた。このうち金井東裏遺跡域内を通過する道路建設部分では、道に沿った細長い調査区が設定され、内部を13区に細分して2012年(平成24年)9月から発掘調査が開始された[2]。
甲を着た古墳人の発見
9月に調査が開始された金井東裏遺跡では、Hr-FA層とHr-FP層が合わせて2メートル以上堆積していた[1]。その下から、古墳時代後期の竪穴住居や溝状遺構、道路、5世紀後半の古墳2基などが発見された。そして11月19日には、第4調査区の31号溝と命名された溝状遺構から「甲を着た古墳人」が発見された[3]。
注釈
出典
- ^ a b c d 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2013b, p. 1.
- ^ 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2014a, p. 1.
- ^ a b 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2014a, p. 2.
- ^ 橋本 2009, pp. 27–30.
- ^ a b 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2015, pp. 1–2.
- ^ 行橋市教育委員会 2005, pp. 132–133.
- ^ 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2016, pp. 1–2.
- ^ a b c 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019a, p. 2.
- ^ 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2013a, p. 2.
- ^ 能登健「発掘調査から読み解く古墳時代の災害」『ここまでわかった!「古代」謎の4世紀』、新人物文庫、2014年、p.182.
- ^ 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2013c, pp. 1–2.
- ^ 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2019b, pp. 1–2.
- ^ 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2014b, pp. 1–2.
- ^ “よろいを着た古墳人、正体は村の長? 火山の下から覚醒”. 朝日新聞. (2020年6月13日) 2020年12月17日閲覧。
- ^ 群馬県埋蔵文化財調査事業団 2013d, pp. 1–2.
- 1 甲を着た古墳人とは
- 2 甲を着た古墳人の概要
- 3 出土状況
- 4 意義
- 5 参考文献
- 6 関連項目
- 甲を着た古墳人のページへのリンク