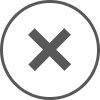内生生物
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/12/03 10:16 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動ある生物にとって、他の生物への共生が生存に必須である場合、その生物にとって共生は絶対または偏性(obligate)であるという。多くの場合、内部共生は内生生物と宿主のどちらにとっても偏性である。ハオリムシ類(シボグリヌム科)がその例であり、その内生菌から栄養素を得ている。昆虫と共生するボルバキアも偏性内生生物の例である。しかし、全ての内部共生が宿主にとって生存に必須なものではなく、内生生物か宿主かのどちらかにとってだけ有益な例も存在する。バンクロフト糸状虫Wuchereria bancroftiや常在糸状虫Mansonella perstansなどは人間や昆虫の寄生虫であり、昆虫を介して人間体内に侵入すると考えられている。
真核生物にとって最も一般的な細胞内小器官であるミトコンドリアと、葉緑体などの色素体は元々、内生細菌であったとされる。この定説を細胞内共生説という。細胞内共生説は、異なる生物の統合による新生物の誕生(シンビオジェネシス)の考えに基づく。この考えは1905年に最初に考え出され、1910年にロシアの植物学者Konstantin Mereschkowskiによって公表された[2][3]。
目次
細胞内小器官の内部共生
真核生物にとって最も一般的な細胞内小器官であるミトコンドリアと、葉緑体などの色素体は元々、内生細菌であったとされる。これら細胞小器官の起源は、食作用で真核細胞に取り込まれた細菌であるとされる。取り込まれた後に細菌は細胞内で進化を繰り返し、宿主と細菌は共生関係になったとされる。この仮説を細胞内共生説という。
細胞内共生説では、ミトコンドリアの前身となった好気性細菌を嫌気性細菌が取り込んだにもかかわらず、消化に失敗したことになる。細胞質は消化途中の栄養源で満たされており、内生細菌にとって好ましい環境であったと考えられている。内生細菌が好気呼吸により細胞質内の物質からアデノシン三リン酸を合成し、その一部を宿主の細胞質に供給したと考えられている。この供給は嫌気性の宿主に好気呼吸を可能にさせ、それによるエネルギーを与える。最終的に、内生細菌は独立することができなくなり、細胞内小器官となった。
葉緑体の起源はミトコンドリアのそれと近しい。昔、真核細胞が光合成性の藍藻を取り込み、消化に失敗したと考えられている。そして、ミトコンドリアと同様に細胞内で生息するうちに葉緑体となったとされる。他の細胞内小器官も内生細菌に由来するかもしれない。繊毛や鞭毛、中心小体、微小管は元々、スピロヘータと初期真核細胞の間の生物であったという意見がある。
細胞内共生説の根拠はいくつかある[4]。ミトコンドリアと色素体は、宿主のものとは異なる独自の少量のDNAを持つ。このDNAは、オルガネラが独立した好気性細菌であったときのゲノムの名残である可能性がある。また、ミトコンドリアと色素体のゲノムが細菌の系統樹に照らし合わされた結果、ゲノムから細菌のDNA配列が発見された。ミトコンドリアは、アルファプロテオバクテリア門の細菌が起源であることを明確に示すDNA配列を持つ。色素体は、藍藻を起源とするDNA配列を持つ。
さらに、原核細胞に好気性細菌が内部共生した過程を反映したような生物が発見されており、これは真核細胞と細胞内小器官との関係に非常に類似している。例えば、大型アメーバPelomyxaはミトコンドリアを持たないが、好気性細菌を保有し、これが同様の役割を果たす。イシサンゴ目のサンゴの一部や二枚貝、嚢舌類の腹足類の一部、ミドリゾウリムシなど繊毛虫の一種は細胞内に藻類や化学合成細菌をその生涯にわたって保有する。また、昆虫の内生菌の多くは太古から宿主との共生関係を続けており、その関係は垂直感染により子孫へと受け継がれている。
加えて、昆虫内生菌のゲノム進化の過程は、細胞内共生説での内生細菌から細胞内小器官への進化過程と類似する。類似点とは例えば、ゲノム量の減少、ゲノム進化の速さ、そしてヌクレオチドにおいてグアニンとシトシンが減りアデニンとチミンが豊富となる配列変化である。
細胞内共生説の更なる証拠として、葉緑体およびミトコンドリアには原核生物のリボソームと、それらを囲む二重膜が存在する。これまで、もともと独立していた時代の原核生物の膜が内膜であり、外膜は、最初に原核生物を呑み込んだ食細胞のもの(食細胞膜)であると広く考えられていた。しかしながら、この見解は次の事実に反する。i)現代の藍藻とアルファプロテオバクテリアの両方がグラム陰性菌であり、細胞膜は二重膜である。 ii)内在性細胞小器官(葉緑体およびミトコンドリア)の外膜において脂質およびタンパク質組成物はこれら細菌のものに非常に類似している[5]。これまでの生化学研究の知見は、細胞内小器官の進化中に、祖先細菌の二重膜が葉緑体とミトコンドリアのものとなり、食細胞膜が消失したことを強く示唆している。 ある種の藻類には三重または四重膜を持つものも存在する。恐らく内共生が繰り返された結果であろう(ごく稀に貪食細胞の膜が残っている場合もある)。
海洋無脊椎動物の内生細菌
細胞内部以外に生息する内生生物も存在する。細胞外内生細菌は棘皮動物門の4つの綱全て(ウミユリ綱、クモヒトデ綱、ウニ綱、およびナマコ綱)で発見されている。これらの細菌には共生生物としての一般的性質(感染、個体間や子孫間への伝播、代謝要求)はほとんど確認されていない。系統学的解析によると、これらの内生生物はアルファプロテオバクテリア綱に属し、リゾビウム属とチオバシラス属に関連している。別の研究では棘皮動物門において内生細菌は多種にわたって広く分布し、その菌数は非常に高い。
海洋性の貧毛類の一部(例えば、OlaviusやInanidrillus)はその全身に偏性細胞外内生細菌を持っている。これらは化学合成性の内生細菌に栄養的に依存しており、消化器系や排泄系(消化管、口腔、原腎管)を持たない。
- ^ Margulis, Lynn; Chapman, Michael J. (2009). Kingdoms & domains an illustrated guide to the phyla of life on Earth (4th ed.). Amsterdam: Academic Press/Elsevier. p. 493. ISBN 978-0-08-092014-6 2016年8月2日閲覧。.
- ^ Mereschkowsky, Konstantin (1910). “Theorie der zwei Plasmaarten als Grundlage der Symbiogenesis, einer neuen Lehre von der Ent‐stehung der Organismen.”. Biol Centralbl. 30: 353‐367.
- ^ Mereschkowsky C (1905). “Über Natur und Ursprung der Chromatophoren im Pflanzenreiche”. Biol Centralbl 25: 593–604.
- ^ Tree of Life Eukaryotes
- ^ Inoue, K (2007). “The chloroplast outer envelope membrane: the edge of light and excitement”. Journal of Integrative Plant Biology 49 (8): 1100–1111. doi:10.1111/j.1672-9072.2007.00543.x.
- ^ Baker AC (November 2003). “FLEXIBILITY AND SPECIFICITY IN CORAL-ALGAL SYMBIOSIS: Diversity, Ecology, and Biogeography of Symbiodinium”. Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics 34: 661–89. doi:10.1146/annurev.ecolsys.34.011802.132417.
- ^ Douglas, A E (1998). “Nutritional interactions in insect-microbial symbioses: Aphids and their symbiotic bacteria Buchnera”. Annual Review of Entomology 43: 17–38. doi:10.1146/annurev.ento.43.1.17. ISSN 0066-4170. PMID 15012383.
- ^ S. Aksoy, A. A. Pourhosseini, A. Chow (February 1995). “Mycetome endosymbionts of tsetse flies constitute a distinct lineage related to Enterobacteriaceae”. Insect Molecular Biology 4 (1): 15-22. doi:10.1111/j.1365-2583.1995.tb00003.x.
- ^ Susan C. Welburn, I. Maudlin & D. S. Ellis (1987). “In vitro cultivation of rickettsia-like-organisms from Glossina spp”. Annals of Tropical Medicine & Parasitology 81 (3): 331-335.
- ^ The Viruses That Make Us: A Role For Endogenous Retrovirus In The Evolution Of Placental Species (by Luis P. Villarreal)
- ^ Villarreal LP (October 2001). “Persisting Viruses Could Play Role in Driving Host Evolution”. ASM News (American Society for Microbiology). オリジナルの2009年5月8日時点によるアーカイブ。.
- 1 内生生物とは
- 2 内生生物の概要
- 3 海洋性の後生動物と原生生物の内生渦鞭毛藻
- 4 脚注
- 内生生物のページへのリンク