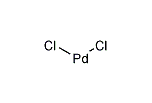二塩化パラジウム
塩化パラジウム(II)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/15 01:16 UTC 版)
| 塩化パラジウム(II) | |
|---|---|
 |
|
 |
|
 |
|
|
別称
Palladium dichloride, Palladous chloride
|
|
| 識別情報 | |
| CAS登録番号 | 7647-10-1  |
| PubChem | 24290 |
| ChemSpider | 22710 |
| UNII | N9214IR8N7  |
| EC番号 | 231-596-2 |
| RTECS番号 | RT3500000 |
|
|
|
|
| 特性 | |
| 化学式 | PdCl2 |
| モル質量 | 177.326 g/mol (無水和物) 213.357 g/mol (二水和物) |
| 外観 | 暗赤色固体 吸湿性 (無水和物) 暗褐色の結晶 (二水和物) |
| 密度 | 4.0 g/cm3 |
| 融点 | 679℃ (分解) |
| 水への溶解度 | 微量に溶け、冷水に溶けやすい |
| 溶解度 | 有機溶媒に溶ける 塩酸にはすみやかに溶ける |
| 磁化率 | −38.0×10−6 cm3/mol |
| 危険性 | |
| 半数致死量 LD50 | 2704 mg/kg (ラット, 経口) |
| 関連する物質 | |
| その他の陰イオン | フッ化パラジウム(II) 臭化パラジウム(II) ヨウ化パラジウム(II) |
| その他の陽イオン | 塩化ニッケル(II) 塩化白金(II) 塩化白金(II,IV) 塩化白金(IV) |
| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |
塩化パラジウム(II)(えんかパラジウム(II)、Palladium(II) chloride)は、代表的なパラジウムの塩化物で、茶色い粉末状の外見をもつ、無機化合物である。組成式はPd(II)Cl2。
性質
塩化パラジウム(II)の固体の中では、各パラジウム中心の周りに4個の塩素が平面四配位型構造の形で配位し、それぞれの塩素はさらに別のパラジウム中心にも配位した架橋となっている(μ-クロロ錯体)。この架橋構造がポリマー状に連続した無限構造のため、そのままの形では水に不溶であるが、ここに塩化物イオンを付加させるとテトラクロロパラデートイオン PdCl42− の形でポリマー構造が分解し、水に溶解する。
用途
カップリング反応などの有機合成反応の有用な触媒、テトラキス(トリフェニルホスフィン)パラジウム(0) (Pd(PPh3)4) や PdCl2(PPh3)2、Pd2(dba)3 など、さまざまなパラジウム錯体を合成するための出発物質として用いられる。塩化パラジウム(II)自身も、ワッカー酸化などの反応触媒として用いられる。
出典
- 塩化パラジウム(II)のページへのリンク