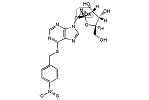S‐(4‐ニトロベンジル)‐6‐チオイノシン
| 分子式: | C17H17N5O7S |
| その他の名称: | 6-(4-Nitrobenzylthio)-9H-purine-9-yl β-D-ribofuranoside、S-(4-ニトロベンジル)-6-チオイノシン、S-(4-Nitrobenzyl)-6-thioinosine、NBTI |
| 体系名: | 6-(4-ニトロベンジルチオ)-9H-プリン-9-イルβ-D-リボフラノシド |
チタン‐ニオブ
NBTI
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/27 08:39 UTC 版)
NBTI(エヌビーティーアイ)とは、(英語: Negative Bias Temperature Instability : 負バイアス温度不安定性)の略で、P型半導体(PMOS)の劣化メカニズムのひとつ。古くはスロートラップ現象と呼ばれていた。1990年代はじめに観測された現象で、加工プロセスの微細化に伴い顕在化している。
概要
トランジスタのゲート電極に対し基板の電位が負の状態でチップの温度が上昇すると、P型トランジスタの閾値電圧(Vth)の絶対値が徐々に大きくなりトランジスタの特性(Ids , Vth)が変動する現象。負バイアスが印加されない状態では変動した特性が急速に回復するが、負バイアスが印加された状態では、トランジスタの動作にかかわらず素子劣化が進行する。ただし、負バイアスと正バイアスを交互に繰り返すAC動作では、正バイアス印加の際に負バイアスとは逆の反応が起き特性が回復する為、NBTI 寿命が向上する。NBTI劣化は、印加電圧を下げることで緩和される。
最終的には半導体素子の故障につながる。
pMOS(PMOS) トランジスタは、金属 - 半導体酸化膜 - 半導体の三層構造(MOS:Metal Oxide Semiconductor)になっている半導体素子のうち、正孔(ホール)が電流を運ぶタイプ。
劣化メカニズム
2013年時点では、メカニズムは解明されていない。しかし、Reaction Diffusion モデルが有力と考えられている[1]。
- PMOSのゲートに負バイアスを印加すると、Si基板表面に反転層が形成され、正孔が集まる。(エネルギーの高いホットホールが発生)
 カテゴリツリー
カテゴリツリー  コモンズ・カテゴリツリー
コモンズ・カテゴリツリー
ニオブチタン合金
(NbTi から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/19 15:15 UTC 版)
ナビゲーションに移動 検索に移動ニオブチタン合金 (Nb-Ti) はニオブとチタンの合金である。第二種超伝導体として知られ、超伝導磁石に広く使われている。転移温度は約10ケルビンである[1]。
1962年にアトミックス・インターナショナル社のT. G. ベルリンコートとR. R. ヘイクはニオブチタン合金が高い臨界磁場と高い臨界電流密度を両立し、しかも価格が手頃で作業性にも優れることを見出した[2][3]。ニオブチタン合金は他の数多くの超伝導体と比べても有用性が際立っていたことから、最も広く利用される超伝導体の地位を確立した。
ニオブチタン合金の最大臨界磁場は約15テスラで、最大で約10テスラまでの磁場を発生する超伝導磁石を作ることができる。より強い磁場が必要な場合には、ニオブチタン合金より高性能だが高価で製造も難しいニオブスズ合金が使われる。
2014年には超伝導体の市場規模は約50億ユーロに達した[4]が、そのうち約80%はニオブチタン合金を主に採用するMRI装置が占めている。
特筆される用途
超伝導磁石
アルゴンヌ国立研究所には、直径4.8メートルで1.8テスラの磁場を発生するニオブチタン合金製の超伝導磁石を備えた泡箱が設けられている[5]。
フェルミ国立加速器研究所にあったテバトロン加速器のメインリング (周長4マイル) には、約1000個のニオブチタン合金製超伝導磁石が用いられていた[6]。 この超伝導磁石には17トンのニオブチタン合金線を含む50トンの銅線が巻かれ[7]、動作温度4.5 Kで最大4.5テスラの磁場を発生させていた。
1999年にブルックヘブン国立研究所に設置されたRHICには全長3.8キロメートルの二重蓄積リングが設けられ、1740個のニオブチタン合金製超伝導磁石が発生する3.45テスラの磁場で重イオン線を周回させている[8]。
CERNが運用している大型ハドロン衝突型加速器 (LHC) には1200トンの超伝導線[9]が使われており、そのうち470トンがニオブチタン合金である[10]。動作温度は1.9 Kで、最大8.3テスラの磁場を発生させている。
国際宇宙ステーションに搭載されたアルファ磁気分光器にも液体ヘリウムで冷却されるニオブチタン合金製超伝導磁石が使われていたが、後に常伝導磁石に交換された。
国際協力で建設されている核融合実証炉ITERのポロイダル磁場コイルにもニオブチタン合金が使用されている。2008年には、試作コイルが動作電流52キロアンペア、発生磁場6.4テスラで安定動作を達成した[11]。
ドイツのヘリカル型核融合実験炉ヴェンデルシュタイン7-Xにもニオブチタン合金製超伝導磁石が使われている。
ギャラリー
関連項目
- ニオブスズ合金
- バナジウムガリウム合金
関連書籍
- Nb-Ti - from beginnings to perfection - discovery of the best compositions and conductor designs and fabrication methods.
出典
- ^ Charifoulline, Z. (May 2006). “Residual Resistivity Ratio (RRR) measurements of LHC superconducting NbTi cable strands”. IEEE Transactions on Applied Superconductivity 16 (2): 1188–1191. Bibcode: 2006ITAS...16.1188C. doi:10.1109/TASC.2006.873322.
- ^ T. G. Berlincourt and R. R. Hake (1962). “Pulsed-Magnetic-Field Studies of Superconducting Transition Metal Alloys at High and Low Current Densities”. Bull. Am. Phys. Soc. 2 (7): 408.
- ^ T. G. Berlincourt (1987). “Emergence of NbTi as a Supermagnet Material”. Cryogenics 27 (6): 283. doi:10.1016/0011-2275(87)90057-9.
- ^ “Archived copy”. 2015年5月17日閲覧。
- ^ “Superconducting Magnets”. HyperPhysics. 2019年1月4日閲覧。
- ^ R. Scanlan (1986年5月). “Survey of High Field Superconducting Material for Accelerator Magnets”. 2011年8月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年8月30日閲覧。
- ^ Robert R. Wilson (1978年). “The Tevatron”. Fermilab. 2019年1月4日閲覧。
- ^ “Archived copy”. 2009年12月7日閲覧。
- ^ Lucio Rossi (22 Feb 2010). “Superconductivity: its role, its success and its setbacks in the Large Hadron Collider of CERN”. Superconductor Science and Technology 23 (3): 034001. doi:10.1088/0953-2048/23/3/034001.
- ^ Status of the LHC superconducting cable mass production 2002
- ^ “Milestones in the History of the ITER Project”. iter.org (2011年). 2011年3月31日閲覧。 “The test coil achieves stable operation at 52 kA and 6.4 Tesla.”
- NbTiのページへのリンク