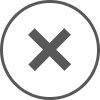フェルナン・メンデス・ピント
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/03 14:28 UTC 版)
『遍歴記』
1569年ごろから書き始めたものと言われている。1578年頃には全文を書き終えていたと推測されるが、生前は刊行されず、1583年の彼の死から31年を経て1614年に刊行された[12]。本書執筆時は、ヨーロッパ各地でザビエルの伝記や書簡集が多くの言語で続々と刊行された時期と重なる[12]。
完全な題名は以下の通りである。
『我々西洋では少ししかあるいはまったく知られていないシナ王国、タタール、通常シャムと言われるソルナウ王国、カラミニャム王国、ペグー王国、マルタバン王国そして東洋の多くの王国とその主達について見聞きした多くの珍しい事、そして、彼や他の人物達、双方に生じた多くの特異な出来事の記録、そして、いくつかのことやその最後には東洋の地で唯一の光であり輝きであり、かの地におけるイエズス会の総長である聖職者フランシスコ・ザビエルの死について簡単な事項について語られたフェルナン・メンデス・ピントの遍歴記。』
(古典ポルトガル語では: "Peregrinaçam de Fernam Mendez Pinto em que da conta de muytas e muyto estranhas cousas que vio & ouvio no reyno da China, no da Tartaria, no de Sornau, que vulgarmente se chama de Sião, no de Calaminhan, no do Pegù, no de Martauão, & em outros muytos reynos & senhorios das partes Orientais, de que nestas nossas do Occidente ha muyto pouca ou nenhua noticia. E tambem da conta de muytos casos particulares que acontecerão assi a elle como a outras muytas pessoas. E no fim della trata brevemente de alguas cousas, & da morte do Santo Padre Francisco Xavier, unica luz & resplandor daquellas partes do Oriente, & reitor nellas universal da Companhia de Iesus.")
なお、出版された本は原稿と同じ内容というわけではなく、ある文は消されており、他は「修正」されている。ピントが積極的にイエズス会に参加していた事が指摘されているにもかかわらず、イエズス会に言及した箇所が削除されており、これは注目する必要がある。
史実性
『遍歴記』の内容は、おそらく彼の記憶に基づく事実によって書かれたものと思われ、必ずしも正確な史料とは言えない。しかし、ヨーロッパ人がアジアに与えた影響、ポルトガル人の東洋における行動を現実的に分析し、記述しているといえる。
一番、疑問が投げかけられているのは、ピントがヨーロッパ人として最初に日本へ上陸し、銃を紹介した種子島漂着者3人のうちのひとりを自分と主張している部分であるが、イエズス会宣教師で日本語に精通していたジョアン・ロドリゲスはその著書『日本教会史』でそれを否定している[13]。多くの検証の結果として、ピントは鉄砲伝来年の翌年の1544(天文13)年に初めて薩摩半島の山川に渡来したとの説が有力視されている[2]。なお、ヨーロッパ人の初来航については、鉄砲伝来の2年前の1541(天文10)年にポルトガル船が豊後に流れ着いており、現在のポルトガルではこの年を「日本発見年」としている[2](発見のモニュメント)。
ピントが日本に降り立った人物であるということに対してはほとんど議論がない。つまり、後世の著述家による記録よりは『遍歴記』はある程度正確なものといえる。ザビエルの史料などから確実とされるのは、1551(天文20)年に豊後でザビエルと共に領主の大友義鎮(後の宗麟)に会見し、ザビエルが山口に修道院を建てるための資金を貸し、その後ザビエルとマラッカまで帰路を共にしたことである[12]。また、ザビエルの志を継いだインド準管区長メルキオール・ヌーニェスの日本視察を資金面で援助し、1556(弘治2)年に彼と共に再び豊後を訪問している[12]。
また別の信憑性に関する議論では、彼がジャワでムスリムと戦ったという記述についてである。これは様々な歴史家が分析を行ったが、オランダの歴史学者P. A. Tieleは1880年に、ピント自身はこの戦いに参加しておらず、彼が他人から得た情報で書いた物と推定した。しかし同時に、Tieleはその時代のジャワに関する情報が少ないことから、ピントの記録の重要性は認めている。つまり、ピント著述の正確性に疑問があるとしても、その時代を語る唯一の情報と言うこともある。
大英帝国の官僚として東南アジアに20年滞在した現代人モーリス・コリスは、ピントの記録はすべてが信頼できるものではないが、16世紀のヨーロッパで一番完成度の高いアジアの記録であり、基本的な出来事などに関する記述は大まかに信頼できるものとしている。
文学性
この『遍歴記』は現実とフィクションが織り交ぜられたもので、現代でいえば「冒険小説」の範疇に準ずる[2]。アントニオ・サライウヴァというポルトガル人文化史学者によって文学作品として大きく評価され、史実性の議論はともかく、文学としてとらえられる事もある。たとえばアントニオ・デ・ファリアに関する記述はピカレスク小説のようなものと見ることもでき、『遍歴記』に記される現地に住むアジア人から発せられる言葉はポルトガルに対して皮肉めいており、一種の風刺本と見ることもできる。
- ^ 『大航海時代 旅と発見の2世紀』(1985年)p.85
- ^ a b c d e f 「ほら吹きピント」の本当の話 メンデス・ピントがザビエルを支援する 2-1奥 正敬、京都外国語大学図書館、2006
- ^ 『大航海時代 旅と発見の2世紀』(1985年)p.87
- ^ Interracial Intimacy in Japan: Western Men and Japanese Women, 1543-1900 Gary P. Leupp, A&C Black, 2003
- ^ a b Cats, Rebecca Fernão Mendes Pinto and His Peregrinação Hispania [Publicaciones periódicas]. Vol. 74, No 3, September 1991, University of California, Los Angeles
- ^ De 18 a 20 de Maio, às 22 horas MOSTRA DE TEATRO AMADOR NO CENTRO CULTURAL VILA FLOR 16 May 2006, Municipio de Guimarães
- ^ 日本語訳者の岡村多希子はピントはユダヤ人ではなかったとしているが(訳者後書き)、カリフォルニア大学ポルトガル学部はピントがマラーノであったことが通説であるとラビ・M・トケイヤーは伝えている。『ユダヤ製国家 日本』徳間書店2006
- ^ “Fernao Mendes Pinto 6: Grave Robbery and Leeches” (英語). Human Circus (2024年1月17日). 2024年4月3日閲覧。
- ^ a b 宇田川武久 (2013-09-05). 日本銃砲の歴史と技術. 雄山閣. p. 39. ISBN 9784639022763
- ^ 伊川健二. “発見のモニュメントに潜む謎” (PDF). 2018年12月7日閲覧。
- ^ 伊川健二. “16世紀の日本と環シナ海域 ~海禁と拡張のはざまで~” (PDF). p. 30. 2018年12月7日閲覧。
- ^ a b c d 「ほら吹きピント」の本当の話 メンデス・ピントがザビエルを支援する 2-2奥 正敬、京都外国語大学図書館、2006
- ^ モタ朝日日本歴史人物事典
固有名詞の分類
- フェルナン・メンデス・ピントのページへのリンク