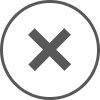第一インターナショナル
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/05 06:22 UTC 版)
普仏戦争論とパリ・コミューン論

マルクスと普仏戦争論
1870年の7月19日に勃発した普仏戦争によって年次大会は2年間延期となったが、IWAの活動はその間も活発に展開した。IWAは普仏戦争に対する反戦、第二帝政への批判を強めていたが、マルクスの個人的感想はまったく異なったものだったようである。7月20日、マルクスはエンゲルスに宛てた書簡でこのように述べている。
「フランス人たちは棍棒を必要としている。もしプロイセン人が勝てば、国家権力の集中はドイツの労働者階級の集中に有益だ。さらに、ドイツの優越は西ヨーロッパの労働運動の重心をフランスからドイツに移すことになるだろう。そして、これら両国における1866年から現在に至るまでの運動を比較してみただけでも、ドイツの労働者階級が理論的にも組織的にもフランスの労働者階級にも勝っていることを知るには、十分なのだ。世界の舞台におけるフランスの労働者階級に対するドイツの労働者階級の優越は、同時に、プルードンなどの理論に対する我々の理論の優越でもあるだろう。」[48]
マルクスは、ブリテンやフランスのような先発工業国による運動よりも、アメリカやドイツのような新興工業国の運動の方が未来を捉えていると考えていたようである。各国の労働者階級は母国の伝統や政治文化を抜けきれなかった。大掴みにいえば、ブリテン・フランス組は現状維持的な姿勢を持っており、アメリカ組、そして、ドイツの場合は「国家のための社会主義」を目指すラッサール派を別にすれば、社会主義革命を目指して歴史的大局的な見通しを重視するマルクス主義勢力が形成されるなど進取の精神を有していた性格の違いが背景にあった。こうした背景を俯瞰しつつ、各国労働運動の政治文化と自身の社会理論とを重ね合わさせるように見ており、プルードンの空想的社会主義に対するマルクスによる科学的社会主義理論の優越を主張していた。マルクス自身は自分の理論の科学性と新興工業国の労働運動とその先にある革命運動の革新性に期待していたのである。
マルクスの読みは的中する。普仏戦争はプロイセン側の圧勝で終わって、ナポレオン3世は投降した。そして講和条件に領土割譲―アルザス=ロレーヌの併合が浮上した。これを受けて、マルクスはプロイセン側の祖国防衛がやがて侵略戦争へと変貌し、独仏間の確執が抜き差しならないものになっていくことに不吉な予感を抱く。1870年8月末、マルクスとエンゲルスは戦争について「ドイツがアルザスとロレーヌを奪うならフランスはロシアと組んでドイツと戦争するでしょう。それが破滅的な結果をもたらすことは言うまでもありません」とベーベル宛ての書簡において語り後日の憂慮を表明した。ドイツ統一を目指すプロイセン王国は、周辺の大国と覇権競争を繰り広げ、普墺戦争から普仏戦争へと、ある戦争から次の戦争をつくりだしてプロイセンの覇権を確立した。こうした展開の中からドイツ帝国が実現したのは歴史的必然だったとマルクス、そしてエンゲルスが見ていたことがうかがえる。だが、領土割譲をフランスに強いるのであれば、フランスの報復が近い将来に控えていることが容易に予想された。マルクスとエンゲルスにとって世界大戦の勃発は眼前に見えていたということが考えられる[49]。
マルクスとパリ・コミューン
一方、マルクスは9月9日に総評議会として「プロイセンによるアルザス=ロレーヌの併合」を非難する声明を採択するとともに『普仏戦争反対第二宣言』を発表した。マルクスは普仏戦争後の情勢不安に便乗したパリの蜂起に懸念を示し、プロイセン軍との戦時中に革命を試みるというのは不毛と考えて新政府との協力を説いていた。マルクスはひとたびパリ・コミューン革命が宣言されるとコミューン政府を支持した[50]。パリ・コミューンの歴史的経験はマルクスに刺激を与えた。そして、『フランスの内乱』を執筆して、総評議会の名で自身の見解を世界に発表した。著書においてはコミューン革命の経緯を辿りながら、革命の事績を総括するとともに、コミューン崩壊の原因を分析している[51]。そして、社会主義政党の必要性を説き、反革命勢力の一掃とプロレタリアート独裁の確立、社会主義国家の建設に関する本格的な議論を提示した。こうしたコミューン論は後にボリシェビキを指導したウラジーミル・レーニンによって徹底的に研究されてマルクス・レーニン主義思想として体系化され、ロシア十月革命の理論的支柱へと発展していく[52]。
- ^ a b 日本大百科全書(ニッポニカ) - インターナショナル コトバンク. 2018年10月15日閲覧。
- ^ a b ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - インターナショナル コトバンク. 2018年10月15日閲覧。
- ^ a b デジタル大辞泉 コトバンク. 2018年10月15日閲覧。
- ^ a b c ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 第1インターナショナル コトバンク. 2018年10月15日閲覧。
- ^ a b c 日本大百科全書(ニッポニカ) - インターナショナル#第一インターナショナル コトバンク. 2018年10月15日閲覧。
- ^ ベア 1975 pp.34-35
- ^ フォスター 1956 p.37
- ^ [[#CITEREFロイデン・ハリソン1972|ロイデン・ハリソン 1972]] p.19, p.39
- ^ [[#CITEREFロイデン・ハリソン1972|ロイデン・ハリソン 1972]] p.50
- ^ a b フォスター 1956 pp.40-41
- ^ フォスター 1956 pp.41-42
- ^ フォスター 1956 p.47
- ^ フォスター 1956 pp.47-48
- ^ フォスター 1956 p.48
- ^ フォスター 1956 p.49
- ^ フォスター 1956 pp.49-50
- ^ フォスター 1956 pp.50-52
- ^ a b フォスター 1956 p.55
- ^ フォスター 1956 pp.56-59
- ^ フォスター 1956 pp.58-59
- ^ フォスター 1956 p.53
- ^ フォスター 1956 p.54
- ^ a b フォスター 1956 p.64
- ^ a b [[#CITEREFマルクス,不破哲三2012|マルクス,不破哲三 2012]] p.288
- ^ [[#CITEREFマルクス,不破哲三2010|マルクス,不破哲三 2010]] pp.46-47
- ^ フォスター 1956 p.69
- ^ フォスター 1956 p.70
- ^ 佐喜真望(2007) pp.226-227
- ^ フォスター 1956 pp.71-72
- ^ フォスター 1956 p.72
- ^ a b c フォスター 1956 p.73
- ^ フォスター 1956 pp.73-74
- ^ フォスター 1956 p.74
- ^ フォスター 1956 pp.86-87
- ^ フォスター 1956 p.71
- ^ フォスター 1956 p.79
- ^ フォスター 1956 pp.75-76
- ^ フォスター 1956 p.77, p.80
- ^ フォスター 1956 pp.80-81
- ^ フォスター 1956 p.82
- ^ フォスター 1956 p.83
- ^ フォスター 1956 p.84
- ^ ハント 2016 p.301
- ^ a b ハント 2016 p.302
- ^ ハント 2016 p.303
- ^ [[#CITEREFマルクス,不破哲三2010|マルクス,不破哲三 2010]] pp.129-130
- ^ [[#CITEREFマルクス,不破哲三2010|マルクス,不破哲三 2010]] pp.131-133
- ^ [[#CITEREFマルクス,不破哲三2012|マルクス,不破哲三 2012]] pp.77-78
- ^ フォスター 1956 p.90
- ^ フォスター 1956 p.93
- ^ フォスター 1956 p.94
- ^ フォスター 1956 pp.98-100
- ^ フォスター 1956 pp.102-103
- ^ フォスター 1956 p.103
- ^ フォスター 1956 p.104
- ^ フォスター 1956 pp.104-105
- ^ フォスター 1956 p.105
- ^ フォスター 1956 p.107
- ^ 「ハーグ大会についての演説」1872年9月 マルクス・エンゲルス全集(18) 158ページ、不破哲三『科学的社会主義における民主主義の探求』40ページ
- ^ フォスター 1956 p.109
- ^ フォスター 1956 pp.107-108
- ^ a b フォスター 1956 p.110
- ^ フォスター 1956 pp.112-113
- ^ フォスター 1956 pp.117-118
- ^ フォスター 1956 pp.114-115
- ^ フォスター 1956 pp.119-120
- ^ フォスター 1956 p.122
- ^ フォスター 1956 p.123
- ^ フォスター 1956 p.108
- ^ フォスター 1956 pp.124-125
- ^ フォスター 1956 p.128
- ^ フォスター 1956 pp.128-129
- ^ フォスター 1956 p.130-131
第一インターナショナルと同じ種類の言葉
| 国際組織に関連する言葉 | IGO INGO 社会主義インターナショナル 第一インターナショナル |
固有名詞の分類
- 第一インターナショナルのページへのリンク