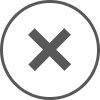スバス・チャンドラ・ボース
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/24 04:12 UTC 版)
死に対する議論
ボースの死の知らせを受けたインド総督アーチボルド・ウェーヴェルや連合国東南アジア方面軍司令官ルイス・マウントバッテンのみならず、ガンディーでさえも日本の発表を信じず、ボースが独立闘争の継続のために日本の協力のもとに逃亡したと考えていたように、公式情報を信じない向きはその当時から存在した[26]。また戦後からしばらくの間、世界各地でボースの目撃情報が相次いで伝えられている[26]。
加えてボースと近い立場にあったA.M.ナイルも自書内で、今や敗戦国となった日本を経由して日本の旧敵国のソ連へ向かおうとする事が不可能であったことや、ボースの敵であるイギリスと同じ連合国の1国であるソ連と協力を行おうとすることの不可解さ、さらに事故の際に「死んだ」とされる日本人の複数の同乗者がその後も生存していたことや、ボースとS.A.アイエルが持ち出した、宝飾品などを中心とした仮政府の資産が行方不明になっているとして、ボースの「飛行機事故死」に疑問を投げかけている。特にインドにおいてボースの事故死を信じない者を中心として、生存説を支持する論説もたびたび出されている[31]。
これらの疑問に対し、インド政府は過去3度にわたって調査委員会を組織し、1956年(シャー・ナワズ委員会、シャー・ナワズはインド国民軍で最高幹部の一員を務め、戦後のインド国民軍裁判被告のひとり)、1970年(コスラ委員会)、2006年(後述)にそれぞれ報告書を作成している。最初の2回(実施時の政権与党はいずれもインド国民会議派)は「飛行機事故で死亡し生存の可能性がない」と結論づけた。
しかし、インド人民党が与党であった1999年に組織した3度目の調査委員会であるムカルジー委員会は「飛行機事故は連合軍によるボースの追跡をかわすために日本軍が作り上げた」とし、蓮光寺の遺骨はボースのものではなく、ボースがすでに死亡していることは間違いないものの死因については「説得力のある証拠がない」として具体的に言及せず[注釈 1]、恐らくソ連に向かったとしたうえ、シベリアで厚遇されるボースを見たという証言、ソ連のニキータ・フルシチョフ第一書記が「45日以内にインド(当時はネルー首相)に返せる」と語ったなどの通訳の証言を集めた[33]。

この3度目の報告書が発表された2006年には、政権与党は再びインド国民会議派などによる統一進歩同盟 (UPA) 連立政権に移っており、発表時のインド政府はムカルジー委員会の「調査結果に同意しない」と表明した。ただし同意しない理由については「複数の友好国との関係」を理由に公表を拒んだ。
このほかボースの甥の妻は「政府の考えに賛成だ。墜落死には多くの証拠があり、遺骨はチャンドラ・ボースのものだ」とコメントした[34]。
その一方で、1985年9月にウッタル・プラデーシュ州ファイザーバードで死亡したバーグワンジー(またはグムナミ・ババ)という人物こそボースだったという主張もインドでは根強い[注釈 2]。
さらに2012年には 『India's Biggest Cover-up』という書籍が通常版、Kindle版で刊行されプラナブ・ムカルジー大統領の隠蔽工作への関与が名指しされて論争が再燃(最大級の英字紙ザ・タイムズ・オブ・インディアなど[35] 各メディアがこぞって取り上げた)、2013年1月にはイラーハーバード高等裁判所が実際にボースであったかの再調査を命じている[36]。
2017年5月30日、インド政府は市民団体の情報公開請求に対し、ボースが「1945年8月18日、飛行機事故のため台北で死亡したと結論付けた」と回答し、生存説を公式に否定した[37]。
注釈
出典
- ^ a b c d e f g 森瀬晃吉 1999, p. 58.
- ^ a b c パスモア 2016, p. 137.
- ^ a b c d e 森瀬晃吉 1999, p. 59.
- ^ a b 竹中千春 2018, p. 145.
- ^ a b c 竹中千春 2018, p. 147.
- ^ a b c d 森瀬晃吉 1999, p. 60.
- ^ 森瀬晃吉 1999, p. 70.
- ^ a b c d 森瀬晃吉 1999, p. 61.
- ^ 児島襄 1974, p. 154.
- ^ 森瀬晃吉 1999, pp. 61–62.
- ^ a b c 森瀬晃吉 1999, p. 62.
- ^ a b c 森瀬晃吉 1999, p. 65.
- ^ 森瀬晃吉 1999, p. 64.
- ^ 米田文孝・秋山暁勲 2002, p. 13.
- ^ a b 児島襄 1974, p. 156.
- ^ a b c d 森瀬晃吉 1999, p. 66.
- ^ 『黎明の世紀 大東亜会議とその主役たち』深田祐介著 文藝春秋 1991年[要ページ番号]
- ^ a b 森瀬晃吉 1999, p. 67.
- ^ 児島襄 1974, pp. 164–165.
- ^ a b c 森瀬晃吉 1999, p. 68.
- ^ a b 児島襄 1974, p. 169.
- ^ “印独立運動家チャンドラ・ボースの「ソ連亡命」を日本が終戦直前に容認 ”. 産経新聞. (2016年2月19日) 2016年7月8日閲覧。
- ^ 森本達雄 1972, p. 187.
- ^ 森本達雄 1972, p. 189.
- ^ a b c d e f 児島襄 1974, p. 170.
- ^ a b c d e 米田文孝・秋山暁勲 2002, p. 46.
- ^ 萬晩報「スバス・チャンドラ・ボース氏の最後の一日」- ハビブル・ラーマン大佐の回想
- ^ a b 橋本欣也 2009, p. 3.
- ^ 橋本欣也 2009, pp. 3–4.
- ^ a b 橋本欣也 2009, p. 4.
- ^ “The Enigma of Subhas Chandra Bose”. Hindustantimes.com. 2012年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月14日閲覧。
- ^ 朝日新聞2006年5月10日夕刊
- ^ “帝国日本の陰謀か?インド独立運動の英雄チャンドラ・ボースの死の謎”. ハイウェイエンジニアのインド観察 (2013年2月25日). 2021年9月14日閲覧。
- ^ 朝日新聞2006年5月22日夕刊
- ^ IB doctored document to prove govt line on Netaji's death: Book
- ^ “A quick note on the order (31 January 2013) by the Lucknow Bench of the Allahabad High Court on Gumnami Baba”. :: Subhas Chandra Bose :: (2013年2月). 2013年8月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年9月14日閲覧。
- ^ “独立の英雄「死亡」=政府、生存説を公式否定-インド”. 時事通信社. (2017年6月5日) 2017年6月5日閲覧。
- ^ a b 米田文孝・秋山暁勲 2002, p. 47.
- ^ “5 things about life and times of Subhas Chandra Bose” (英語). The Indian Express (2022年9月8日). 2022年9月10日閲覧。
- ^ 児島襄 1974, p. 160.
- ^ 児島襄 1974, p. 161.
固有名詞の分類
- スバス・チャンドラ・ボースのページへのリンク